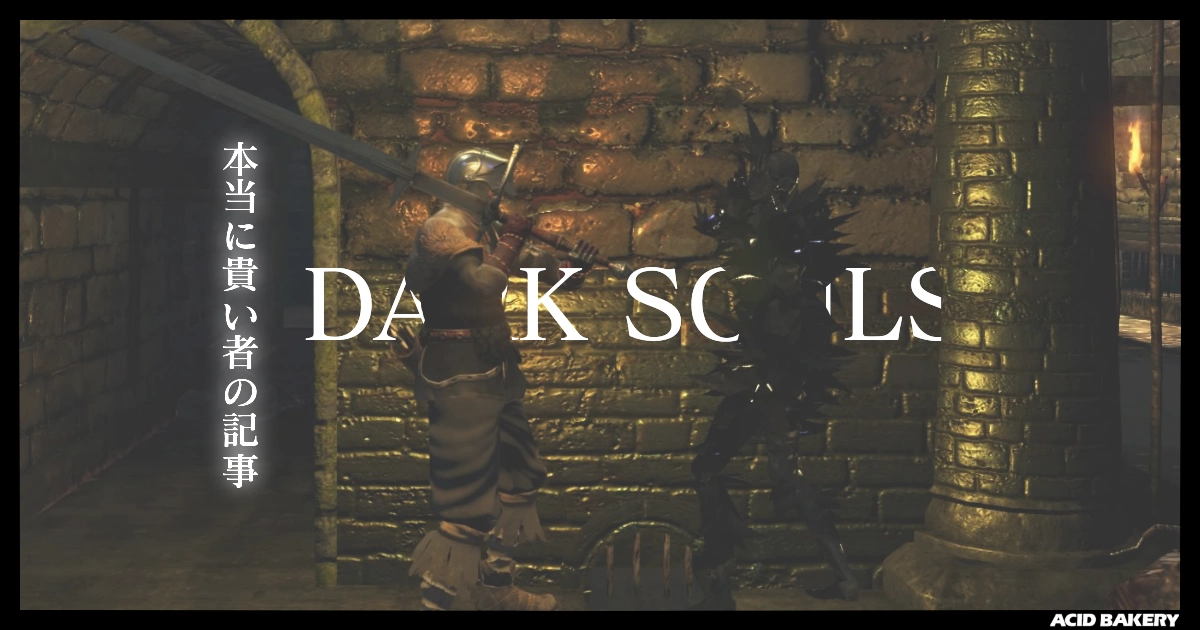罪の火は火に非ず(後編)
2019.10.14
前回の続きです。加えて一つご報告があるのですが、当記事では罪の火について完全な解明が出来なかったというような事を言いました。もちろん個人の空想なのでどこまで行っても「解明」とは言えませんし、結局これを書いている現時点でも出来ているつもりにすらなれていないのですが、前回の記事をアップしてからふとした思い付きがありまして、もしかすれば罪の火、その属性問題について「は」、説明がつくかもしれません。色々と難しく考えすぎていました。

闇に祈らば火が灯る

お願い! ダークネス
闇は火になれません。だって闇だもん。幾ら火を真似ようとも、それは何ものも生まぬ、闇属性の火である。しかし闇を素材に炎属性を熾した、そう思わしき例が一つあります。「混沌の炎」です。
混沌の炎
イザリスの溶岩石を削り出したデーモンの杖
炎属性の攻撃力を持った武器としても使える
デーモンの炎司祭は、最初のデーモンであり イザリスの魔女が混沌に飲まれる前の 呪術でない、炎の魔術の最後の使い手だった
デーモンの杖 - 『DARK SOULS』
イザリスの魔女たちが用いたという杖
後に混沌の火を生み出した彼女たちは 魔術師であると同時に祈祷師でもあり 故にこの杖は信仰補正を持っている
デーモンの杖 - 『DARK SOULS 3』
魔女イザリスは最初の火より王のソウルを取り出したものの一人。やがてそれは混沌の炎や呪術へと繋がっていく訳ですが、原初、彼女が見出したのはどうやら「炎」ではなく、「炎の魔術」でした。具体的にどう違うのかと言うと、分かりやすいところでは『1』デーモンの炎司祭が放つ熱波。これは炎属性ではなく魔力属性なんです。つまり「火の真似事」だった。
デーモンとは混沌が生んだ怪物です。なのでこの時期を境に「炎の魔術(魔力属性)」は「混沌(炎属性)」に入れ替わり始めていたと考えられます。ここら辺も謎が多いですが、以下の台詞がヒントになるでしょう。
「私の母イザリスはかつて最初の王の一人だった。最初の火のそばで、ソウルを見出し、その力で王になったんだ。……そして母はその力で自分だけの炎を熾そうとし ……それを制御できなかった。混沌の炎は母も妹も飲み込み、異形の生命の苗床にしてしまった」
クラーナ - 『DARK SOULS』
「その牢獄のずっと奥に“忘れられた罪人”がいるのよ。はじまりの火を生み出そうとした、バカな罪人がね 」
クラーナ - 『DARK SOULS 2』
二つ目のテキストに関しては『2』の四大ボス「忘れられた罪人」に対するものですが、あの罪人は魔女イザリスの成れの果て、しぼりカスのような存在です。つまり一度討伐されて尚、彼女は妄執の「続き」を行っていたという顛末でした。
原初、魔女イザリスは最初の火を作りたかった。しかし実際に仕上がったのは「炎の魔術」であり、それは魔力属性の、炎ですらないものでした。そこから何をどうしてか「混沌」という「炎属性」を獲得するに至り、しかし彼女達は自ら飲み込まれてしまいます。実際に何をしたかは明言されていませんが、以下の描写が糸口になるでしょうか。
『1』では人間性を篝火に捧げることで火が育つ訳ですが、一方で混沌武器は同じく人間性によって火力をアップさせました。
二つの炎が持つ共通した性質は何を暗示するものか。これは炎、「火」というものが持つ、「闇と合わさる事で勢いを増す」という根源的な特性を説明する為。そしてこれは「闇のソウルを持つ人(不死)こそが火継ぎを行う」という未来の暗示でもあったのでしょう。
その上で、イザリスは発想を変えます。火が闇によって育てられるのであれば、闇の解明こそ火に通じるのではないか。加えて言うなら、イザリス自身は「王のソウル」を有している訳です。王のソウルとは「はじまり火」の断片。これを闇と合わせれば……。と、そんな経緯があったかは全くもって不明ですが、闇のソウルが混沌に根差す仮説の補強としてもう一つ、闇に纏わる推測を加えたい。
重大なヒントです。「イザリスの杖」には「魔術師であると同時に祈祷師だった」なる一文がありました。『2』以降の呪術が理力・信仰補正を受けるようになったのはこの設定をより厳密にする為でしょうか。「闇」が持つある性質。それは「信仰補正」です。
闇の武器は闇攻撃力を持ち信仰による補正も高くなる。
闇の貴石 - 『DARK SOULS 3』
闇派生武器の性質だけを語ったテキストではありません。闇は「信仰」に感応するというフレーバーです。振り返ってみれば『1』でも、聖職者ほど多量の人間性を有していました。彼らは身内同士で助け合い人間性の確保を容易にしていたというような事を誰かが言っていましたが、むしろこの闇と聖職の親和性こそが本当の所かなと想像しています。人に内在する人間性(闇)が、宿主の信仰に刺激されたんです。信仰の力である奇跡とはそのほとんどが光(雷)として発現しますが、光と闇は元々一つだったことを考えると、光がそうであるように、闇もまた信仰に感応するんでしょう。
イザリスが闇に手を染めたとするなら、それまではどうだかわからなかった彼女達の「祈祷師」としての一面がようやく活きてくることになります。理力の業でしかなかった「炎の魔術」が、闇と合わさることで最強に見え、彼女達の祈りは遂に成就したんじゃないでしょうか。闇は魔女たちの祈りに感応し、炎を熾してみせたのかもしれません。
混沌の武器は炎攻撃力を持ち理力、信仰両方の補正を受ける。
闇の貴石 - 『DARK SOULS 3』
かくして「炎属性」は成り、しかしそれはどうやら呪われた炎でした。深淵がアルトリウスを暴走させ、ウーラシール市民たちを異形に変えたように、闇とは結びついたものをおぞましく歪ませる。だからこそ「混沌の炎」は、デーモンという怪物の苗床となってしまったのです。それは何かを産み出すという意味で「最初の火」に似ると言えなくもないですが、しかし後の時代になって尚もイザリスが「最初の火」を製造する事に囚われ続けた姿から察するに、混沌とは結局「最初の火のなりそこない」でしかなかったのでしょう。
と、そんな訳で闇が炎属性を生んだ実例として混沌の炎を挙げました。怪異を生む炎という観点からは、「混沌の炎」と「罪の火」は類似します。しかし同じものかと言えば、まあ違うわけです。由来に闇が関わるだけに混沌も罪の火も怪異を産み出しますが、罪の火のそれはデーモンではありません(罪の都の敵にデーモン特効は入らない)。そして何より混沌の炎は消えて無くなりました。例え闇を宿した、なりそこないの暴走の火だとしても、消えゆくそれは確かに「火」の一部だったようです。そこが二つの炎の、決定的な差異と言えます。
消えぬ故に火ではなく、しかし深淵に近いとされながら、闇属性ではなく炎属性として振る舞う罪の火。似た性質を持つ混沌と比較して理解を得ようとしましたが、より話をややこしくしてしまったかもしれません。しかし混沌を熾したイザリスの魔女たちの在り方は、罪の火に迫る非常に大きなヒントになります。
理力と信仰、両方上げろ
イザリスの魔女たちは、魔術師でありながら祈祷師でした。その在り方を念頭に置いて以下をお読みください。
深みの主教たちの礼拝の燭台
それは剣であると共に魔術の杖である
彼らは、冷たい谷のマクダネルの教えにより 聖職者でありながら、魔術師となったという
聖者の燭台 - 『DARK SOULS 3』
深みの聖堂の大主教に与えられる大杖
最高位の象徴にすぎなかった大杖は 大主教マクダネルの手で魔術杖となった
それは信仰を魔術の糧とする禁忌である
大主教の大杖 - 『DARK SOULS 3』
深みの主教たちが飛ばしてくるクッッソうぜえ火球、恐らくあれが彼らの魔術です。そして禁忌を破ってまでマクダネルがそれを伝えた理由として、恐らく深みを封じるという使命故だと考えられます。
深みの聖堂、その主教たちのローブ
エンジは火の加護を意味する
深みの封印者であったはずの彼らは やがて皆、おぞみに飲まれた
信仰も灯火も、役には立たなかったのだ
主教のローブ - 『DARK SOULS 3』
深みに飲まれた深みの主教たちは、元はその封印者でした。深淵を覗くものは深淵に飲まれる。
で、以下の画像も観て頂きたい。

マクダネル


マクダネル

場所はイルシールです。像のモデルはマクダネルでしょうか。わかり辛くて申し訳ないのですが、左の画像では魔術の杖と思わしきものを持ち、右では炎の灯ったカップと思わしきものを所持している。つまりマクダネルと、彼が伝えた炎の魔術についての像だと思われますが、なぜ聖職者であったはずの彼は魔術を推したのか。それはイルシールもまたある種の深みに侵されており、マクダネルはその対処法を知っていたからです。
冷たい谷には、月の虫が蔓延っている
青虫の丸薬 - 『DARK SOULS 3』
深みの聖堂に伝わる暗い奇跡
蟲の群れを召喚し、敵を蝕む
蝕み - 『DARK SOULS 3』
若き魔術師サリヴァーンが 絵画を去る前に残した魔術のひとつ
極低温の霧を発生させる
瞬間凍結 - 『DARK SOULS 3』
『3』で導入された状態異常「凍傷」、これの正体は月の虫による「蝕み」です。「FROSTBITE(凍傷)」は「FROST(冷たい) BITE(蝕み)」だったというオチ。
で、「蝕み」の蟲が深みからの侵食であるなら、月の虫もまた同様である訳です。どこまでおぞましかろうと蟲は蟲。深みの聖堂で受ける事が多い「蛆」状態は出血を伴いますが、松明を灯せば解除できますし、「凍傷」も炎ダメージを受けることで解除可能。蟲は炎に弱いんです。マクダネルが冷たい谷にいた頃、既に深みの封印者だったのかは不明ですが、月の虫もまた深みの一種だと捉えた場合、彼の対「深み」のノウハウと技術はその頃に培われたと見ていいでしょう。つまりは「いいから焼いちまえ」と。だからマクダネルは聖職者でありながら炎の魔術を伝えたんです。
お気づきでしょうか。主教たちの用いる炎の魔術は「炎属性」である訳です。炎属性の、炎の魔術。さらっと、イザリスが実現できなかった事をやってのけている。正直なぜ主教たちは炎を求めながら呪術を使わなかったのか、など疑問はあるのですが、本項で重要なのはこの一点。イザリスも主教たちも、共に聖職者でありながら魔術師でした。
そしてイザリスの魔女たちが自分達に決定的に欠けている「闇のソウル」を取り込む事で、「願いを叶えた」、つまり炎を熾したという仮説が正しいなら、人間という生き物は生まれながらにして所有している訳です。生来の闇、「人間性」を。
マクダネルが聖職者でありながら魔術師であるという両輪を主教たちに課したのは、イザリスが、自身と相容れぬはずの闇に手を出してまで叶えた「炎属性」に、元より闇持つ人間は「信仰と魔術」という手段で至れる事を知っていたからなのかもしれません。ちなみに証拠と言うには弱いかもしれませんが、深みの主教たちが放つ火球はエゲつないほどの追尾性能を有しています。これは彼らの炎の魔術が闇を元手にしているからではないでしょうか。
古く竜の学院が失った大魔術師 「ビッグハット」ローガンの独自魔術のひとつ
追尾性の高いソウルの塊を浮かべ、放つ
探求者たるローガンの一端が見える魔術だが 生命に惹かれるその性質において 後の研究では、むしろ闇に近いとされている
追尾するソウルの塊 - 『DARK SOULS 3』
これは地味に大切なポイントです。恐らく人間の持つソウルは、人間由来のものである時点で闇を含むんでしょう。扱うものによっては、その性質が色濃く出てしまうのだと。そして何より重要なのは、「属性」は必ずしもそのソウルの本質を反映しないという事です。
このともすれば当たり前の、しかし重要な気づきを与えてくれた「追尾するソウルの塊」。この魔術を学ぶことができるのはローガンのスクロールである訳ですが、どこで取得できるのかというと、そう、罪の都です。さて帰ってまいりました
繰り返しになりますが、炎を熾したイザリスの魔女たち、そして主教たちは「聖職者でありながら魔術師」でした。そして。
罪の都、その宮廷魔術師たちのフード
その黒く高い帽子が示唆するように 彼らはまた、神官でもあったという
宮廷魔術師のフード - 『DARK SOULS 3』
罪の都の宮廷魔術師。彼らもまた魔術師でありながら聖職者でした。イザリス、深みの主教、そして宮廷魔術師と、『3』ではやけにこの「魔術師かつ聖職者」という役割が推されている気がします。そしてそれぞれの傍らに「火」がある。何もない、と考えるのは個人的に難しい。
異形と化した罪の都の住人 その中にあった異様な武器
彼女たちはある神官の家族であり その呪いが、罪の火の切欠になったという
エレオノーラ - 『DARK SOULS 3』
罪の火の切欠になったという「呪い」が何かは不明です。しかしこのテキストで示された神官が、やはり魔術師を兼ねるのだとすれば、やはり深淵(闇)と「魔術と信仰」が火に繋がったという線には期待が持てます。
闇は信仰に応える。つまりは「願いを叶えてくれる」。だから魔術師でありながら聖職者でもある彼女達(彼ら)の願いに応え、それは炎属性と成ったんです。
罪の都、その地の深淵が願いに応えて熾した火。それが罪の火でした。
「属性」とはただの言葉
闇は炎属性になれない、などと前回色々言いましたが、難しく考えすぎていました。要するに属性とは表面的な特徴でしかなかったんです。
なぜ呪術「黒炎」が闇属性だったかと言えば、簡単な話、それが闇である事こそ望ましいと、見出した者が願ったからでしょう。シンプルに考えて良かったんです。闇はその気になって願えば炎にも変わる。ただし、その本質を闇のままに。
「火継ぎの大剣」に宿る火が最初の火そのもの、あるいは欠片のようなものだとして、その火はやはり炎属性である訳です。しかし同じ炎属性でありながら「混沌の炎」が「最初の火」に成り得なかったように、それは火を熾したソウルの本質を表しません。だから罪の火が炎属性である事と、その本質を闇とするであろう事は、矛盾しないんです。
そうなると気になるのは、なぜ同じく闇と関わりがあると思わしき混沌の炎は、罪の火のように「消えぬ火」足りえなかったのかという点。理屈をつけるなら、それこそイザリスの偉業なのだと思います。魔女イザリスとは「はじまりの火」に最も近き「王のソウル」を宿した者の一柱。闇に乞い願い、それは呪われた火となって成就したのだとしても、やはりそれは真に「炎」だったんです。
熾した火の主体が闇か否か。簡単に判断するなら、罪の火と混沌の炎の違いはそんなところだと理解しています。混沌の炎においては、闇は触媒に過ぎなかったと言い換えていいかもしれません。強いて付け加えるなら、後世「最初の火」の力が弱まってしまったであろう事と無関係ではないのかなと。罪の都の神官が何を願ったかは分かりませんが、火の影響が弱まった事で、その祈りを深淵(闇)が拾い上げてしまったという考え方もできるかと思います。だからこそ、その祈りの結果を鎮める為に、人々はヨームという薪を火にくべようとしたのではないでしょうか。
さて、補足として「属性」についてもう一つ。
思い出して欲しいのが、奴隷騎士ゲール編の終盤。彼は自身の肉体から、恐らく「呪い」のようなものを放ち、地面に暗い穴を穿ったかと思えば、そこを着弾点として雷が落ちました。

ダークソウルが呼んだ暗い雷

地面の穴は、不死の肉体に穿たれるものと同種でしょうか。そしてそれは、或いは深淵へと続くのでしょうか。今やゲール爺の血肉はダークソウルで満たされ、故に彼のソウルは闇と密接に結ばれています。それは人が持つ人間性などという卑小なレベルではなく、より深く、根源的な「闇」なのでしょう。
雷とは元来、光の業とされてきました。そしてそれは正しい。「白教の輪」を扱う事からも、ゲール爺は白教に属す、光を信仰の対象とする人間だったはずです。今や闇で充ちたゲール爺が、それでも雷を招来したのはその信仰心故でしょうか。
しかしてその雷は暗いのでした。



雷の対比

この暗さは何事か。これも単純なことです。闇が雷(属性)に変質したもの、つまり罪の火と同源の現象なんです。闇は祈りを聞き届けるが故に、炎にも雷にも容易に変質する。ただしその本質を闇としたまま。だから、種火を判定したアンドレイのように、見る人間が見ればゲール爺の雷に対してこう述べたんじゃないでしょうか。「暗すぎる。むしろ深淵に近いものだ」と。
という訳で改めて申し上げます。罪の火は火に非ず。炎の如き闇でした。
深海の時代
罪の火について取り合えずの仮説が立った事で、また「深海」についての想像が膨らみます。
深海の時代とは何か。それは「火」を根源とするソウル(神秘)が消え去り、ただ闇のソウルだけが残る世界です。それはかつて世界蛇カアスが述べた「闇の時代」に似て、しかし決定的に異なるものです。
深みは本来、静謐にして神聖であり 故におぞましいものたちの寝床となる
深みの加護 - 『DARK SOULS 3』
深みに潜む蟲たちは、小さな顎に牙を持ち 瞬く間に皮膚を裂き、肉に潜り込む
蝕み - 『DARK SOULS 3』
人の内にある最も重いもの。人の澱み
それはどんな深みにも沈み 故にいつか、世界の枷になるという
人の澱み - 『DARK SOULS 3』
人間性は「人の澱み」として深みへ沈み、そこで「おぞましいもの(おぞみ)」へと変態することが示唆されています。それはただ「蝕み」に代表されるような蟲に限定されません。



おぞましいメンバー紹介するぜ!




おぞましいメンバー紹介するぜ! - 2

言わば「人が人として生きるための当たり前の力」であった人間性が、人に牙を剥き、或いは人を人でないものへ変えてしまう。分かりやすく言えば、深海の時代とはこのような怪異が跋扈する時代なんです。ただ闇をエネルギーとして活用できたであろう「闇の時代」と決定的に異なる点はこれでしょう。火の時代が長く続きすぎたが故に、闇もまた想定を超えて深まったのかもしれません。
そんな訳で「罪の火」、これもまた深海の時代の脅威の一種なのだと思います。ゲール爺の降ろした暗い雷も同じ。闇はおぞましい生物としてのみ変化するのではなく、火の無くなった世界で、およそ闇とは呼べない振る舞いを手に入れる。言い換えるなら、深海の時代とは、それまで「火」によって抑圧されてきた「闇」が多様性を手に入れる時代なのです。ただし、そう、その本質を闇としたまま。
世界の差異の源となった、はじまりの火。その代替を闇が務める深海の時代。謎の解明にまた一歩近づいた、そう思って頂ければ幸いです。
罪
罪の火の属性についての疑問、何となく氷解した気がします。ついでのように深海の時代に触れる事も出来たので筆を置きたいところなのですが、これではまだ半分です。罪の火の「罪」ってなんだよ。
都の罪
仮説だけなら、実は簡単です。イザリスのそれに倣い、「はじまりの火を作ろうとしてしまった」ことを「罪」と結び付ければいい。「魔術師であり祈祷師だった」魔女たちが自らの産み出した炎に焼かれたように、「魔術師であり聖職者だった」都の神官もまた同じ事をした挙句、都を罪で焼いてしまった。罪の都とは廃都イザリスの再現なのだと思えばすっきりまとまります。
ちなみに上述したように、はじまりの火の再現に努めた者は「忘れられた罪人」として『2』では扱われ、「火の製造」は罪である事が仄めかされています。もう一つ加えるなら、『2』の呪術「炎の鎚」と『3』の呪術「罪の炎」が効果・アイコン共に酷似しているのはご存知でしょうか。
罪の炎
罪の炎 / 炎の鎚
「炎の鎚」の方の画質が荒いけど両方とも間に合わせです。説明すると長くなるのですが、切り取ったアイコンがどっか行っちゃって、もう一度用意するのがめんどいんです(そのうちやります)。ただ両者が似ている事は伝わったかと。
罪の炎に由来する呪術
離れた敵を炎で包み、焼き払う
巨人ヨームが薪の王となった後 罪の都は炎により滅びた
それは空より生じ、人々だけを焼いたという
罪の炎 - 『DARK SOULS 3』
古の国オラフィスの大魔術師、ストレイドによって生み出された呪術のひとつ
遠く離れた敵を巨大な炎で包み、焼き払う
大魔術師ストレイドは一切の弟子を取らず、ただただ術の世界に没頭したため その叡智の多くは失われている
炎の鎚 - 『DARK SOULS 3』
仕方がないのでギリガンも加えてやると、罪の都にはやけに『2』の要素が集っているように思えます。これらの事から、罪の都の「罪」とは、『2』の時点で示唆された「火の製造」に通じると考えて問題はないでしょう。考察として非常にまとまりがあって宜しい、あと『2』が強くピックアップされてて嬉しい! ……んですが、残念ながらこれでは腑に落ちない点がある。
上記「罪の炎」にあるテキスト、「巨人ヨームが薪の王となった後 罪の都は炎により滅びた」「それは空より生じ、人々だけを焼いたという」……これが分からない。本当に全然分からない。
罪の炎
問題をややこしくしていると思うので整理する意味で可能性を絞るのですが、「罪の炎」を「罪の火」と別個に捉える必要はないと考えています。それまでとは比較にならないほどの猛火、大きくなった罪の火を指して「炎」と呼んだのだと。
ちなみにですが呪術「罪の炎」は実際に「罪の火」に類するものを召喚している訳ではないと思っています。「罪の炎」には「罪の炎に由来する呪術」とありますが、これは「都が炎に焼かれた」というエピソードに着想を得た術師が、それを呪術を以て再現しただけに過ぎないのではないかと。
ウーラシールに迷い込んだある呪術師が 深淵の闇に見出した呪術
黒炎 - 『DARK SOULS』
覇王ウォルニールが深淵に落ちて後 墓守となった呪術師たちが見出した呪術
黒炎 - 『DARK SOULS 3』
こちらも同じ呪術であるのに経緯が異なります。両エピソードに関連性があるとしてもいいのですが、これは「異なる由来、異なる人物が同じ業を見出した」という話だと思っています。なので上述した「罪の炎」と「炎の鎚」に関しても同じ事が言えるかなと。何らかの繋がりはあるかもしれませんが、片やオラフィスのストレイドが探求によって、そして片や罪の都の惨状から何者かが、同じ業に到達したのだと納得しています。
さて問題はなぜ火の勢いが増したか、です。罪の火は深淵に近いもの。不死の呪いと同じく闇に根差すものであるが故に、人々は火継ぎによってそれを遠ざけようとしたと前回書きました。しかし結果は全くの逆。火継ぎにより、むしろ闇の力が増したかのようです。
分からん。助けてくれ。という事で幾つかの思い付きを書いておきます。後はお願いしますね。
取りあえずはこんなものでしょうか。一個ずつやっていきます。
最初の火が盛っている最中は不死の呪いが鎮まる、つまり闇が遠ざかる訳ですが、この「火と闇の反比例」は作為的なものだったようです。
古い人の武器は、深淵によって鍛えられ 僅かにだが生を帯びる
そしてそれ故に、持ち主たちと同様に 神々に火の封を施されたという
輪の騎士シリーズ - 『DARK SOULS 3』
そもそも人の祖たる誰も知らぬ小人が闇を見出したのは、世界に「火」が登場したればこそです。つまり火と闇は、本来であれば共にあるもの。不死も「火」の産物と言えます。それが今のように「火が弱まらなければ闇が強く存在できない」というおかしな状況になったのは、上記した通り「火の封」とやらが世界及び人類種悉くに施されたからなのでしょう。
だとして、これまでの火の弱まりと異なり、ヨームの時代に本格的な「火の陰り」が訪れたのだとして、そのせいで「火の封」もまた弱まったと仮定すれば、火の強さと闇の強さは正比例に戻っている事になり、つまり火継ぎと共に罪の火(深淵)もまた深まって、その火は大炎と化して都を焼いたのだ! ……とできれば何となく飲み込めなくはないのですが、これはちょっとおかしい。なぜなら火の封がこの時代既に外れてしまったのだとすると、火継ぎが不死の呪いを鎮めるというそもそもの前提が崩れる為、ヨームの時代以降、不死が発生し続けている事になりかねません。劇中でそこらへん何も触れられていないので別にそれでも構わないのですが、ちょっと飛躍の仕方が大きすぎるので、個人的感覚からしてこの線で推し進めたくはないかなあというのが正直な所。
「かつて我らの父グウィンは、火の陰りを憂い自ら薪の王となり 以来人の子ら、その英雄たちが、火を継いでいきました」
ヨルシカ - 『DARK SOULS 3』
はじまりの火継ぎを大王グウィンが行い、以来「人間」がそれを務めてきた。つまり「巨人ヨーム」もまた人間だった事が明言された訳です。
ただこれに関しては、ヨルシカの言を指して「お前は何もかも知っているのか」という疑念とセットです。また彼女の言葉を、劇中登場する「巨人」という種族もまた人間性を持つ「ヒト」の一種だったという意味と捉えていいのか、ヨームが「巨人のように大きな人間」だったと捉えるべきなのかで解釈が分かれる部分でしょう。どちらの線も決定的に否定されるものではないと思います。
当サイトにおいては、巨人もまた「人間」の一種だったという解釈を採用しているのですが、例えばヨルシカが知らないだけで、ヨームは人間が継いできた火の歴史の中で唯一例外的に薪の王となった「巨人(人外)」だったと考えてもいいかもしれません。
つまり「人間」が継ぐべきだった火を「巨人」が継いでしまったが故に、「罪」は大きくなったという仮説です。
都では神官が火の生成を望み、その罪を切欠に「火の如き闇」が熾り、そしてそれを鎮めようとして、人が成すべき火継ぎを人以外が行った罪が、火を煽る結果となった。即ち罪の都の罪とは、徹頭徹尾「火への冒涜」だったのだと。……筋は通っている気がしますが、ヨームが例外的な火継ぎを行ってしまったというなら、もうちょっとそこら辺がテキストで触れられててもいいような気がして、やはり個人的な感覚ですが「据わりが悪い」と思う次第です。
実は「ヨームの火継ぎを原因として罪の炎が人々を焼いた」とはどこにも書かれていません。
巨人ヨームが薪の王となった後 罪の都は炎により滅びた
罪の炎 - 『DARK SOULS 3』
「」のテキストには、単に時系列の話が記載されているだけです。だから民が願った「ヨームの火継ぎ」は罪の火を鎮める事に全く何の関与もせず、ただ単純に「何らかの別の理由」によって大きくなった罪の火により都は焼かれた、それが本当の所なのかもしれません。身も蓋もないですが、これが一番筋の通った説明と言えるでしょうか。
しかし「自身を慕う者などいないと分かっていて、それでも罪の火を鎮める為に自らを火へ投じたヨーム」という構図が美しいと感じる身としては、やはり都を救う為の火継ぎが都を滅ぼす原因となったという線を信じたいんですね(考察でも何でもねえな)。
とは言え全く唯の「気分」で申し上げている訳ではありません。
グウィン王が火継ぎに旅立ったとき 騎士たちは王を追い、再び熾った火に焼かれた
以来彼らは灰となり、世界をさまよい続けている
黒騎士の兜 - 『DARK SOULS』
ヨームの火継ぎが彼の治めた民たちを焼いた。思うにこの構図は、かつて大王グウィンが継いだ火によって、彼の騎士たちもまた焼かれた、その構図の「なぞり」になっていると思うんです。それはヨームを担ぎあげた心無き民たちと、グウィンに最後まで付き従った騎士たちの対比であり、それはそのまま罪の火と最初の火の対比になっている。なればこそ、ヨームの火継ぎが、罪の火を大きくした原因でなければならない、という願望です。
ただそうなると、やはり罪の火を熾した「罪」とは何か、そしてなぜ火継ぎによって「火(闇)」が大きくなったかという疑問に回帰します。何かしっくりくる仮説は無いのだろうか。
それは人々だけを焼いた
それは空より生じ、人々だけを焼いたという
罪の炎 - 『DARK SOULS 3』
次に気になるのはこれです。人々だけを焼いた? 人間だけを? なぜ?
人間性の闇に仮そめの意思を与え放つもの
その意思は人への羨望、あるいは愛であり 人々は目標を執拗に追い続ける
追う者たち - 『DARK SOULS 3』
追尾性の高いソウルの塊を浮かべ、放つ
探求者たるローガンの一端が見える魔術だが 生命に惹かれるその性質において 後の研究では、むしろ闇に近いとされている
追尾するソウルの塊 - 『DARK SOULS 3』
答えを求めるならここら辺だと思うんです。罪の火は闇である。だから炎のように振る舞いながらも、闇としての本質を手放せない。つまり「追う者たち」のように「目標を執拗に追い続け」、つまりは「人々だけを」焼いた。
が、ちょっとだけ首を傾げてしまうのが、闇とは「火」、つまり生命(ソウル)全般へと惹かれるのであって、追尾の対象は人に限定されるものではないんじゃないかという点です。これは「追う者たち」にあるように、人間性の一部分、「人への羨望」だけが強く反映された結果であり、より「人間的」と言える性質が罪の火(炎)には付与されているんじゃないかと解釈すれば、何とか頷けるでしょうか。
しかしちょっとした事を思いつきました。これこそ罪の火、その「罪」に関わる部分なのではないかという発想です。
罪の火の罪とは、まさしく「罪」だったのではないでしょうか。
罪の行方は
黒髪の魔女ベルカの伝える奇跡
短時間に大ダメージを受けると、自動的に反撃する
罪とは罰せられるべきものであれば 罪を定義し、罰を執行するのが 罪の女神ベルカの役目であろう
因果応報 - 『DARK SOULS』
古の女神にまつわる仮面
罪を司ると言われたこの神の名は 今はもう失われている
罪の仮面 - 『DARK SOULS』
罪の女神ベルカの管理する記録帳
罪人とは、神々や誓約を蔑ろにした者たちであり いつか暗月の刃に倒れる運命にある
罪人録 - 『DARK SOULS』
罪の女神ベルカの司祭が売っている符
他世界からの侵入者に殺されたとき、その侵入者の罪を告発する
告発された者は罪人録に載り いつか暗月の刃に倒れるだろう
告罪符 - 『DARK SOULS』
陰の太陽グウィンドリンに仕える 暗月の剣の騎士たちに与えられる神秘のオーブ
彼らはつまり、神々の復讐の刃なのだ
青い瞳のオーブ - 『DARK SOULS』
『ダークソウル』シリーズの肝、その一つとも言っていい「罪」というシステム。 NPC と敵対しても、それが罪として可視化されているが故に「赦される」事ができ、そして赦されざる罪人は暗月の誓約者によって誅される。そして免罪は、シリーズ通して「罪の女神」ベルカに関わる存在と共にありました。
一つ素朴な疑問があるのですが、火の時代の終わり、神々が消え去っていく傍ら、罪の女神ベルカもまた消えていく定めなのでしょうか。仮に彼女が消えゆくとして「罪」という概念も消えていくのでしょうか。
そしてもう一つ。さり気なくセットにされていた為に余り疑問に感じていなかったのですが、ベルカは「罪」だけでなく、どうやら「呪い」にも関わっていたようです。
犠牲の儀式によって作られる 罪の女神ベルカの、神秘の指輪
中でも、赤紫の色味を持つものは特別とされる
装備者は、死んでも何も失うことはなく おそろしい呪死すら無効化してしまうが この指輪は壊れてしまう
犠牲の指輪 - 『DARK SOULS』
さらにベルカの信徒である「カリムのオズワルド(『1』)」は「解呪石」を売り、「教戒師クロムウェル(『2』)」は「呪い咬みの指輪」を扱っている訳ですが、「罪の女神像(『3』)」に至っては直接解呪をしてくれます。「罪」と「呪い」の間には何らかの関連性がある。少なくともそういうメッセージを、シリーズ初期から伝えたかったのは間違いない、と思いたい。しかし罪とは……呪いとは……ベルカとは……と考えだすと訳が分からなくなるので、簡素に仮説を立てる事とします。
罪も「呪い」の一種であり、人のみに課せられるものである。
「呪い」とは何か。当サイトではそれを「死」として扱ってきました。
正確には、人は尋常の生命であれば一度きりの「死」を幾重にも溜め込んでおける。その仕組みは不死にとっての力である一方で「呪い」なのだと。そして上述の罪に関連するアイテムテキストを読む限り、罪は神が自らに徒為す『人』を裁く為の仕組みと読めます。だとしてそれは神の定めた、或いは人だけが持つ何らかの特性を利用して設定された、人だけを選んで発動する「呪い」と言い換えられます。罪の女神ベルカは、呪いの女神ベルカだったのかもしれません。
彼女たちはある神官の家族であり その呪いが、罪の火の切欠になったという
エレオノーラ - 『DARK SOULS 3』
エレオノーラと神官に関わる「呪い」とは、「罪」と言い換えられるでしょうか。
グウィンドリンやヨルシカが管理していた「暗月システム」は、罪人の元へ狂いなく射出される裁きの弾道でした。劇中、それが人以外へ向けられた事は無いと記憶しています。人間だけに設定された「罪」に従い、「罰」とはやはり人間だけを焼くように作られている。
つまり「罪の火」の「罪」とは、文字通りこの「罪」に則っていたのではないかと主張したい訳です。罪自体の内容は未だもって不明です。最初の火の製造に手を染めたからか、人以外が火を継いだからなのか、或いは『2』完全版の副題にある「原罪」とやらが関わるのか。前回最期に語ったように、それは取るに足らない罪なのかもしれない。或いは罪の都が戦争を行っていた事と関わりがあるのでしょうか。多くの戦死者の怨みが、この深淵の地では火の切欠となったのか……。一切合切分かってません。しかし罪の火が「人のみを焼いた」という事象は、この「罪」という「呪い」が作用した結果なのではないかと思うのです。なぜ罪の都だけが焼かれたのかと言えば、それは罪の都の人々に向けた「罰」故だったのではないでしょうか。
暗月が罪人を裁く仕組みに則り、罪の火は罪人を焼いたのです。
司る神がいなくなれば、暗月というシステムは消えるのでしょう。しかし罪というものが、人の生来背負う業ならば、それは神が無くとも残り続けるはず。罪の火とは神無き時代の、暗月に変わる「罰」なのかもしれません。
罪の火の罪と火
罪の都とは深淵の地でした。深淵(闇)と信仰、そして魔術が結びつくことでどうやら火は熾ります。それが「罪」となったのか、或いはその火こそが「罰」なのか、詳しい背景は分かりませんが、熾った罪の火は、神の裁きの如く都の人々に降り注いだ。これが現状想像できる範囲での、罪の火のあらましです。
ちなみにですがシリーズおなじみの奇跡「神の怒り」。これが取得できるのは、罪の都でした。神々は都の罪に怒っていたのでしょうか。しかしその地が深淵である為に、或いは火の陰りに神々もまた弱り切っていたのか、その怒りは正常に働かなかったのかもしれません。
罪。この業を人だけが背負わねばならぬとして、神による裁き(暗月)か、人の熾した罪の火か。どちらの罰が、マシなのでしょう。
その男、サリヴァーン
最後にサリヴァーンの話でもしましょうか。なんだか『3』のストーリーの裏で派手に動き回っていそうなこの男、実はよく分かっていないので、ここで多くは語らないのですが、しかしここまでの読み解きをした上だと見えてくるものがあります。その男サリヴァーンは、神に成り代わろうとした男なのだと。
若き魔術師サリヴァーンが 絵画を去る前に残した魔術のひとつ
極低温の霧を発生させる
絵画で生まれ育った彼にとって その冷たい地は、捨てるべき故郷であった
まだ何も、失ってさえいなかったのだ
瞬間凍結 - 『DARK SOULS 3』
法王サリヴァーンの持つ右手の剣
罪の火を称する儀式の剣
遥か昔、イルシールのはずれ
その地下に罪の都と消えぬ火を見出したとき 若き魔術師サリヴァーンの心にも消えぬ野心が灯ったのだろう
戦技は「罪の火」
罪の火を一時的に呼び出す技
罪の大剣 - 『DARK SOULS 3』
法王サリヴァーンの持つ左手の剣
月の裁きを称する儀式の剣であるが その魔力は、月よりもむしろ魔術に近い
暗い月よりも、なお暗い青色は 魔術師サリヴァーンの本質であったろう
戦技は「裁きの構え」
その刀身は構えにより暗い魔力を帯び 通常攻撃で踏み込み突き、強攻撃で横薙ぎの光波と状況に応じ使い分けられる
裁きの大剣 - 『DARK SOULS 3』
絵画世界とは世を追われた忌み人が集う地です。「失った者」の世界を出身とするサリヴァーンは、まだ何も失っていなかったが故に、絵画を脱したようです。思えばイルシールへの侵入に人形が必要である点は絵画世界と同じです。もしも「冷気」が、絵画世界から持ち込まれた、或いはサリヴァーンが蔓延させたものだとすれば、彼は捨てた故郷をイルシールへと再現したというような背景が見えてきます。それはサリヴァーンなりの郷愁なのか、単に便利だから利用しただけなのか。
ともかく、時系列は不明ですが、彼は罪の都の地下で罪の火を見出します。その消えぬ火がどのような野心を彼の心にもたらしたのか、具体的には分かりません。しかし上述の仮説に則れば、罪の火とは、文字通り「罪」の体現である訳です。
そしてもう一方の裁きの大剣。面白いのは「月よりも魔術に近い」という一文。『ダークソウル』シリーズにおける「月」とは信仰と切り離せません。もう少し言うなら、それは「暗月のタリスマン」に見られるように、「信仰を魔力に変換する」性質を指す訳です。その上でサリヴァーンの魔力は「月よりも魔術に近い」という。つまり月(信仰)の都に身を置きながら、サリヴァーンに信仰心など欠片も無かった事を意味するんじゃないかと思います。そりゃ神をエルドリッチの供物としますよ。たぶん少しの葛藤も無かったんじゃないでしょうか。
大きなポイントとして、裁きの大剣とは「月の裁き」を称するものであったこと。月の裁きとは、暗月の在り方そのものでしょうか。
要するに、です。サリヴァーンが振るった二本の大剣は、そのまま「罪」と「罰」、「ベルカ」と「グウィンドリン」という神の力、その顕現であった訳です。火の陰りにおいて、サリヴァーンは神の役割を担おうとしていた。故に「法王」なのだと。薪の王たちに玉座なし。しかし法王は一人、神の座に着こうとしていたのです。
付け加えるなら、サリヴァーンとは先の時代を見越していたように思います。「蝕み」とは深みの業であり、「冷気」とは冷たい蝕み、つまりはこれも深みの一種です。そして「罪の火」もまたある種の深みであるなら、サリヴァーンとは「冷気」と「消えぬ火」という、二つの深みを手にした事になる。
彼は陰った火の先に、深海の時代を見た。
エルドリッチのソウル - 『DARK SOULS 3』
サリヴァーンもまた同じものを見たのでしょうか。はじまりの火を根源とするソウルが消え去る以上、その後尚も残る闇(深み)へ活路を求めるしかない。サリヴァーンは、神々と「火」の存続を望む者達にとっての正しく「敵対者」であり、しかしその在り方は、次代を見据えた正道だったとも言えるのです。
その男サリヴァーン、神々に成り代わり、法を司らんとした者でした。
火の物語
なんだかよく分からないままですが、罪の火についてはこんな感じです。今はこれが限界。
改めてまとめると、
前編・後編と別れたこの記事の要点は以上の二つ。長くなりましたが、これだけ伝わってくれればいいかなと思います。
その黒炎は闇に非ず
という事で、おまけ。最後の最後、もう一つだけ触れておきたい「炎」がありました。修道女フリーデ、その黒炎です。
黒教会の指導者であった長女エルフリーデが 彼女の騎士に授けたという炎を模した剣
戦技は「エルフリーデの黒炎」
オーニクスブレード - 『DARK SOULS 3』
オーニクスブレードの黒い炎、そしてフリーデ第三形態が放つ黒い炎。上記した呪術「黒炎」を鑑みるに、これは人間性の、闇属性の炎だと思われるかもしれませんが、残念ながら炎属性です。こ、このアマ……! (「女性」と「尼」をかけた面白ギャグ)
フリーデの中で燻り続けたそれが、どんな意志の投影された炎だったのかは分かる筈もありません。しかし彼女は「火の無い灰」でした。灰とは名も無く、薪にもなれなかった呪われた不死だと言います。故に火を求め、彼女は絵画世界へ訪れました。
一人目の灰として絵画を訪れたフリーデは だが教父と共に、火ではなく腐れを選んだ
修道女フリーデのソウル - 『DARK SOULS 3』
何の決意か、灰でありながら彼女は、しかし火を選びませんでした。火の宿主であるアリアンデルと共にその燻りを封じ続けてきた。そして連戦を越え、通常であればボス撃破後、主人公に宿るはずの残り火は、フリーデへと宿ります。残り火の継承もまた、ある種の火継ぎだった。灰でありながら火を忌避し、それでも最後には、灰ゆえに起こしてしまった黒い炎。その正体は。
「『いつか灰はふたつ、そして火を起こす』
やはり君には、灰には、火が相応しい…」
教父アリアンデル - 『DARK SOULS 3』
火です。その黒炎は闇に非ず、きっと、嘘偽りのない、「フリーデの火」だった。
赤々と炎のように振る舞いながら、しかしその本質を深淵とした罪の火があった一方で、闇の如き黒色であった彼女のそれは、本物の火だった。これはそういう話なのだと思います。属性も、その色も、宿したソウルの本質ではないのだと。
『DARKSOULS』、闇の名を冠したこの世界は、しかし始まりから終わりまで、火の物語でした。
追記(2019.12.08)
続き書きました。