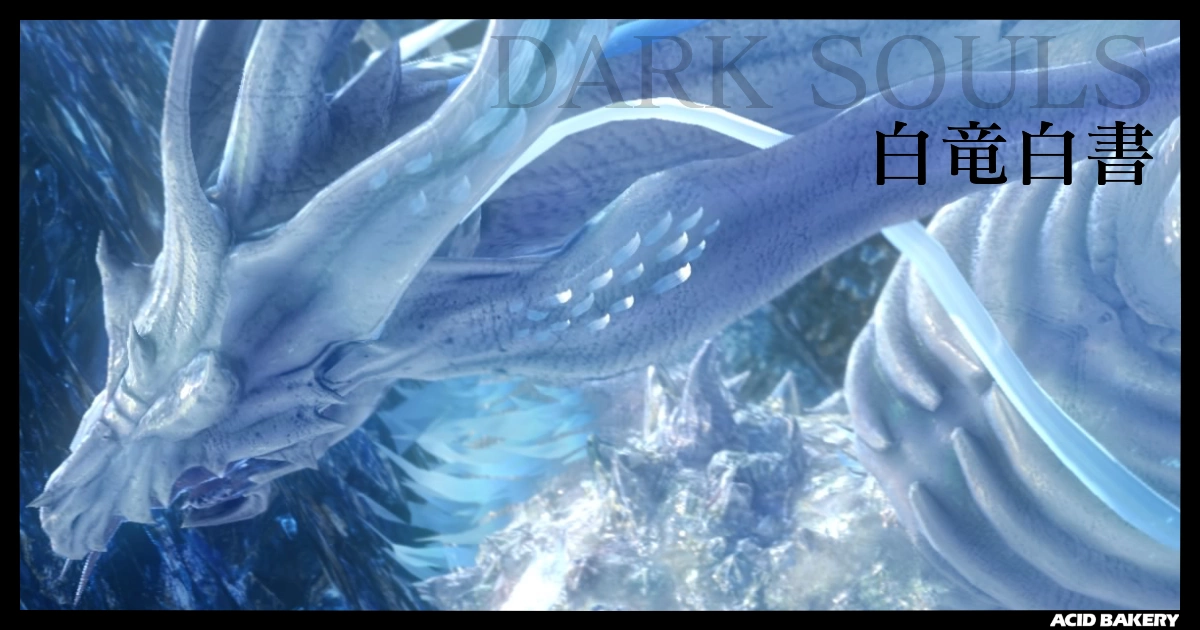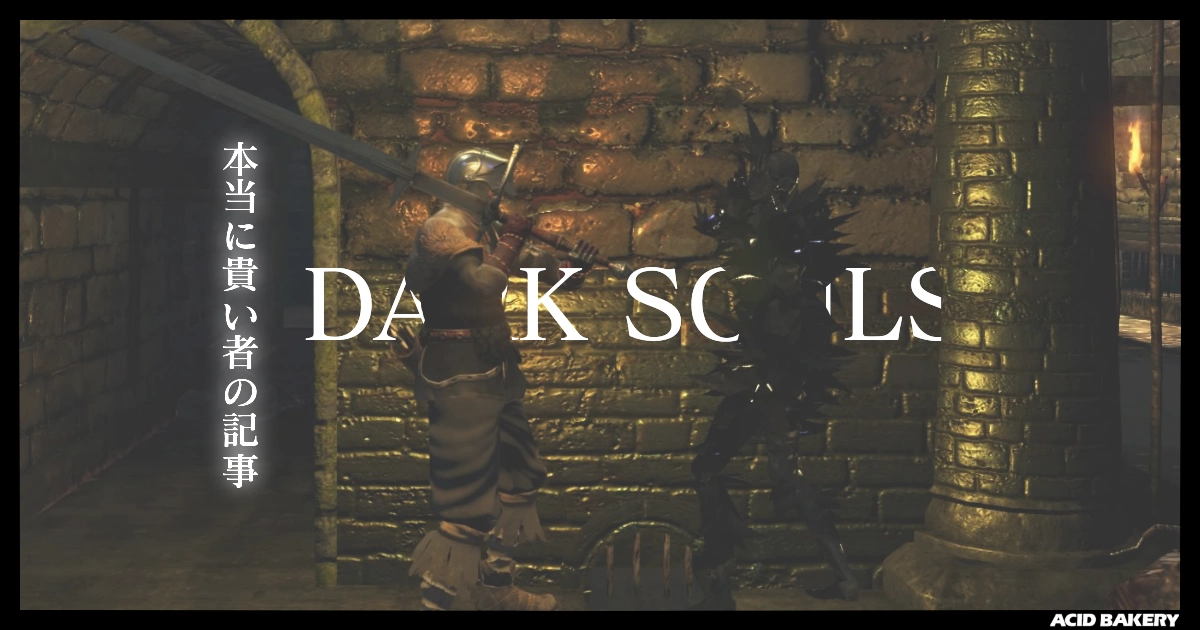火と楔と血の話 06
2020.12.27
前回の続きです。この記事は『デモンズソウル』『ダークソウル』『ブラッドボーン』の世界観には繋がりがあるという仮定に基づいた児戯幻想の類です。必然、該当作品のネタバレを扱いますのでご了承ください。
本来は前回と合わせて 1 つの記事だったもの。なので前回の記事を読んで「ん?」となる部分を埋められたらいいなと願ってやまないのですが、もはや自分でも何を書いているのかよく分からなくなっているので、保証できる限りではないし、どうか助けて欲しい。
というわけで思いつくままつらつら書いていくので、つらつら読んでいってください。いきます。

火の時代の上位者たち

「あれってなんだったの?」のコーナー
そも上位者とは
前回の成果として、上位者を定義することができた気になれました。上位者とは「火をもたらす者」です。以下まとめ。
もうちょいシンプルにまとめるなら、上位者とその赤子の関係は、遡って火防女と篝火の関係を原型とするというのが当サイトの主張です。篝火に人間性(闇)をくべてその火を大きく育てたように、深海の時代においては血の遺志(闇)を赤子へと捧げ大きく育てる形にシフトしたんです。
深海の時代には、人を由来とする「人間性」と、神話の時代より少しずつ深部へと澱んでいった暗いソウルの 2 つしか残っていません。共に闇に属するソウルです。闇は属性こそ炎や雷、魔力(神秘)に変化するものの、本質は闇。しかし「月の力」だけが闇を火のソウルに変えられる、つまりはそれをずっと続けていった先には大きな「火」が熾るかもしれないし、もしくは何か別のおぞましい結末が待っているかもしれませんねという話でした。だから「月」を宿す上位者とは、即ち「火をもたらす者」なのだと。
と、言うのは実はちょっとだけ嘘なのでこれを機に白状します。
ソウルが生命すべての源であるなら 人のみにある人間性とはなんなのか?
人間性 - 『DARK SOULS』
人は人間性のみで生きるにあらず。そして生命の源がソウルであるなら、実はソウル(火)は尽きていないとも言えます。生き物たちの内に、そして人々の中で受け継がれ、「残り火」とも呼べないような微かなそれらは、本当に細々と世界に残存しているのだと思います。何となく話がややこしくなりそうなので言及しなかった(したっけ?)のですが、とにもかくにも、そんな残り滓のようなソウルすらも含めて「赤子(火の炉)」は求めているんでしょう。ソウルとは、掻いて集めて火にくべるもの。全ては火の時代の再現なのです。
失ったもの
「火をもたらす者」。仮にも上位者を定義したのですから、以下のテキストの謎も解けるでしょうか。
全ての上位者は赤子を失い、そして求めている
3 本目のへその緒 - 『Bloodborne』
思いつく限りでは幾つかの解釈が可能です。
だが、実際にそれが何をもたらすものか、皆忘れてしまった
3 本目のへその緒 - 『Bloodborne』
こんな感じ。火を求めるが故に、上位者たちは火をもたらさんとするんです。
自立行動する種付け装置
多くの上位者に見られる特徴として、「軟体」というものがあります。なぜか。媒介者として都合がいいからだと思っています。
- 媒介者
それ自身は病原体ではないが、病原体をある宿主から他の宿主へ運ぶことで感染症を媒介する生物のことである。
Wikipedia より
ありがとう Wikipedia。上位者の先触れで知られる「精霊」が軟体生物として知られているのも同様の理由です。上位者は赤子を求めている。だから自分の血(精)を広くバラまけた方が良いわけです。だから彼女達は随所で精霊をバラまき、そして精霊は自身に宿る上位者の「精」を植え付けて回っているんでしょう。精霊の正体とは、要は「自立行動する種付け装置」なのだと思います。便利な世の中になったなあ。
また何度も言ってる通り、人間性は深みに澱んで実体を得ます。それは大抵「虫」になりますが、だからこそ上位者たちは「軟体」という進化を選んだのかもしれないなと思いました。軟体である理由。それは「虫」を宿しやすく、また感染させやすいからなんです。ちなみにその昔、「精霊」と呼ばれていたのは蟹でした。



火防女の魂と血の穢れ




新旧精霊

かつて人間性は黒い精でしたが、「虫」の形を得た途端、「蟹じゃ効率が悪いな」と進化の途上で判断が下されたのかもしれません。だとすればこうも言えるでしょう。深みのソウル、寄生虫……大元を正せば全て人間性ですが、それがどのような形態を得たかによって、その宿主たる者の性質も左右されるのではないか。ならば上位者の形態から、そこに宿る人間性(深みのソウル)がどのような性質を持っているのか、ある程度推測できるかもしれません。人間性こそが、人の淀みの、まさしく根源でした。
メルゴーの乳母
「あいつらってなんだったの?」編。個別にやっていきましょう。メルゴーの乳母について。彼女(?)に関しては余りに訳が分からないのですが、ちょっと観察すると面白い特徴が散見します。以前書いた記事で「メルゴーの乳母は他の上位者と違って霊的な存在だ」というような事を言いました。叩いた時のエフェクトがカインハーストの「廃城の悪霊」と同じだからというのが根拠です。ここにちょい足しするなら、実はウーラシールの地下に沸く人間性も似たエフェクトを発生させます。





人間性をブッ叩け

ただ先に言っておくとあんま徹底して検証してないので、「このエフェクト他の奴からも出るじゃねーか!」という事態になりかねません。あくまでも参考程度にしてください。しかしこの推測が正しいなら、メルゴーの乳母が「どんなもので構成されているか」、つまり先程も少し触れた、「上位者はそこに宿すものによって形態が左右される」という話題に繋がります。
では続いての注目ポイント。メルゴーの乳母は戦闘中に暗闇の領域を展開し、かつ分裂してきますが、その時に限り腕を伸ばして斬りかかってきます。
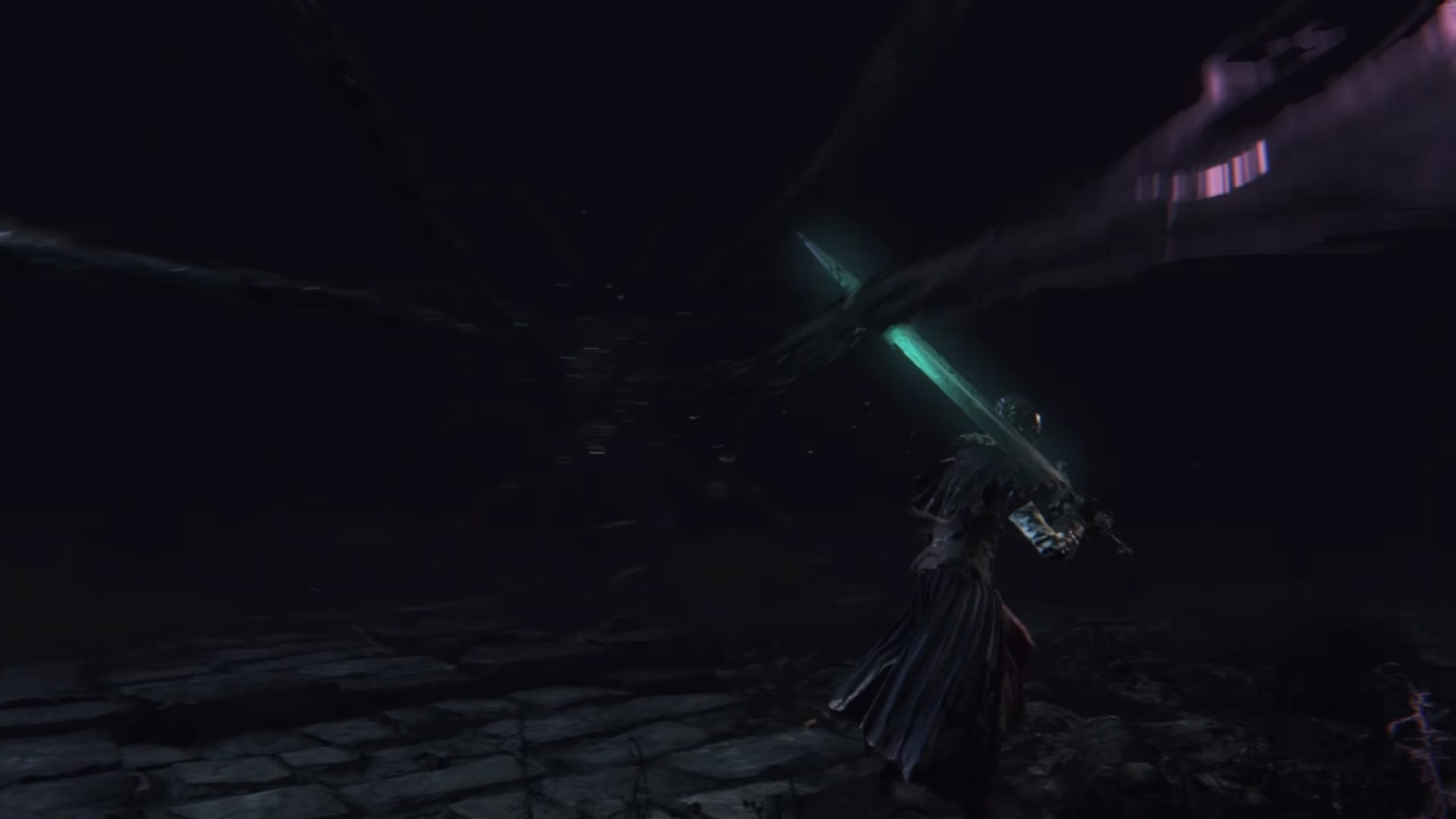
伸びるよ
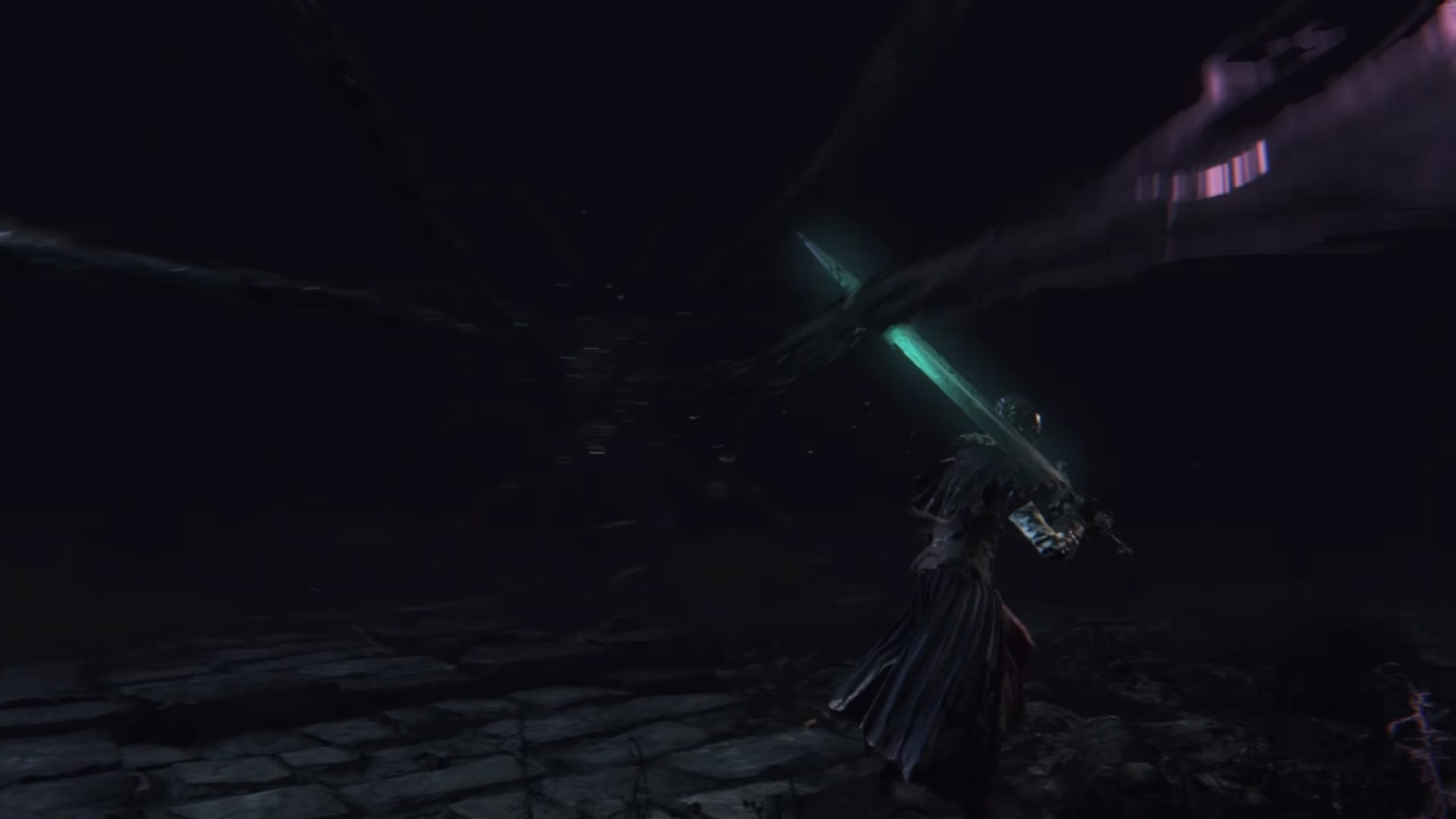
腕が伸びているということは軟体? という話ではなく、どうにも以前からこの光景に既視感があったんです。で、この間わかりました。小ロンドの亡霊です。

すっごく伸びるよ

で、亡霊と言えばこちらにも注目して欲しい。人様から教わったことなんですが、小ロンドの亡霊には女性タイプもいて、彼女たちは赤子を抱いています。そして乳母戦時において彼女もまた内側に赤子を抱いている。



赤子を抱く女性の亡霊

だから単純な話、メルゴーの乳母とは小ロンドの亡霊たちを下敷きにデザインされたキャラクターだったんじゃないか、そしてそれによって彼女という上位者がどういった性質を持つ存在かを示すフレーバーとしていたんじゃないかと思った訳です。
そして小ロンドの亡霊描写が含む示唆はこれだけに留まりません。ご紹介した亡霊女は雷を放ってきますが、何と赤子から放たれているんです。赤子が触媒なのか、母が赤子にとっての触媒なのかは不明ですが、ここまでお読み頂いた皆さまには覚えのある描写であるはず。母と共にあり、雷を呼ぶ赤子。ゴースの遺子です。



カモン・ベイビー・サンダーボルト

小ロンドの亡霊が上位者だったという意味で言ってるわけじゃないです。ただ虫と精霊がそうであるように、赤子と母が一所にあることで特殊な現象を引き起こすという事例は、小ロンドにおいて既に描かれていたという話です。だからメルゴーの乳母もまた同じだったんじゃないでしょうか。彼女は分身といった特殊能力を行使してきますが、そのような能力は本来であれば存在せず、或いは喪失しており、しかし内にメルゴー(赤子)を抱くことで発揮出来ていた、という推測です。とすれば「すべての上位者は赤子を求めている」にも繋がるんじゃないでしょうか。赤子(月)を失った上位者は、他の赤子(月)を抱くことでそれを補完するんです。これを念頭に置いておくと他の要素も繋がるので、うっすらと覚えておいてください。
悪夢について
まだあります。メルゴーの乳母に纏わる一連の描写は「悪夢」というものへの示唆も含みます。これは過去記事でも書きましたが、人間性は深い場所へと澱みます。つまり世界の奥底にはそれが溜まっていて、そこは純然たる澱み(深みのソウル)によって構成された領域となっているんじゃないかと。要は地下遺跡とはその領域、言ってしまえば「深み」へと物理的にアクセスする為の試みであり、聖杯ダンジョンにおいて悪夢にしか登場しない怪異が散見したのは古き人々の試みが的を射ていた証だったと述べてきました。そして亡霊という存在を起点に、悪夢という世界の描写が小ロンド遺跡に似せられていると仮定します。そしてそれはなぜかと考えてみます。
悪夢とは深淵である。人間性、或いは闇が澱むことで構築された暗い世界を、古い時代の人や神は「深淵」と称し、後の時代においては「悪夢」と称されたんです。亡霊と乳母の対比が顕著であるように、深淵と悪夢それぞれに類似する現象を配置したのは、とどのつまり二つの領域が同じ、或いは密接に関わることを示唆する為でした。
「羽」が示すもの
話題を戻しますが、「軟体であること」は手段の一つでした。或いはそこに宿る寄生虫も、深みのソウルがとる形態の一つに過ぎません。そして恐らくメルゴーの乳母とは、そこに当てはまらない事例ではないかという話がここまでの内容です。彼女(?)は、純粋に深みのソウルだけで構成された上位者であり、それは亡霊、ないし闇霊と言って良い存在なのだろうと。
気になるのは、彼女のみが撃破の際に、他の怪異のように血ではなく羽を散らせる点です。これどういうことでしょうか。わかんないですよね。

極上の羽毛です。

乳母が亡霊に似て、深淵と悪夢を結ぶ重要なピースとしてデザインされたと推測できても、「乳母自身は何者なのか」に関しては全然理解が及びません。ノーヒントと言っていい。まあ、分からないはずのものを分からないままにしておくのも一つの楽しみではあると思います。しかしながら考察サイトの端くれであるなら、ちょっとだけ頑張ってみるのも一興でしょう。
というわけで、「羽」。心当たりがあるわけですよ。これ。



掃除しろ。

左がゲルトルードの鳥かごで、右が双王子とのバトルエリアです。双王子はともかく、ゲルトルードに関して言えば、この羽は「天使」との関連性が疑えます。



天使の羽

天使自身は羽毛を持たないようにも見えますが、彼らの周囲には僅かに光輝く羽が散っていることがお分かりでしょうか。ここが地味にポイントだと思っていて、この光の羽のエフェクトは、ゲルトルードの奇跡である「天使の光柱」に見られる他、ロスリック王子の魔法からも似たものが確認できます。これが降り積もったものが双王子エリアの光景、その正体なんでしょう。

光の羽?

「天使の娘」ゲルトルードと天使たちに共通項が存在するのは頷けます。しかし、ではロスリック王子は? 彼もまた天使を信奉していたのか、というとちょっと違うと思っていて、たぶん「天使」を起点にしてしまうから話がややこしくなる。つまり天使・ゲルトルード・ロスリック王子の三者には共通した因子があり、それが「羽」として顕れたと考える方が個人的にはしっくりきます。要はその「因子」さえ持っていれば羽は散るんじゃないかなと思うんです。「羽」とはただの副産物という解釈ですね。ではその因子とは何か。

巡礼者進化表

前回の記事からの流用ですが、闇の苗床として変態する巡礼者は、ある一点の因子の有無によって行末が分かれるのだと申し上げました。「月の力」です。月の力を宿した巡礼者だけが蛹となり、空に天使を幻視する。だからシンプルな仮説として、ロスリック兄妹と天使に共通する因子とは「月の力」であり、「羽」はその顕れだったのではないでしょうか。
例えゴールが同じでも
ロスリック王子とゲルトルードに宿った月の力はどこからきたのか。これは血の営みに秘密があると思っています。
白竜シースの名で伝わる伝説のドラゴンウェポン
妖王オスロエスは妄執の先に月光を追い だが、それに見えることすらできなかった
月光の大剣 - 『DARK SOULS 3』
妖王オスロエスは大書庫の異端、つまり白竜シースの一端と繋がりはしたものの、彼自身が月光に見えることは無かったそうです。しかし彼のソウルからは月光の大剣が練成できる。矛盾でしょうか。いえ、それは彼の中に月光が宿っていた確かな証であり、ですが彼自身は最後までそれを自覚することは無かったんでしょう。「啓蒙」です。
内なるものを自覚せず、失ってそれに気付く
滑稽だが、それは啓蒙の本質でもある
自らの血を舐め、その甘さに驚くように
脳液 - 『Bloodborne』
妖王自身は「内なるもの」を自覚できず、しかしそのソウルは月光を帯びていました。そしてソウルとは血に宿ります。ならば月の力もまた受け継がれるのでしょう。故に妖王の血を継いだゲルトルードは、その血から啓蒙を得、やがてその啓蒙(物語)には「天使」という名前が与えられました。
「天使の娘」ゲルトルードの奇跡
王妃の聖女であったゲルトルードは 彼女のいう天使に見え、その物語を知ったという
彼女は光と声を失い、だが物語を記し続けた
常人には理解できぬ、破綻した書付の由が ロスリック天使信仰の源流となったのだ
天使の光柱 - 『DARK SOULS 3』
幾度かの繰り返しになりますが、なぜ娘であるゲルトルードに顕れた月の力が、親であるオスロエスの元にはもたらされなかったのか。妖王が女性ではないからです。月の力とは女性の力ですから。……としてしまうと、ロスリック王子に月の力が宿ったことに疑問が生じますが、これも結構な重要ポイントです。この後で触れていきますが、取りあえず今は「羽」がある種の月の顕れであるという仮説のみ受け取ってください。
そして月の力とは、上位者の力であるとも言えます。だからメルゴーの乳母が「羽(月)」を持つことにも繋がってくると思うのですが、そうした上で、「羽を持つ上位者」と「羽を持たない上位者」の間には如何なる差異が存在するのだろうか、というのが本項で語りたい部分でした。ここを明らかにすれば、謎の多いメルゴーの乳母について少しは解析が進むかなと思った次第です。ということで、また性懲りもなく作図したのでご覧ください。

これが深海の時代だ!

ごちゃごちゃしてますが、肝心なのは一つだけです。これは前述していることですが、大地の深層に澱む闇と、宇宙の深淵は、たぶん同じところに繋がっています。物理的にそこを目指して地下遺跡を作り上げたトゥメルと、宇宙へと交信を試みた聖歌隊は、結局は同じ「深海」を目指していたわけです。しかしたとえゴールが同じだろうと、行く道が違えば必要な手段も違うはず。地を行くものに翼は必要ないんです。
何が言いたいか。要は「深み」を地下や海へ求めたものたちには「軟体」が、そして天空(宇宙)へと求めたものたちには「翼」が与えられるのではないかという仮説です。

正反対の道を行き、それでも同じ場所へ辿り着いた人たち

もっと言い切ってしまうなら、血に頼った進化を遂げた者は軟体に至る傾向にあるのかなと推測します。血を原因とするが故にその進化はとても生物的で、だからそこに当てはまらない進化に成功したものは、天を行く翼を獲得し、そしてその肉体はソウルのみで構成されるんじゃないかと。上位者に至る経路が「天」か「地(海)」かで分かれた結果、その性質が「鳥類」「軟体」に大別されるというのは、なかなかシンプルで分かりやすい類別なんじゃないでしょうか。ウィレーム先生は血を忌避していましたが、翼を獲得する進化であれば納得してくれたのかもしれません。結局は同じ場所かもしれないんですけどね。
血ではなく、天を行く道もあるんです。恐らくメルゴーの乳母とは血に依らぬ進化を遂げた一人なのかなと推測します。そして同じように「羽」を顕現させた天使たちは、人が持つ多用な進化の可能性、中でも天への祈りを以て新たな領域へと飛び立つ者たちを示す、ある種の先触れだった、というのはどうでしょう。天使という存在は、その進化は、やがてメルゴーを始めとした「翼を持つ(肉体を持たない)上位者」に繋がるのではないかというお話でした。
そうそう、余談ですが漁村の入口で和やかに迎え入れてくれる村人さんは気になることを言っていました。
「…さあ、呪詛を。すべての血の無きものたちよ。すべての血の無きものたちよ。我らに耳をすましたまえ…」
漁村民 - 『Bloodborne』
血の無きもの。それはメルゴーの乳母のように肉体を持たぬ怪異全てへの呼び掛けなのでしょうか。謎は尽きません。
アメンドーズ (1)
ついでにこいつにも軽く触れておきます。結論を先にいうと「やっぱりよくわかんない」んですが、それでもソウルシリーズの要素を代入すると、多少の解像度向上は見込めます。じゃあやってみましょう。
まずこれまでの仮説として、ざっくりとどういう存在かを述べるなら「赤子のなりそこない」だと解釈しています。上位者であることは確かなようですが(トロフィー参照)、パッチ・ザ・スパイダー曰く「あれは憐れな落とし子」らしいので、上位者であっても、別段もてはやされるような階層にはいないことが伺えます。ではなぜそんなものが生まれてきてしまったかと言えば、二つの可能性を考えていました。
1. についてですが、要は「赤子は一度生を受け、命を奪われることで『個性』を獲得する」という発想です。死はソウルの一側面。生を失うということは、死という力を得ることでもあります。劇中でアリアンナや偽ヨセフカを赤子ごと殺傷しましたが、むしろあれがきっかけとなって新たな「月の魔物」が生まれるのではないかという仮説ですね。皮肉も効いていて、今後のシリーズ展開にも繋げられそうで気に入っている仮説なんですが、正直今となっては次にご紹介する仮説の方が可能性としては高いと思っています。
2. の「畑が悪かったから」というのは、シンプルに母親が出来損ないだったからという発想です。酷い物言いですがお許しください。赤子の上位者が生まれてくる条件は幾つかあるようですが、肝心要は「母体」の出来です。火防女、或いはそこに類する素質を持つもの、先の時代においては「Fair Maiden」と呼ばれる特別な女性を介してのみ特別な赤子は生まれてきます。一方で医療教会は「血の聖女」とされる、特殊な調整を加えた女性を保有していました。
教会の尼僧たちは、優れた血を宿すべく選ばれ 調整された「血の聖女」である
アデーラの血 - 『Bloodborne』
月の魔物が「Fair Maiden」を介して生まれてくるなら、アメンドーズとはこの「血の聖女」を介して生まれてくるのかもしれません。それはそれで人が間接的に上位者の生誕に関与していることになるので偉業と言っていいのでしょうが、恐らく、少なくとも上位者の視点においては「これじゃない」んだと思います。だから生まれてきてしまった者たちは「憐れな落とし子」なんでしょう。
メンシス学派の「メンシス」とは「月」を意味するようですが、月が赤子を指すなら、彼らが根城としていた隠し街ヤハグルに大量のアメンドーズが蠢いていたあたり、あれらはメンシス学派が試みたハチャメチャな人体実験の賜物なのかもしれません。そういえば聖女アデーラがあの街に囚われていましたが、あれはそういう目的の為だったのでしょうか。助けられて良かったですね。
そしてそれを踏まえると「血の聖女」アデーラによる娼婦アリアンナの殺害イベントが一層深みを増します。いわゆる「まがいもの」が「本物」を害した訳です。きっと赤子を望むオドンに取っても理外の一幕だったと思います。ある意味で、人の情念が上位者の思惑を超えた瞬間だったのかもしれません。
アメンドーズ (2)
さてそんなアメンドーズ。実はソウルシリーズが有する、ある「伝統」を受け継ぐキャラクターでもあります。「腕」です。





「掴み」は OK

何度も言ってしまいますが、人間性とは人の本質であり、人の本質とは「欲」。そしてそれが強く反映されたものがこれらの「腕」です。それを象徴するキーアイテムの一つがダークハンドですね。人間性の権化である深淵の主マヌス、不死を糧に変容した呪腹の大樹、そして人の澱み(人間性)が人を介して形を成したアメンドーズらが、共通して大きな「腕」を持つのは当然と言えば当然でしょうか。
そしてこの場合、「掴んだ対象を時空を超えて移動させる」という意味で、アメンドーズの特性はマヌスのそれに近い。そしてこの特性は闇に属するものたちが当然のように持つ能力でもあります。『DARK SOULS 3』でボルドや踊り子が暗闇の中から出現したように、また吹き溜まりでは湿り人たちが地面から、ハーラルドの戦士たちが濁った水たまりの中から出現していたはずです。『DARK SOULS 2』においては聖壁の都サルヴァのボス「穢れのエレナ」などが顕著でした。彼女自身がワープするどころか、ヴェルスタッドらを召喚していたことが強く印象に残っている方も多いと思います。
全ての闇は繋がっているんです。全ての海が繋がっているように、闇を通じて、地下深層と宇宙、そして悪夢もまた繋がっている。「悪夢とは深淵」である。
アメンドーズが行う時空間転移とは、そうした闇が持つ特性を利用した能力でした。
アメンドーズ (3)
アメンドーズが持つもう一つの特性。それは「啓蒙の付与」です。アメンドーズの腕に掴まれた際に啓蒙を得ることができます。これはつまるところ上位者による「啓蒙活動」なのでしょうか。そも啓蒙とは「苗床としての素質」に関わるものだという説明をしてきたと思いますが、正直ここではあまり重要ではなく、アメンドーズの「啓蒙をする」という在り方に対し、過去作に重なる描写があるんじゃないかなと考えました。
カリムでは、聖女は物語の語り部である。
分厚い聖書を何冊もよく覚え、よい声で語る。
そのように、彼女たちは名高い。
聖女の指輪 - 『DARK SOULS 3』
アメンドーズとは啓蒙(物語)の語り部だったのではないか。何を目的としたものだったのかは分かりません。無知な人々の蒙を啓き、人類を幼年期から脱却させる導き手とも解釈できますが、或いはカリムのイリーナが火防女になりそこない、しかし奇跡を啓蒙することで終には至ったように、アメンドーズもまた同じなのかもしれません。火防女としての素質を持たぬ者しか赤子を抱けないなら、アメンドーズもまた上位者であるが故に赤子を求め、故に火防女たらんとした聖女の在り方をなぞっているんじゃないでしょうか。「憐れな落とし子」から脱却し、赤子(火)を抱くために。
血の聖女を介して存在する、憐れな落とし子アメンドーズ。異形たる聖女(語り部)、だったのでしょうか。
不揃いの向日葵
この章の締めとして触れておきたいことが次の光景です。

星輪樹の庭

これは「星輪樹」という植物らしいのですが、見た印象としてはひまわりに近い。ひまわりの有名な性質に「向日性」があり、要は太陽の光を追いかけて向きを変えるというもの。厳密にいえば若いひまわりのみの性質で、成熟すると向きは東に(ほぼ)固定されるようなのですが、そうして太陽を追いかける理由にしても、陽の光を受けやすいようにという自然の創意であるようです。
それを踏まえてこの一見成熟しきっているような星輪樹が、その方向をてんでバラバラにして咲いている理由を考えると、世界に太陽が存在しないからなんじゃないかと思うんです。太陽というのは単に星という意味に留まらず、かつてグウィンが「火」より見出した、王のソウルを指します。とっくの昔に火は陰り、今や太陽のソウルは存在しない。故に向日性の植物は不揃いに狂い咲いているのかなと、そんな余談でした。
灰と火の上位者たち
ここからがメインパート。
はじまりの白竜(1)
下準備は終わりと言っておいてなんですが、「月」に関しておさらいをしておきましょう。
月光は「信仰から魔力を生む力」です。「暗月の光の剣」などの性質からそう解釈します。しかし非常に厄介なことに、それが「理力から生まれた魔力」なのか「信仰から生まれた魔力」なのか、プレイヤー視点からは区別がつかないようになっています。前回も言いましたが、属性とは表層の性質であり、ソウルとしての本質が火であろうと闇であろうと、魔力属性である以上、一見して効果上の区別は存在しません。ですが、だからこそ面白い記述がこちら。
法王サリヴァーンの持つ左手の剣
月の裁きを称する儀式の剣であるが その魔力は、月よりもむしろ魔術に近い
暗い月よりも、なお暗い青色は 魔術師サリヴァーンの本質であったろう
裁きの大剣 - 『DARK SOULS 3』
『その魔力は、月よりもむしろ魔術に近い』そうです。あまつさえサリヴァーンは法王という身分でありながら、何と主神をエルドリッチへの供物としました。こう考えます。奴に信仰心など欠片も無かった。だからド聖職者であるはずの「法王」サリヴァーンが裁きの名のもとに振るう大剣には、信仰補正どころか要求値すら存在しません。「月の裁き」と称するそれは嘘っぱちも良いところで、青い輝きは、徹頭徹尾、「魔術師」サリヴァーンの理力の産物なんです。大剣のテキストはそういう意味で読むと味わい深い。法王の名の下、彼は「月に代わっておしおき」していたんです。
そして殊更興味深いのが、思いっきり「月」の名を冠したお馴染み「月光の大剣」です。こいつにも信仰補正は乗らず、また要求もされません。月の名を持つ癖に、まさか月と関りを持たないとでもいうのでしょうか。或いは月が信仰を魔力に云々というのは唯の勘違いなのでしょうか。しかしながら「似ている」というのは、そこにある差異を浮き彫りにする為の描写だと捉えてみます。だから「裁きの大剣」と「月光の大剣」の性質が酷似し、その上で前者のテキストに「月よりも魔術に近い」とわざわざ記述されているのは、一見して同じであっても、そこには決定的な差異が存在することの強調なんじゃないかと思うんですね。
なので「月光の大剣」の特性を単純に解釈するなら、あれは確かに月の力を発祥とする魔力の結晶ですが、一度顕現してしまった「魔力」は既に祈りや奇跡の範疇には収まらず、あくまでも魔術や理力によって運用されるのだと、そう捉えています。
となると一つの想像が膨らむこと止む無しです。
歴史上、聖職者と魔術師はしばし対立した
だから質実な聖職者たちには 魔術に対する手段が必要だったのだ
魔力防護 - 『DARK SOULS』
聖職者と魔術師は対立し、そして奇跡と魔術もまた相反する業だと、少なくとも人々は考えてきたようです。しかし本当にそうでしょうか。そもそも魔術とは誰がもたらしたものだったか。
魔術の租たるシースの魔力の結晶であり その力は月光の波として開放される
月光の大剣 - 『DARK SOULS』
魔術とは白竜シースが編み出した業でした。ですがよくよく考えてみると、シースの魔力、その結晶に「月」の名が与えられるのはどういった理由からなのか。もしかすると魔術とはシースが月の力と祈りによって編み出した業だったんじゃないでしょうか。魔術と奇跡。起源を遡れば、そこに明確な違いなど存在しなかったのかもしれません。であるなら、きっとそれを知らず互いを忌み嫌う魔術師と聖職者たちの何と滑稽なことでしょう。……どこかで聞いた話ですね。つまるところ、このオチ自体が一種のセルフ・パロディだったんじゃないかというお話でした。あ、リメイク版発売おめでとうございます。
さあ楽しくなってきました。月の力の白竜シースとは、果たして、真に何者だったのか。
はじまりの白竜(2)
こんな記事を書きました。
古竜について、その正体へ迫ろうとしたものなんですが、古竜や灰の時代のことを語る上で欠かせないと考える小道具、或いは広げなければならない風呂敷がありまして、それが「世界絵画説」です。似たようなことは誰かが考えていると思うので、あまり「自説」みたいな扱いはしたくないのですが、要するにソウルシリーズの世界そのものが一枚の絵画の中の出来事だったという仮説です。
いま読み返すと、長い長いと呻いていた『火継ぎの傍ら、世界を描く』なんて全然長くないですね。よくないインフレだ。
ともかく「世界は一枚の画」でした。アリアンデル絵画世界で絵描きのお嬢様が求めた「暗い魂(ダークソウル)」、それを顔料に描かれた画には、不死の英雄にちなんで「灰」の名が与えられます。これが世界の起源、「灰の時代」の由来であり、『DARK SOULS』とは英雄の働きと、暗い魂の宿った「血」から「生まれた」というお話。
血はすべてを溶かし、すべてそこから生まれる
儀式の血 - 『Bloodborne』
それを踏まえまして、「恐竜は鳥類の祖先である」なんて言説をここで取り上げます。これがソウルシリーズ史のベースになっていると仮定するなら、古竜たちもまた代を重ねて鳥へと進化していったのかなと思う訳です。無名の王がライドオンする「嵐の竜」は、進化の途上に位置するが故に、あのような鳥と竜のハイブリッド的外形なんじゃないかと。

無名さんちの鳥ドラゴン

で、あれば、「逆」もあり得るんじゃないかと思うんです。
「世界絵画説」の便利なところは、疑似的なタイムスリップを実現できる点です。火の時代にあった忌み人たちが、絵画を通って世界の始まりへと遡ることが可能になります。だとすれば後は単純な連想ゲームじゃないでしょうか。時代の流れと共に竜が鳥に成るなら、時代の逆行が鳥を竜に至らしめるとは考えられないでしょうか。
お嬢様はその画が、「誰かの居場所になる」ことを望んでいました。ならば何も存在しない灰の世界に、それでも在った古竜たちとは、この差異無き世界を居場所と求めた忌み人の成れの果てだったのではないか。絵画を介した時代の逆行は、鳥を竜へと変えたのです。

世界絵画説に基づく古竜の起源についての一考

画像は種族としての進化チャートを示しており、嵐の竜がそのまま祭祀場のカラスになったとかそういう意味ではありませんよ、一応。
アリアンデルの篝火「絵画の底」は、マクダネルが歓喜した「世界の底」になぞらえたものだと考えます。それは絵画それ自体がある種の「深み」であることを示します。だからこそ絵画に居場所を求めた人々は、「深み」の作用によって人間性の変化が促され、結果、器である肉体が鴉や木に変態するんです。では、絵画(深み)の中で更にもう一度絵画を潜ったら? その思考実験の答えこそが、灰の時代の古竜たちでした。絵画を二枚潜ること。これが、人が古竜に至る真の道なんです。
では白竜シースは? こんな記事を書きました。
古竜についての考察を踏まえ、では白竜とは何だったのかを書いたものです。要点を纏めます。まず確認事項として、「月」とは女性のみが持つ力であろうということ。従ってシースとは女性であり、そして元は聖女だったのではないかという連想が成り立ちます。そして重要なもう一点。
白竜シースに仕える魔術師たち、伝道者の兜
縦二列に並んだ六つの目は シースの見えないそれを代替するためである
伝道者の六目兜 - 『DARK SOULS』
なぜシースに盲目という設定が与えられていたのか。そして『DARK SOULS 3』において、なぜ総ての火防女が盲目であるという設定を再確認させたのか。白竜シースが火防女だからではないかと。
灰の時代に至った忌み人たち。そこに紛れた、たった一人の火防女。この差異こそが、差異無きはずの灰の時代において、ただ一体のウロコ無き竜を生み出してしまった。それが「白竜白書」の結論でした。しかし一つだけ答えを出していない疑問があります。一体だけ他と違う理由は分かった。では、「なぜ」そのような姿に変わったのか。
はじまりの白竜(3)
深海の時代。火を失った世界における火防女の役割とは何か。それは、或いは古い時代から続く残り火を守ることなのかもしれませんが、一方で人間性の揺り籠と呼ばれたその素質故に、上位者の血を介して人の澱みにさえ順応し、彼女たちはそれを赤子として育みます。そして赤子の母は、苗床としてより相応しい形に変態する。それは大抵、巨大な軟体生物の形を取るようです。
火の無き時代において火防女が示す末路が上位者への進化であるなら、同じく火の存在しない灰の時代においてはどうなのか。同じことが起こるのではないでしょうか。
絵画を二度潜った先、人は竜に成りました。では、火防女は? 火の無き灰の時代、たった一人の火防女は、ウロコを持たぬ軟体に成ったのだと思います。それが火の無き世界の火防女の末路であり、そして白竜の出現は、熾った火を失った後に世界が辿る顛末、その先触れだったのです。
灰の時代の古竜たち。その内、たった一体紛れたそれを、神代の者たちは「ウロコのない竜」と呼びました。しかし彼女は、もっと異質な、竜ですらない別の何かだったのかもしれません。
白竜シース、最初の上位者でした。

上位者シース

上位者シースの話をしよう(1)
白竜シースとは灰の時代の火防女であり、最初の上位者でした。確証も無いのにそんなことを言い切ってしまって大丈夫なんでしょうか? 大丈夫大丈夫、責任はフロムが取る。そんなわけで白竜シースは上位者である、という仮定のもと、そのつもりになって物語を見つめ直してみましょう。結構面白いことが色々と分かってきます。
まず手頃な場所から手をつけますが、皆さんは漁村の上位者ゴースの名の由来についてどうお考えでしょうか。「KOS」或いは「KOSM」と綴られるその名は、たぶん「KOSMOS(宇宙)」が語源なのかなと思っています。母なるゴースは、母なる宇宙をもじり名づけられ、そしてそれは宇宙と深海の繋がりの示唆なのではないかと。しかしここに一つ付け加えるなら、至極シンプルに「ゴース」とは「シース」に寄せた名だったら嬉しいなーと、思っているんですが、まあ偶然でしょうかね。そしてこの二体。見方によっては、共に「純白の軟体生物」でした。



シース / ゴース

ではこの二体を似せたのだと仮定して、それはなぜか。意図を勘繰るなら、「灰」と「深海」という差異こそあれど、「火の無き時代」という環境に在る特別な女性はそれぞれが似た進化を遂げることになるのだと、その示唆の為なんじゃないかと思っています。
そんな訳で、こういった思索は、これまで構築してきた『Bloodborne』における謎を読み解く為の仮説・推論を、そのまま『DARK SOULS』に適用し、その謎を読み解いていく、それはそれは楽しい遊びが可能になることを意味します。宮崎社長曰く『Bloodborne』の設定は大分前から温めていたものらしいですが、それはどこまでを含むのでしょうか。全ては『DARK SOULS』から、或いはそれ以前からの伏せカードだったのか、もしくは『Bloodbonre』の為に過去作を寄せたのか……まあ、考えても詮無きことは放っておいて、話を先に進めましょう。
上位者シースの話をしよう(2)
一つ連想しておきたい事柄があります。「Fair Maiden」、中でも色濃い素質を持つ「娘」が上位者へと進化する切欠の一つに「赤子」が存在しました。一部の上位者などはこれを獲得できなかったが故に、進化を遂げながらも「見捨てられた」のではないかとも述べてきましたが、果たしてシースはどうでしょうか。では、踏まえ、以下の画像をご覧ください。

『Dark Souls Design Works』より

どうでしょう、どう見えるでしょうか。「シース妊娠説」は時たま目にしていましたが、ここまでの仮説と組み合わせてみると結構ワクワクしませんか。
もっともこの発光源を「シースの赤子」と解釈してしまうと新たな疑問が生まれるのですがそれは後述するとして、確かなことは、シースを語る上で「月光」という概念が欠かせないということ。そして月光とは、上位者の力でした。
篝火が持つ「闇を火(ソウル)に変換する力」は、篝火の化身たる火防女の力とも言え、それは彼女たちが持つと思われる「月の力」に由来するのではないか。当サイトではそんな仮説を立てました。そして後世、「火防女」と彼女たちが持つ「月の力」が、深みの影響により「母」と「赤子」に置き換わるなら、即ち上位者とその赤子は元々一つの存在だったと言えます。ただ形と在り方を変え、分かたれただけ。だから上位者は自身の半身たる赤子(月)を求めるのでしょうか。
特別な女性と赤子。それらは精霊と寄生虫のように、一所にあることで絶大な神秘を生みだします。だからメルゴーの乳母は赤子を抱くことで力を得、母体を傍らに置いた遺子は太陽色の雷光を呼び、女王ヤーナムは上位者でこそないものの、我が子の鳴き声と共に狩人を拘束しました。では白竜には如何なる神秘が宿ったのか。
悪夢の上位者とは、いわば感応する精神であり 故に呼ぶ者の声に応えることも多い
カレル「月」 - 『Bloodborne』
月とは「信仰から魔力(ソウル)を生み出す力」でした。そして形を得ようとも月はその性質を残し、故に呼ぶ者の声を糧に魔力を生み出します。以て「魔物」、或いは「赤子」と呼ばれる上位者を内に抱いたものは、かくして神に近しい力と形を得る訳です。全て理屈は一貫していて、灰の時代であっても同じこと。内に宿した「月」より引き出した魔力を基に、最初の上位者は、大いなる業を組み上げました。これが「魔術」です。
魔力、魔物、魔術。その始まりには「月」があったのでした。
上位者シースの話をしよう(3)
どんどんいきましょう。今のところ上位者は二種に大別でき、「軟体」と「霊体(鳥)」が存在するのではないかと前述しました。特に身に宿す「深みのソウル」が虫の形を取った場合、その宿主は虫の苗床に相応しい「軟体」に進化するのではないか、なんてことも言いました。ゴースの寄生虫とは、彼女の中で育まれた、彼女だけの「実体ある深みのソウル」だったのだろうと。つまりある意味で、上位者と寄生生物とは切って切り離せぬ間柄であるということです。それは母(宿主)と赤子(寄生生物)の関係に似ます。赤子とは母から養分を吸い上げて育つ寄生虫のようなものである……そんな解釈をプレイヤーにさせるゲーム会社があるらしいですよ!
思い出して欲しいのが、『DARK SOULS 2』に登場する「公のフレイディア」なる大ボスです。以前書きましたが、「鉄の古王」「忘れられた罪人」「腐れ」「公のフレイディア」とは、それぞれが『DARK SOULS 1』における王たちの成れの果てでした。というより、その偉大なソウル故、滅するに滅しきれず後世へと影響を及ぼし続ける、言わば「絞りカス」と言うべきでしょうか。詳しくは過去記事をお読みいただくとして、中でもフレイディアは特異な描かれ方をしていました。他のボスが撃破と共に「GREAT SOUL EMBRACED」と表示されるのに対し、フレイディアのみそれが無く、しかし直後現れる「赤い何か」に触れることでようやくその表記が現れます。要は偉大なるソウルを宿す者の正体は巨大蜘蛛フレイディアではなく、フレイディアを宿主とした「這う蟲」の方だったわけです。つまりはこの今や矮小な蟲こそ、かつて白竜として名を馳せたシースの成れの果て、絞りカスだったのでした。
さて、聖剣の狩人ルドウイークには、彼を導く光の糸、小人が宿っていたといいます。これも過去に書いてますがその光の糸とはルドウイークに宿った「ゴースの寄生虫」、ないし彼女の血だったのではないかと思っています。虫はソウルの具現。ならばそれが「ゴースの(血の)遺志」として彼を導いたのなら、言い換えれば一匹の虫に至るまで、そこには上位者の遺志(ソウル)が宿る理屈になります。
「這う蟲」とはシースの末路でした。そして上位者の寄生虫が宿主の遺志を秘めるなら、フレイディアに憑いた「這う蟲」とは「シースの寄生虫(遺志)」と言い換えられるのかもしれません。かつての竜が蟲に堕ちて尚死なず、変わらぬ妄執を追い続けるという一遍の寓話。しかしその裏に隠されたものは、上位者と寄生虫の関係を示す、遠大な前振りだったんじゃないでしょうか。
余談ですが今振り返ってみると、この辺の「撃破したボスそのものではなく、取り憑いていた『核』に触れることでイベントが終わる」という意味で、フレイディアと遺子戦の演出は共通しています。そして双方「虫(蟲)」が関わると。ただの偶然か、いつものセルフ・オマージュなのか、或いはそれらを隠れ蓑にした伏線だったのでしょうか。
上位者シースの話をしよう(4)
シースが元々火防女であったなら、実のところ人間であった頃の彼女はシリーズ中で登場していたのではないか、などと「白竜白書」の中で考えてみました。幾人か候補を挙げたのですが、個人的な「推し」が彼女です。

結晶の娘、クリエムヒルト

根拠もつらつら並べました。彼女は本編で(たぶん)倒したのですが、実はこっそり生き延びて絵画を潜ったのかもしれません。で、三度目の白状になりますが、嘘は吐いていないものの、そこでは割愛した理由があるのでご紹介します。
クリエムヒルトには「結晶の娘」という二つ名のようなものがありました。これが何を意味するのかは当然の如く明かされていませんが、推測だけなら一つ浮かびます。「結晶の娘」とは、後の「美しい娘(Fair Mainden)」に属する存在ではないか。つまり上位者を生み、そして自身も上位者へ進化する素質を秘めた女性です。それを示唆する為に与えられた号が「娘」なんじゃないかと。
しかし考えれば考えるほどに不思議な話です。「白竜白書」でも言いましたが、クリエムヒルトの結晶の魔術は古老より受け継いだものらしく、しかしその源流には白竜シースがいる。クリエムヒルトとしての学びが、後にシースとして拓いた魔術の土台となり、そしてそれが遥かな未来、「灰」の絵画を潜り、過去の自分へ明け渡される。何とも奇妙な円環です。全て想像の話ですが、正しいとすればまさしく、彼女は「結晶(シース)」が生んだ娘であり、そしてやがては「結晶(シース)」に至る「娘」だったのでした。
変態を分けるもの
ちょっと横道に逸れます。
同じことばっかり言ってますがこの場を借りて白状します。こんな記事を書きました。
冷たい谷のイルシールに蔓延るという「月の虫」とは、繁殖した「這う蟲」、つまりはシースの末路だったんじゃないかという内容の記事です。嘘をついたつもりも無いんですが、実のところ半分くらいは本気じゃないです。
というのも想像するに、月の虫というのはサリヴァーンが故郷から連れてきた、絵画産の「おぞみ」なんじゃないかと思ってます。
イルシールの奴隷たちが作る秘薬。
冷たい谷には、月の虫が蔓延っている。
青虫の丸薬 - 『DARK SOULS 3』
蟲の群れを召喚し、敵を蝕む
深みに潜む蟲たちは、小さな顎に牙を持ち 瞬く間に皮膚を裂き、肉に潜り込む
蝕み - 『DARK SOULS 3』
若き魔術師サリヴァーンが 絵画を去る前に残した魔術のひとつ
極低温の霧を発生させる
瞬間凍結 - 『DARK SOULS 3』
『3』で導入された凍傷とは、この月の虫による「蝕み(虫食み)」であり、故に「FROST BITE(噛む)」とはダブルミーニングになっているというお話をしました。で、月と言えばシースだから、這う虫となったシースはその後月の虫として……というような流れだったはずですが、「瞬間凍結」のテキストを読むに、実のところ月の虫はサリヴァーンが外界に持ち込んだもの、「絵画という深みからの召喚物」なんじゃないかと思い直したんです。
なぜなら「虫」とは人間性が深みを寝床として生(実体)を得たもの。そして絵画世界が一つの深みであるなら、絵画世界を苗床として育った「人の澱み」こそが月の虫の正体なんじゃないかと、本音を言うとこっちの仮説を推してます。まあ色々言っておけば後で繋がってくる事もあると思うので「月の虫 = シース説」は完全に棄却せず、隅っこのほうに寝かせておいてやってください。
さて、では月の虫が絵画世界産の「おぞみ」「蝕み」であるとした上で、ちょっと聞いて頂きたい話があります。
血の発見は、彼らに進化の夢をもたらした
病的な、あるいは倒錯を伴う変態は、その初歩として知られる
右回りの変態 / 左回りの変態 - 『Bloodborne』
この「左右」のカレルはそれぞれ禁域の森に落ちているのですが、特に後者は星界からの使者がいる辺りに配置されています。配置の仕方から見るに、これは血による進化が上位者寄り(左回り)か、そうでないか(右回り)を示しているんじゃないか、というのは過去記事でたぶん言ってるわけですが、右回りが HP に関わるカレルであるのに対し、左回りはスタミナに関わるものでした。つまりこれ、もしかすると HP ダメージの「蝕み」とスタミナダメージの「凍傷(月の虫)」にそれぞれ対応しているんじゃないかと思うわけです。つまり「蝕み」と「瞬間凍結」の差異は、後の「右回り」「左回り」それぞれの変態に対する変態的前振りだったということ(『Bloodborne』の方が先に発売されていますが)。これが正しいなら、「月の虫」とは上位者を始めとした、「左回りの異形たち」に寄生する「おぞみ」の総称である……なんて解釈もありかもしれません。だとするとゴースの寄生虫も「月の虫」の一種だったわけです。わざわざ虫に「月」の名が与えられているのはそういうことなのかなと思ってます。
獣血の主の中には巨大なウジが潜んでいました。成虫にならずウジのまま育つのは、宿主に欠陥があるからではないか。即ち「獣の愚か」であり、体内で虫を成体へと育み得る素質こそ「瞳(≒月)」であるという仮説を立てました。上位者の中でこそ虫は特別に成長する訳です。そして月が「信仰を魔力に変える力」だという認識を踏まえれば、「蝕み」が奇跡であるのに対し、「瞬間凍結」が魔術であることにも繋がります。何があったかは不明ですが、月を介して絵画の底で、「蝕み(信仰)」は「月の虫(魔力)」へと変異したんでしょう。
更に或いは、それは赤子のように、虫でありながら月の力を残すとも考えられます。魔力や理力によって運用こそ可能であるものの、持つものの素質によって本質たる「月」を取り戻す、そんな性質を秘めるのだと考えてみましょう。それを知らぬ者にとってはただの寄生虫であっても、宿すもの、握るものが違えば力を返してくれる。だから上位者に宿る寄生虫は、その月の力ゆえに宿るものを選ぶんです。
人に宿るものではない
ただ握りしめて殴る、武器とも呼べぬ一匹だが この虫は「苗床」の精霊を刺激するという
ゴースの寄生虫 - 『Bloodborne』
月の虫から力を引き出す、「然るべき宿主」への変態。それが「左回り」なんです。
天使は上位者なのか
上位者には「霊体」タイプが存在し、その特徴として翼を得るのではないかと前述しました。では当然の疑問として、「天使は上位者なのか」。
どうなんでしょうね。当たり前の話、確認する術も無いので適当にそれらしい形で着地させたいところ。ただこれに関して言えば前回の記事でヒントっぽいものに触れていたりします。
失敗作と星界の使者の間には明確な差があり、それは「中途半端に開いた花」と、「硬く閉じた蕾」の描写で表されました。素質のないものは早々に花開き、素質あるものこそ「上質な苗床」として蕾を閉じるんです。そしてそれは早々に羽化した巡礼の蝶と、蛹として硬く閉じた巡礼の蛹(天使)の差にそのまま適用できます。

結晶の娘、クリエムヒルト


蛹(蕾)から生じた異形

「星輪草(つぼみ)」と「巡礼の蛹(さなぎ)」、固く閉じたそれらが、より上質な苗床を示すなら、それらから生じた天使と星界の使者とは同等の存在である。「天使」とは「天界の使者」を表す名だったんじゃないでしょうか。
「死者」を養分として「使者」が生まれるという仮説が正しいのなら、不死の巡礼者が常しえに「死」を重ね続けた先に生み出すものもまた同じではないでしょうか。細かい成り立ちは異なれど、根本の仕組みは共通していたのだと考えると面白いかもしれませんね。
ただ星界の使者を例として取り上げるなら、あれには巨大な固体がいたわけです。そして巨大なあれは上位者として扱われています(トロフィー参照)。そうなると天使の背後にも巨大な固体が控えているとか想像出来てしまうのですが、正直そこまでやってしまうと果てがありません(楽しいけど)。
じゃあ別口で掘り下げてみましょう。天使の娘ゲルトルードです。そう、ゲルトルードもまた「娘」でした。シース候補のクリエムヒルト、彼女の存在に含みを持たせるために「娘」の名が在ったと想像するなら、「天使の娘」もまた怪しい。もっともゲルトルードは既に朽ち果てていたようですが、それでも彼女が遺したものがあります。「天使信仰」です。
なぜ巡礼者たちはロスリックを目指したのか。あの土地に天使を生み出す要因があったからだと思いますが、それこそゲルトルードの「天使信仰」だったのだと考えています。
カリムのイリーナが「啓蒙」によって火防女に至ったように、ある種の奇跡と信仰は人に変化を促します。ならば天使への信仰が天使を生んでもおかしくはないのかなと思うんです。天使という幻想そのものが一種の奇跡だと言い換えてもいいでしょうか。一人の「娘」の祈りが、未だ存在しないものへの信仰が、遥かな未来に「天界の使者」という形で実現した。あれはそういう話だったのかなと想像しています。
月光蝶
これも繰り返しになってしまいますが、上位者に進化することが叶いながらも「眷属」として扱われる存在がいます。ロマや星界からの使者(大)、エーブリエタースなどがそれです。要は赤子を生み出せなかった固体が、しかし一面的な素養だけはあるものだから変態できたのではないかと仮説を立てています。胎内の赤子に影響されて母体が変わるのではなく、上位者の血、「月の虫」に反応し、その影響で肉体だけは変態した、そんな流れなんじゃないでしょうか。
上位者に召し上げられている以上、彼女たちは月の力を宿しているのでしょうが、やはり赤子でなければ決定的な要因に欠けるのでしょう。「眷属」とわざわざ区分されているのには理由があるはずです。彼女たちの素養が不完全であった原因の一つは、「年齢」であったと推測します。肉体が成熟していなかった。具体的に言うなら、「子供を作れる体」が出来上がっていなかったんです。未だ子を設ける機能の無い幼子などが、しかし上位者の血と交わってしまった結果、眷属上位者は生まれるんじゃないかと。
ここで再度天使を取り上げてみますが、もちろん蛹に変態する以前の巡礼者たちについて我々は知りません。ただ一人を除いて。その巡礼者は、吹き溜まりの入り口でプレイヤーを出迎えてくれる老婆でした。そう、「妊娠できないこと」が眷属化の条件の一つであるなら、幼子と老人は条件の上で同じはず。もしも巡礼者たちが誰も年月を重ねた老人であるなら、少なくともそこから生まれた天使とはどれも「眷属」だったんじゃないかという、想像の一助です。
そしてもう一つ。『DARK SOULS 2』の冒頭でプレイヤーを出迎える三人の老婆、彼女たちはかつて火防女であったそうです。裏を返せば、火防女とは一生涯続けられるものではない訳です。もし彼女たちが加齢故にその資格を失ったと考えるなら、やはり「赤子を成せるか」という要素は、火防女、ないし女性という「苗床」が、深みのソウルと結びつく為に外せない要素なんでしょう。
さて天使にはまだ面白い特徴が残っています。翼に続き、「半身が触手状である」というものです。「白竜白書」でもお話しましたが、この特徴を持つ者は天使に限りません。
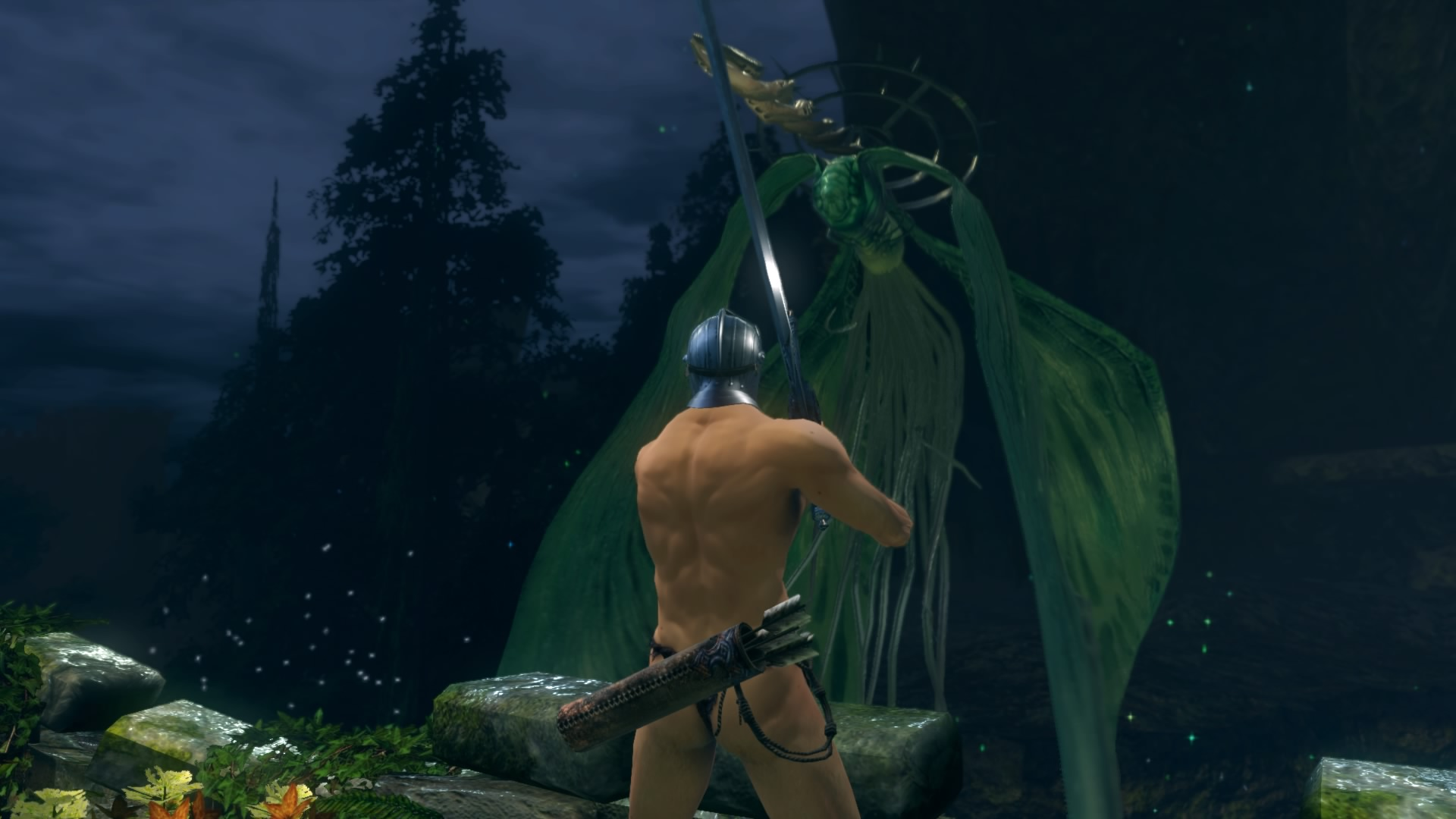
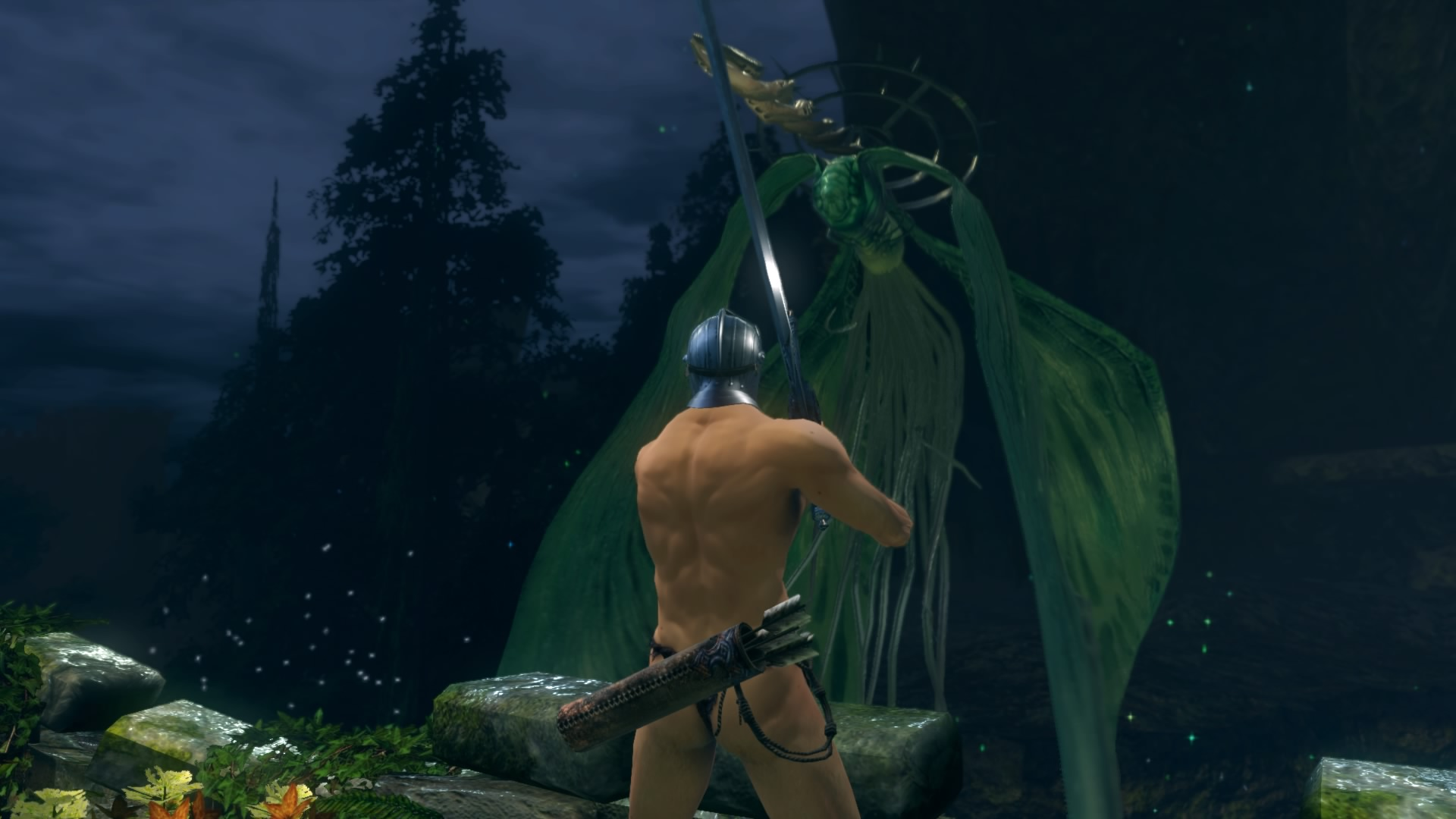





進化の先で「翼」と「触手」を得た皆さま

有翼であり、下半身を根(触手)とする。そんな特徴の合致。これも何度目でしょうか。要は人間の成れの果て、行き着いた先でその進化(変態)は似通った形に収斂するんです。そして改めて色々整理した後でこれらの共通点を持つ異形たちを眺めてみると、どうも世界から火が消えていく過程でこのような存在が生まれてくる事を示しているように思えます。厳密に言うならシースは火の無い灰の時代に進化を遂げ、月光蝶とはそんなシースの被造物でした。そして巡礼の蝶も天使も、火の陰りと共に、深海の到来に呼応するように、人の中より現れました。「似た環境下において、人は似た進化を遂げる」。ここら辺の描写は、シースとゴースの類似性含め、宮崎ワールドの中では結構徹底されているように思います。
では更に、上記の「有翼」であり「半身を触手」とする異形ラインナップの中にもう一体加えてみたいと思います。星の娘、エーブリエタースです

星の娘、エーブリエタース

「星の娘」。「結晶の娘」「天使の娘」のように、彼女もまた「娘」でした。火防女ないし火防女に近い素質を持つ「娘」であるが故に上位者への進化を許される。「星の娘」とはそれを示す名だったのでしょうか。
思えば外見的特徴以上に、エーブリエタースと天使には共通点が多い。「呪死」と「発狂」は同じものだと過去記事で書きましたが、エーブリエタースと天使には、ビーム攻撃の他、「呪死(≒ 発狂)」させてくるという共通項も存在しました。これらが何のための類似かと言えば、やはり前述した通り、「深海(火の無き時代)」に適応した人間は似た形態と能力を取る、その事実を描く為だったのだと思います。が、この話、これだけでは終わりません。星の娘の正体に思いを馳せるなら、天使よりもむしろ「蝶」を掘り下げるべきなんです。
皆様は「エーブリエタース」という言葉の意味をご存知でしょうか。「酩酊」や「中毒」を意味するそうです。これ、意図してやってるんだとすれば憎たらしいなと笑ってしまうんですが、それらの意味が「血に酔う」といったキーワードを擁する『Bloodborne』の世界観とマッチし過ぎている為に、自然と正解の解釈であるように受け入れてしまうんですよね。しかしながら「エーブリエタース(Ebrietas)」という言葉にはどうやらもう一つ意味があります。
蝶です。
和名が無いみたいなんですが、「エーブリエタース」という蝶が存在するようなんです。では、なぜ星の娘に「蝶」の名が与えられているのでしょうか。
二つの受け取り方が出来ます。エーブリエタースとは上位者でありながら眷属でした。それは彼女の進化の切欠となった上位者が存在したということであり、エーブリエタースはその上位者の眷属でした。ならば月光蝶も同じだったんです。白竜の被造物であり、眷属。或いはその基となったのは、月の力を持つ聖女だったのかもしれない。それが月光蝶の正体の一端であり、「エーブリエタース(蝶)」の名は、「シース上位者説」を裏付けるヒントだったという解釈が一つ。
そしてこの仮説は、そのままもう一つの解釈に接続できます。枷の外れた人が進化の果て、特定の形態を取る。その一種を指して「蝶」と呼ぶなら、至極単純に、こういう捉え方が可能になります。
星の娘、エーブリエタース。彼女は深海の時代の月光蝶だった。

星の娘、エーブリエタース


二匹の蝶

余談 : どこもかしこも虫ばかり
ここで一旦原点に立ち返りますが、本当に「上位者 = 月」なのでしょうか。火の無い時代に火を熾す、それが上位者の本質であるなら、その方法に「月」が有効であるだけで、他に方法はあるのかもしれません。例えば最初から火そのものを宿していたら……と考えてみて、面白そうな奴を見つけました。そいつは「虫」の如きであり、人に憑き、火を熾そうと画策し、何とかつて王のソウルを宿してさえいました。

忘れられた罪人

忘れられた罪人。魔女イザリスの成れの果て。しかもこの依り代となっている罪人、女性だそうです。要素を挙げればその在り方は非常に「上位者的」じゃないでしょうか。公のフレイディア(這う蟲)の横にこんな逸材がいたとは……と、言いたいところですが、「そんな想像も面白い」程度に留めておきます。答えを先に置いてから共通項を探そうとすると幾らでも見つかってしまう気もしますし、正直あまり重要でもない。あくまでも余談ということで。
白い娘(1)
話を戻します。シースは上位者でした。そしてどうやらその胎には、彼女の力の源でもある赤子が収まっている……本当でしょうか。
自分で言い出した仮説に「本当でしょうか」もクソもねえだろという話なのですが、例えば火防女シースが深み(灰の時代)に降り立ち、その影響で彼女の月の力が赤子に代わり、更には母体自身が軟体生物に変態した、という流れを想定してしまうと、それはそれで疑問が生じます。プリシラはいつ生まれたのかと。

半竜プリシラ

半竜プリシラ。その正体について知っていることは多くありません。「半竜」の名、そして純白の容姿から、プリシラとは白竜シースの子なのではないかと推測されています。しかしもしも灰の時代に降り立ったシースが、腹に宿すものの影響で上位者化したのなら、今なお胎に宿るそれはプリシラの存在と矛盾してしまう。
ただまあ、実際のところ、こんなものはどうとでも解釈できるわけです。いま行っているのは、これまで積み立ててきた『Bloorborne』の考察素材が如何に『DARK SOULS』に当てはまるかという遊びなので、要は何となく筋が通っていれば宜しいかなと。シースの胎の子は、例えばプリシラより後に出来た第二子或いはそれ以降の子であるなんてことでも筋は通るでしょう。ではシースを上位者化させたのは、第一子(仮)であるプリシラなのでしょうか。
また、こういうのもアリだと思います。何もプリシラがシースの文字通りの子どもでなくても構わないわけです。シースは様々な人体実験を行っていましたし、月光蝶やスキュラを生み出す過程で「半竜」を生み出した。それこそシースとプリシラの血縁関係は劇中明言されている訳ではないのですし、アリじゃないでしょうか。というわけで、以下。
エルドリッチは暗月の神を喰らい遅々としたその中に夢を見た
密かに隠した、白い娘の夢を
生命狩りの鎌 - 『DARK SOULS 3』
出ました、「娘」。星の「娘」エーブリエタースが仮説の通り、上位者の血によって変質した女性であるなら、半竜もまた上位者シースの血に感応した「娘」だったのかもしれません。便利ですね、「娘」って表記。万能細胞より万能かもしれない。
不義の子にして生命の敵である半竜
半竜プリシラのソウル - 『DARK SOULS』
何をもって不義で、生命の敵なのかは解釈が分かれるところですが、敵対関係にあったはずの神と竜が交わり生み出された子供である、というような捉え方が殆どだと思います。しかし前述したような、生命の理に反する、まともな手段ではない方法で生まれたからこその「不義」という解釈も OK でしょう。幸せなら OK です。
白い娘(2)
そんなわけで、改めてプリシラ。彼女は何だったのでしょう。劇中にヒントらしきものを見出すなら、その中の一つが『DARK SOULS 2』の「緑衣の巡礼」だと思っています。彼女は人が作った「竜の子」でした。ひょっとすると緑衣の巡礼とは半竜プリシラの「やり直し」だったんじゃないでしょうか。それは前作で拾いきれなかった設定を緑衣の巡礼という形でやり直したメタ的な意味でもありますし、或いは伝承の半竜を模倣して出来上がったのが緑衣の巡礼という、設定上の意味でもそうです。プリシラは元々火防女ポジションとして設定されつつも没になった経緯があるらしいですが(ラジオより)、それが次回作で練り直されたと考えると楽しい。では、しかしながら、「竜の子(プリシラ)」を火防女に据えようとしたそもそもの意図はなんだったのでしょう。
「私は人によって生み出された竜の子。かつて定められた因果を超えようとした者たち…その者たちが私を生みました。しかし、その思惑は頓挫しました。私は、失敗作だったのです」
緑衣の巡礼 - 『DARK SOULS 2』
『2』はある意味で火継ぎが当たり前の出来事になってしまった時代のお話で、世界は永遠に火の盛衰という絶望を繰り返さなければならないのか、という命題が掲げられていました。その命題に対する解決策として緑衣の巡礼が設計されたなら、彼女の役割は「はじまりの火が永遠に消えないようにする」といったものだったと推測します。
ではこう発想してみます。緑衣の巡礼が半竜プリシラの「やり直し」であったなら、逆を言えば緑衣の巡礼の役割は、そのままプリシラに期待されていたものだったのではないかと。つまりプリシラもまたはじまりの火を消えぬものとする特別な火防女たるを期待されていて、そして多分、失敗したんでしょう。二人はともに、「朽ちぬ竜の力」を、そのまま「朽ちぬ火」に転用するための被造物だったのではないかと想像します。
ならばこうも言えます。プリシラが火防女であったという設定は、実は没になっていなかった、或いは没になったのではなく、「火防女の失敗作」という形で顕れていたのではないか。だとすれば、彼女が火防女でなかろうとも、火防女であるなら尚更に、半竜プリシラとは「特別な女性」でした。それは遠い未来に「fair maiden」と呼ばれるほどに。ならばプリシラが何者であるかよりも、彼女が何を生み出し得るかの方が重要だと考えます。
最古の魔物
細かい話をします。
全ての上位者は赤子を失い、そして求めている
故にこれは青ざめた月との邂逅をもたらし それが狩人と、狩人の夢のはじまりとなったのだ
3 本めのへその緒 - 『Bloodborne』
「青ざめた血」は上位者や赤子の血を指すと言葉だと言った覚えがありますが、「青ざめた『月』」とはなんでしょうか。表記ゆれかもしれませんが、強いて意味を求めるなら、「母体から独立した赤子」を指すのではないかと推測しています。何度も言ってきましたが、寄生虫と精霊のように、子と母が合わさることで神秘は発揮されます。ですが思えば赤子の中で、狩人の夢の「月の魔物」だけが傍らに母を置かず活動していました。つまり「月」が「赤子」を指すなら、「青ざめた月」とは苗床(母体)というある種の楔から解き放たれた、赤子の中でも特殊な個体を指しているのかもしれません。或いはそこまで成熟して初めて、赤子とは「月の魔物」と呼ばれるに足るのでしょうか。というわけで。
シースはグウィン王に与して古竜を裏切り 後に公爵として王の外戚となったとき その偉大なるソウルを分け与えられた
分け与えられた王のソウル(シース) - 『DARK SOULS』
「分け与えられた王のソウル」のテキストにある「外戚」という言葉は「王の母、或いは母方の親族」を意味するようなので、ここを直感的に解釈するなら、シースはグウィン王の義母に当たると読んでいいでしょう。つまりシースの血に連なる誰か、それは恐らくプリシラが、グウィンとの間に子を設けている。
エルドリッチは暗月の神を喰らい遅々としたその中に夢を見た
密かに隠した、白い娘の夢を
生命狩りの鎌 - 『DARK SOULS 3』
再度引用しますが、「生命狩りの鎌」は『1』でプリシラのソウルから生成できる武器でした。なぜエルドリッチのソウルからそれを錬成できたかという、そもそもの疑問に触れるなら、神喰らいの時点においてプリシラが既に喰われていたのだと解釈すべきでしょうか。しかし当サイトの見解は少し異なります。『暗月の神を喰らいながら白い娘の夢を見た』。血がソウルを宿すなら、即ちグウィンドリンの中にプリシラの血が流れていたが故に、エルドリッチは喰らった神の血肉から、その親であるプリシラのソウルを辿ったんです。大王の末子たるグウィンドリンとは、つまりグウィンとプリシラの子でした。
半竜プリシラの厳密な出自は不明です。シースがお腹を痛めたわけではないのかもしれませんが、それでも「白い娘」にはシースの血(ソウル)が混じっているんじゃないかと思います。ならばグウィンドリンとは神のみならず、半竜を介し、白竜の血をも受け継ぐハイブリッドだということです。そしてこの事実はある可能性を示唆します。上位者シースの血を引き、「fair maiden」プリシラから産まれた、月の力を持つ赤子。最古の上位者が、内なる月より「魔術」を見出した一方、その血は「娘」を介して「魔物」としても結実していたんです。
上位者の血を引く特別な赤子として生まれ、母が無くとも月の神秘を振るう魔物。以てこれを「青ざめた月」と呼ぶならば、世界最古のそれこそ、暗月の神グウィンドリンでした。
「青ざめた」(1)
白竜シースは上位者であり、その血を継ぐグウィンドリンは月の魔物でした。ここから先の話をするにあたって、この二者こそ最も重要な駒と言えます。
さて先に進める前にちょっとした補足。話は飛びますが『DARK SOULS』シリーズにおいて「運」と「人間性」は同じものという部分には度々触れてきました。
火の無い灰の一人、アストラのアンリの愛剣
亡国アストラにあって、最も鈍らとされたもの
だがそれは「本当に貴い者の剣」であり 人の本質的な力、運により攻撃力が高まる
アンリの直剣 - 『DARK SOULS 3』
そしてわざとらしいくらいにこれまで触れずにきましたが、『Demon's Souls(デモンズソウル)』もまた一連の歴史の中に組み込まれている……という想定のもとこの記事は書かれています。そして、そこにおいても「運」は人の本質でした。
デーモン「乙女アストラエア」のソウルから生じた 白鉄の直剣
人が生まれながらに持つ本質的な力により威力を増す、「本当に貴い者の剣」
ブルーブラッドソード - 『Demon's Souls』
ブルーブラッドソードもまた運により攻撃力を高めました。二振りの剣は同じ性質を持つわけです。なぜ「本当に貴い者の剣」がブルーブラッドの名を冠するのかと言えば、現実世界において貴族階級は「純潔」であるために肌が白く、青い血管はその証であり、従って「青い血」とは「貴族(貴い者)」を指す言葉として用いられた、その話が転用されたのでしょう。
では「青ざめた血(Pale blood))」はどうか。なぜ「青い血(Blue blood)」ではないのか。ただのセルフオマージュであり、ファンサービスであり、もじりでしかないのでしょうか。個人的には意味があると思っていて、宮崎社長自身がインタビューでこう答えています。
「ここでは「青ざめた血」を2通りに解釈できると思います。ひとつは空の色。白痴の蜘蛛を倒し、メンシスの秘密の儀式を暴いたときの空の色ですね。そのときの空はとても青白く、血の抜けた体のようです」
(I think there are two different ways you could interpret "paleblood" here.One is the color of the sky after you defeat the Vacuous Spider and the Mensis secret ritual is revealed.The sky there is a very pale blue, like a body drained of blood.)
強調部分は当サイトで施したもの。全文でも無いのでリンク先で確認することをお勧めします。さてこの言葉についてなんですが、個人的に重要かなと思うのは、強調した『青白く、血の抜けた体のよう』の部分です。「青ざめた」ことが「血の抜けた」ことを指すなら、特別な血を示す「青い血」と「青ざめた血」とは、似ているようで対極の意味に取れます。「青い血」は決定的に何かを失い、「青ざめた」わけです。
「本当の貴さ」とは即ち人間性でした。しかし人間性は深みへと澱み、性質をそのままに、しかしよりタチの悪いものに変質します。「青い血」と「青ざめた血」とは、そのまま「人間性」と「人の澱み」の違いを指し、そして「青ざめた血」たる上位者が、かつて人の本質であったものから生まれ、しかし今や決定的に人間とは異なる存在に至ったことを示している、そんな解釈は如何でしょう。
或いは「青ざめた」ことで、それは人間性を失ったのではなく、より濃縮され「人間らしく」なったとも考えられます。火が世界から失われ、今や人は不死ではない。不死であることが人の本質、人らしさであるなら、今や人々は「貴さ」を失い、人の成れ果てたる上位者たちこそが「本当に貴い」のかもしれません。
「青ざめた」(2)
さて「青ざめた」ことを示す「pale」という単語。『DARK SOULS 3』内で結構使われていたりします。
パッと見た感じ思うのが、白竜シースに関わるものたちに使用されているかなといった感想でしょうか。シース、そしてその「娘」プリシラ。同じ単語が絵画守り装備にも使われているのは、思うにあの白衣が「白い娘」プリシラを模したものだからです。
生命狩りの力を帯びており、舞うような剣技は白衣の絵画守りたちに通じるものがある
プリシラの短剣 - 『DARK SOULS』
絵画とその守り人たちもまた謎多き存在ですが、もしかすると彼らの起源はプリシラに行き着くのかもしれません。よって絵画守装備の「pale」とは、プリシラを模したればこその「pale」であり、そして白い娘のそれは、母であるシースから受け継がれた「pale」でした。
「pale」という単語が目立って扱われ始めたのは『DARK SOULS 3』からだと記憶しています。なぜかと考えるなら、それは『Bloodborne』における「青ざめた血(pale blood)」を暗示する為であり、やはり白竜シースが上位者であるという事実を示す「ネタばらし」だったんです。
「青ざめた」(3)
……と、言えてしまえば簡単なんですが、正直なところそう言い切る為にはちょっと工夫が必要になってきます。
- 青白い松脂(pale pine resin)
- 青ざめた舌(pale tongue)
- ロンドールの白い影(Londor pale shade)
これらのアイテムにも「pale」は使われています。さてどう解釈したものか。ですが「青白い松脂」に関してはそう難しくありません。
僅かに光を放つ青白い松脂。
一時的に、右手の武器を魔力強化する。
ときに赤い血がまじるというそれはおそらく樹脂ですらないのだろう。
青白い松脂 - 『DARK SOULS 2』
思わせぶりなテキストをそのまま受け取るなら、この松脂の正体は何らかの生物の体液なのでしょう。「人の汁」が「人松脂」として闇属性を得たことを踏まえるなら妥当な線なんじゃないでしょうか。じゃあ何者の体液かと言えば実のところ何でもよくて、上述したような「左回りの変態」を遂げたものの血は、総じて魔力属性、即ち「神秘」を帯びるんじゃないかと推測します。
上位者の先触れとして知られる軟体生物の抜け殻
軟体生物は多種存在し、医療教会は総じてこれを精霊と呼ぶ
特にまだ滑りを残した抜け殻は、また神秘の力も残しており これを擦ることで、武器に神秘の力を纏わせる
精霊の抜け殻 - 『Bloodborne』
上位者の産物である精霊と根源的には同じ。深海に棲むもの、適応を始めたものたちの「青白さ(pale)」から効能を得る試みは、既に始まっていたわけです。
次は「青ざめた舌」。これは後述します。
問題なのが「ロンドールの白い影」です。火の簒奪を目論んだロンドールと、闇より火を熾す上位者たちの目的は一致していると受け取ることもできますが、あくまで感覚的な物言いとして、ロンドールは深海の時代を望んでいなかったように思っています。ロンドールに関わる闇撫でのカアスはかつて、火の消失の後に訪れる闇の時代を望んでいました。しかし火が続いたが故の副作用なのか、闇と深み(深海)が似て非なるものと考えたからこそ、彼らは消失ではなく簒奪した上で火を保持することに拘ったのではないでしょうか。
となるとロンドールの同胞に「白い(pale)」と刻まれることが腑に落ちないわけです。まあ、言ってしまえばただの表記の仕方ですし、そこまで気にすることではないのかもしれません。作品を構成する全てに思惑が通っていると固執するのも、それはそれで偏見だと思いますので、この話はこれで流してしまってもいいのですが、せっかくなのでちょっとだけ掘り下げてみます。
ロンドールとは亡者の国でした。亡者とは死に続け、人間性を失い続けて至る形態だと認識していますが、彼らは「人間性を失って尚も失われない理性」こそ人間の証だと考えている節があります。
「亡者となり、正気を失うなど、そんな凡夫が、我らの王であるものか! 」
ロンドールのユリア - 『DARK SOULS 3』
ロンドールのユリアのセリフがそれを表すでしょうか。そして人間性とは血と共に抜けるもの。そして血が抜ければ人は「青ざめて」ゆく。「ロンドールの白い影」とは、失われていく人間性と、しかし尚も失われぬ人の本質を志す、彼らの意志を示す名であるのかもしれません。
変質という形で人間性を喪失した先に至る「青ざめた血」と、死と引き換えに尚も失われない強固な「人間の本質(ブルーブラッド)」。両者は異なるものでありながらもやはり似ており、例え用法としては異なるものであっても、その「pale」の根源にあるのは「人間性」、ただその一語なのだと、そう解釈しています。することにしました。
ところで、この似て非なるものへのアプローチは、以下の二文を想起させます。
かつて学長ウィレームは「思考の瞳」のため、これを求めた
脳の内に瞳を抱き、偉大なる上位者の思考を得るために
あるいは、人として上位者に伍するために
3 本目のへその緒 - 『Bloodborne』
ウィレーム先生は正しい。情けない進化は人の堕落だ
教室棟の手記 - 『Bloodborne』
そのまま当てはめていいものではないのかもしれませんが、あくまで人のまま進化しようと思索したウィレーム始めビルゲンワースとは、かつて最も人が人らしくある「亡者」という在り方に拘ったロンドールの、精神的な末裔と言えるのかもしれません。
上位者は暗いソウルを求める
ちょっと、改めて基本に立ち返ります。鱗を持たず、故に欲したシース。古竜の時代にあって、自分だけが持っていないものをシースは欲したと理解していますが、「白竜が上位者である」という視点を得れば、その認識は変わるでしょうか。
「人間って、変なものを好きになるわよね。何かに憑りつかれたみたいに。それとも、憑りついてるのかしら フフフッ。あの、醜い裏切り者もそうだったわ。他人のものが欲しくて欲しくて、しょうがなくて…。滑稽なこと フフフッ。あの“這う蟲”は、今も探してるの。自分が欲しいものをね」
愛しいシャラゴア - 『DARK SOULS 2』
「我らには主がいた 我らは皆、その者によって生み出されたのだ。主には、生まれつき欠けたものがあった。己に足りぬものを求め、他を羨み、憤り、常に憎しみに身を焼かれていた。それはやがて、主を狂気へと誘ったという。その狂気の果てに 我らのような、奇妙な命を生んだのだ」
「主は常に孤独であったのだろう。そして、その孤独が理性を殺してしまった。哀れなことよ。主は、ついに気付かなかったのだ。真に己に欠けていたものが、何であったのか」
「我らは互いを殺すことができぬようなのだ。互いの手でつけられた傷では、死ぬことができん。主の狂気によって生みだされたものが我らなら、この業も、それ故かもしれぬ。もしできるなら、我もお前に協力しよう」
蠍のターク - 『DARK SOULS 2』
たった一体、自分だけに押し付けられた差異や不備が受け入れられなかったのか、或いは岩の古竜たちの生死を超えた在り方を単に欲しただけなのか、とにかくシースは鱗を求めて止みませんでした。原始結晶で仮初の不死性を得ていた辺り後者が理由かもしれませんが、その点についてはちょっと疑問もあります。
古竜たちが纏う「岩のウロコ」とは何か。これは灰の時代に至る以前に忌み人たちが宿していた「人間性」、或いは世界を描く際に用いられた「暗い魂」が形を成したものだと推測します。歴代の状態異常「石化」とはその片鱗(ウロコだけに)であったのだろうと。要は「闇」が形を成したものであるが故に、竜狩りの「光(雷)」はそのウロコを貫く訳です。
それを思うとシースは古竜狩りに加担した存在であるわけですから、「朽ちぬウロコとて砕く方法は存在する」ことを熟知していたはずです。なのに欲した。ならば竜たちが持つ不朽を欲しただけでなく、やはり「自分だけが持っていない」ことが我慢ならなかったのかもしれません。
ではそうしたシース個人の意志は置いた上で、「白竜シースは上位者である」という視点を導入してみましょう。上位者には共通して求めるものがありました。赤子です。ではなぜかと考えて、それは赤子が言わば「生ける火の炉」だったからであり、即ち真に求めていたものは、結果得られる「火」であったのだというのがここまでの総括でした。
月の魔物は血を求めました。狩人に獣と獣以上の怪異を狩らせ、そして得た血の遺志は終にゲールマンの手により月の魔物へと献上される。月の魔物はそうしたサイクルで血を自身へと集積していたわけです。それは神代において火がソウルと闇によって育つ仕組みの再現でした。ならば赤子とは、上位者とは、その先にある「火」の為に、餌たる「闇」を求めるんじゃないでしょうか。そして古竜が纏う「岩のウロコ」とは、即ち凝結した「闇」でした。
上位者シースはウロコを求めました。そこに白竜自身の思惑は勿論存在するのでしょうが、根底には「上位者ならではの欲求」が横たわっていたと考えてみると、それはそれで面白いんじゃないかと思います。「月」と「闇」の結びつきの先に「火」が存在するからこそ、シースはそれを求めた。或いは彼女が宿す内なる「月(赤子)」の為の養分としての闇を、本能的に求めたのかもしれません。
時にある種の寄生虫に感染したカタツムリが、捕食者である鳥の気を引くための挙動を取ったり、宿主となったネズミがネコを恐れなくなるケースがあるそうです。それはあえて捕食されることで宿主を乗り換えようとする寄生虫の創意なのでしょう。上位者とは内に夥しい闇を巣食わせる巨大な宿主でした。果たして神に近しいとされる上位者の、その欲求の、どこからどこまでが本心だったのでしょうか。月の魔物は最期、狩人の HP を極限まで減らし、あえてリゲインを誘っていたようにも思えます。そして自らの血を浴びせ、含ませた。ともすればそれは、「血に宿ったもの」の創意だったのではないでしょうか。本質とは「器」を指すのか、「その中身」を指すのか。白竜の渇望は、果たして本当に白竜自身の渇望だったのか。
そしてこれは生来、闇の宿主と言える人間の在り方を想起させます。ソウルを求めるのは人の本質であり、もってこれを「人間性」と呼ぶなら、人は人間性の器に過ぎないのでしょうか。澱んで尚、人を変えるものが「人の本質」であったなら、上位者と人間、青い血と青ざめた血、そこに見た目ほどの差は存在しないのかもしれません。
月の誓約
さて、暗月の神グウィンドリンは、最古の「青ざめた月」……かもしれませんでした。まあ他に該当者もいないので、そういうことにしちゃいます。上位者の血を引き、そして、もしかすると火防女であったプリシラを苗床に形を得た、赤子の上位者です。
振り返ると、メルゴーや狩人の夢の月の魔物は知りませんが、ゴースの遺子とは男性的な外見でした。そしてへその緒によって瞳(月)を宿した狩人もまた、性別に関わりなく赤子へと変態します。本来は月の力と切り離せないはずの「性別」を、赤子だけが無視できる。故にグウィンドリンは、男性でありながら月を宿したんです。
というわけでまた一つ新しい視点を手に入れました。グウィンドリンが月の魔物であるからこそ見えてくるもの。
「あら、月の香り」
偽ヨセフカ - 『Bloodborne』
「月の香りの狩人よ」
女王アンナリーゼ - 『Bloodborne』
結局のところ、プレイヤーキャラクター含む「狩人の夢」に囚われた狩人たちは、月の魔物によって使役されていたと思っています。一部の女性たちが嗅ぎ取った「月の香り」とは、恐らくはこの事実を示すものです。ガスコインの娘も「懐かしい臭い」と初見時に述べますが、これを他の女性が感知するところの「月の香り」と同様のものとするなら、かつて彼女の父は狩人の夢に囚われており、しかし今は夢を見ていない、その事実から発せられた言葉なんでしょう。付け加えるなら娼婦アリアンナも「おかしな香り」と称します。個人的にはカインハーストの血を引く女性だけが嗅ぎ取っているのかなと考えていますが、話が逸れるのでこの辺りはまた別の機会に。
言いたいことはこうです。夢に捕らわれるということは、ある種の暗月誓約だったんじゃないかと。そう考えてしまうと、『Bloodbonre』冒頭で契約書を書かされた描写がじわじわと効いてきます。思えば『Bloodborne』とは、終わらない獣狩りの夜それ自体が一つの悪夢だったのではないかなんて解釈もあるようですが、夢から夢へ、他世界と他世界を跨ぎ、死しても死なぬ狩人の様は、暗月の刃として召喚される復讐霊に似ている。そして暗月の刃も狩人も、共に「狩りの証」をそれぞれの主へと捧げる定めでした。きっとそれは誓約者に課せられた義務であり、約定の証なんじゃないでしょうか。
古い青教との約定に基づき 神の敵たる闇霊を狩った証
約定の証 - 『DARK SOULS 3』
目的や性質は違えども、古来より狩りには、それを捧げる者がいたのではないかというお話でした。
そして目を引くポイントがもう一つ。『DARK SOULS 3』にはシーリスという NPC が登場しますが、彼女は暗月の誓約下にありました。
薄暮の騎士は名も無き月に仕えるものであり 故にその装束は女性的なシルエットを有する
薄暮のヴェール - 『DARK SOULS 3』
「名も無き月に仕える」「故に女性的」、どういう意味でしょうね。お気づきかもしれませんが、「月に仕える女性」という在り方は、かつてアノール・ロンドで見えた暗月の女騎士をなぞったものです。「故に女性的」とは、そういう「ならわし」を示したのだと解釈しています。
では「名も無き月」とは何か。グウィンドリンの名が伝わっていないという意味か、ヨルシカの事ではないのか、はたまた別の月の神ではないか、などと色々推測できると思いますが、気にして欲しいのはこちらです。
薄暮の騎士は名も無き月に仕えるものであり
(Sunless Knights serve the nameless moon, )
薄暮のヴェール - 『DARK SOULS 3』
ローレンスたちの月の魔物。「青ざめた血」
(The nameless moon presence beckoned by Laurence and his associates. Paleblood.)
教室棟の手記 - 『Bloodborne』
後者の和訳では端折られていますが、「ローレンスたちの月の魔物」とは、正確には「ローレンスたちの(名も無き)月の魔物」だったみたいです。「青ざめた血」とは、名も無き月の魔物の仮称、或いは魔物たる上位者という種そのものの別称だったのでしょうか。この共通点に意味を持たせるなら、シーリスが仕えた「名も無き月」もまた、名を持たぬ赤子、いつしか生まれた「月の魔物」だったと考えてみるのはどうでしょう。恐らく深海の時代に入りかけていた火の末期において、既に他の上位者ないしその赤子が生まれ始めていたのでしょう。
名もなき月とシーリス。その在り方は、グウィンドリンと真鍮の女騎士のなぞりでした。ならばその後生まれてくる赤子たち全てがそうなのかもしれません。原点たる暗月の神をなぞるように、ずっと騎士を募り、放つんです。狩りを全うするために。
月の香りの狩人。起源は暗月の剣、その騎士にありました。
余談ですが、狩人の夢も、メンシスの悪夢においても、赤子はその傍らに乳母を置くといった話をしました。それは古く、暗月の神や名も無き月が、傍らに女騎士を置いたことがその発祥だったのかもしれませんね。メルゴーの乳母とは、乳母でありながら女騎士だったんです。







「月」の傍に女あり。

月の魔物。古来よりその傍らに在ったのは、狩人と、女性でした。
わが子を喰らうオスロエス
そろそろシース周りの話から先に進めましょう。火の時代に上位者を探すなら、その内の一体に彼を挙げます。妖王オスロエスです。
ここで「ん?」と疑問符を浮かべてくれたのなら、正直嬉しい。上位者への変態は女性にしか起こり得ないというのが原則であったはず。しかし一方でその原則を無視する方法が存在していました。「へその緒」ですね。元々、ある種の女性は赤子を宿す(正確には内なる月が赤子に変化する)ことで、宿主である母体を相応しい苗床へと変態させました。へその緒による変態もまた同様の仕組みに則っているのであり、要は「月を宿す」ことで、宿主は変化を迎えるわけです。へその緒は「妊娠」という経路を用いない、つまり性別に関わりなく人を進化へと導く方法でした。
さて当サイトでは原則、没データを考察の素材としません。それが「設定上存在しないことになった」という意味での「没」なのか、「設定上は残っているけれど描写が省かれている」だけの没なのかの区別がつかないからです。しかしオスロエスには興味深い没イベントが存在します。動画はこちらですが、没データであることと、やや衝撃的な内容である点に御注意を。
本編からは抹消されていますが、どうも動画の内容として、オスロエスはオセロットを喰っているようです。経緯は不明ですがこう解釈します。さながら透明の赤ちゃんを抱いているかのようなオスロエスですが、その実、彼は既に我が子を喰らっていたのだと。ならば、「fair maiden」が赤子を宿し変態するように、狩人がへその緒を使用することで赤子に変わったように、そしてそれら二つの手段とも異なる、「食べる」という手段をもって、オスロエスは「月」を得たんです。ならばあの姿の説明もつくのではないでしょうか。
実のところオスロエスが何かを切っ掛けにあのような姿に変わった……というようなテキストは存在しないので、もしかすると生まれながらにあのような化物だった可能性もあるっちゃあるのかもしれませんが、その線は他の方に任せます。オスロエスは人として生まれ、しかし我が子を喰らい、上位者へと変わりました。
王はロスリックの血の営みに発狂し 大書庫の異端と繋がったという
それは白竜シースの歪んだ信仰だった
妖王オスロエスのソウル - 『DARK SOULS 3』
先王オスロエスは、竜に魅入られ妖王となり 多くの刺客を差し向けられたという
しかし誰一人、無事戻るものはなかったと
影シリーズ - 『DARK SOULS 3』
オスロエスは自国の「血の営み」に狂い、大書庫の異端、即ち白竜シースの歪んだ信仰と言ったものと繋がったそうです。過去記事で述べたことですが、恐らくこの時点でオスロエスの中にはある変化が訪れます。信仰とは奇跡に通じ、奇跡とは物語であり、そして物語とは啓蒙です。妖王は、白竜の啓蒙を得たのです。
かつて「ビッグハット」は白竜に共鳴し 裸の探究の末、その神の業を己のものとしたという
オスロエスはそれを知り、また啓蒙を得たのだろう
白竜の息 - 『DARK SOULS 3』
白竜シースの名で伝わる伝説のドラゴンウェポン
妖王オスロエスは妄執の先に月光を追い だが、それに見えることすらできなかった
月光の大剣 - 『DARK SOULS 3』
しかし白竜を信仰しながらも彼は月光に見えなかったそうです。何度も言ってますが、オスロエスが男性だからでしょう。しかし彼自身には無理でも、彼の内なる啓蒙(物語)は、彼の子供らに受け継がれていきます。ゲルトルードの天使信仰、ロスリック王子が扱う「羽」の舞う魔法に関しては上述させて頂きました。これらは彼らの月の力の賜物なのだとも。
そして肝心要となるのはオセロットです。
「ああ、愚者どもめ。ようやく気付いたのだろう。愛しいオセロット、竜の御子の力に。だが、そうはいかぬ。この子は、私のすべてだ」
オスロエス - 『DARK SOULS 3』
真実、何が生まれてしまったのかは分かりません。しかしオスロエスの語る「竜の御子」とは、果たして本当に「竜」に纏わるものであったのでしょうか。狂った彼の崇拝する竜とは、ウロコのないシースを指すのであり、ならば産まれたオスロエスとは、彼が追った「月光」を体現するような、そんな子であったのだと推測します。オスロエス自身は性別故、月光に見えなかった。しかし彼が得た啓蒙は子らへと継がれ、やがて「月の魔物」オセロットが生まれたんです。
そして父はそんな我が子を喰らい、白竜に似た姿へと変態します。これは赤子を宿し母なる上位者に至る道とも、へその緒によって自身を赤子へ至らしめる道とも異なるものです。



なりたい自分に。

しかし疑問も残ります。オスロエスのソウルから月光の大剣が錬成できるのは、彼がシースの啓蒙に触れていたからだと思いますが、しかしあの姿に至って尚、やはり妖王は月光に見えること叶わなかったのでしょうか。そう取れるテキストではあります。ならば妖王とは、実験棟の失敗作たちのような出来損ないだったのか、仮にも赤子を摂取している訳ですから、不完全とは言え上位者だったのか。或いは上位者に至りながらも、月を宿すには足らなかった故に眷属上位者に留まったと考えられる、ロマやエーブリエタースらと同じ「見捨てられた」上位者なのか。そんな感じで色々と想像だけなら出来る訳です。
というわけで、妖王オスロエス。たぶん上位者でした。自らの血を舐めて甘いと感じることが啓蒙の本質に似るならば、自分の子供を食べて得られるものもまた啓蒙なのでしょうか。
補足 : なりそこないたちの水銀
属性とは面白いもので、ダメージの増減で対象のバックボーンを推し量ることが可能になります。例えば『Bloodborne』のネズミは炎にも弱いのですが、雷にも弱い。人を食べた際に取り込んだのか、彼らを倒すとスローイングナイフをドロップしますが、つまり体内に金属を所有する故に雷の通りが良い訳です。そしてこれも何度目か分かりませんが、「獣」が炎に弱いのは、彼ら自身というより、彼らの血に潜む寄生虫が炎で焼かれてしまうためではないかと推測しています。この通り、属性とは重要なヒントになるんです。
さて『Bloodborne』において「眷属」に類するエネミーに(全てではないですが)共通する特徴があり、それは「雷属性がよく通る」です。答えは単純で、恐らく彼らの体液が「水銀」だからだと思います。
通常の弾丸では、獣に対する効果は期待できないため 触媒となる水銀に狩人の血を混ぜ、これを弾丸としたもの
水銀弾 - 『Bloodborne』
水銀弾とは秘儀に際して消費されますが、つまりは神秘を招く触媒でした。同じく触媒である血を混ぜることでその効能は上昇するのでしょうか。また所構わず沸く使者たちですが、彼らは白っぽい液体から沸き出でているように見えます。たぶん水銀です。火は失せ、唯一残った闇のソウルも深みへ沈んでしまった時代において、現実世界で神秘を招き、或いは維持する為には触媒という「言い訳」が必要になっているのだと思います。だから使者は水銀溜まりを通り道としなければならず、神秘的変態を遂げた眷属たちは水銀で満たされていなくてはならない。眷属たちを切りつけた際の血飛沫がおおよそ白っぽいのは、彼らの中を水銀が循環しているからであり、金属で満ちたその体には、それ故に雷が通るんです。
さて話が戻りますが、「青白い松脂」はイルシールの地下牢で入手できる遺灰によって売り出されるものですが、あそこで蠢く囚人「なりそこない」たちがドロップする品でもあります。あの松脂は左回りの変態を遂げたものたちの体液だと前述しましたが、はっきり言ってしまえばあのなりそこないたちから抽出されたものなのだと思います。そしてなりそこないたちもまた雷に弱いんですね。そしてあれらは竜のなりそこないなのだと。
それは貧相な尾骨から削り出されたものであり 彼らはそれを、竜の証であると信じている
尾骨の短剣 - 『DARK SOULS 3』
尾骨から削り出された武器は僅かばかりではありますが竜の力を宿します。なりそこないたちは、なりそこないであっても竜であるから、古竜たちがそうであったように雷に弱いのでしょうか。多分違うんじゃないかと思っていて、やつら体液が水銀になりかけているんじゃないかと思います。青白い松脂から見て取れるように赤い血液を残しながらも、その体組成が金属化を始めているんじゃないでしょうか。
そして妖王オスロエスですが、こいつも雷がよく通ります。なりそこないたちと同じ理由なんじゃないかなと思ってるんですが、どうでしょう。オスロエスがおあつらえ向きに「致死の白霧(水銀)」を使ってくるのはその暗示、と考えるのは都合良すぎでしょうか。竜になりそこなった者たちが、皮肉にも自分が目指した存在と、弱点だけは同じものを抱えた。しかしその弱点すらも同じ理由ではなく……と、そんな涙を誘う描写なのかなと。
体液の水銀化は「眷属」に類するものたちの特徴でした。それは上位者であっても変わらない。火の失せた時代に神秘を扱うものは、内に「月」という根拠を持たない以上、己を上質な触媒で満たすといった工夫が必要になるんです。火の陰りに現れたであろう、イルシールのなりそこないたちも同様であり、それは最後まで月に見えること叶わなかったオスロエスも同じ。なので仮にオスロエスもまた上位者なのだとして、やはり精々が「眷属」止まりだったのかなと想像しています。
白竜の啓蒙に触れ、白竜のなりそこないになった上位者オスロエス。それが上位者シースの眷属だとして、妖王にとっては望むところなのでしょうか。
生まれ変わりの fair maiden
(たぶん)眷属上位者オスロエス。彼の子オセロットは月の魔物だったという仮説を立ててみました。しかし上位者を信仰し、その啓蒙に触れたからと言って、産まれる子供が上位者であるというのは簡単過ぎます。そんなに簡単ならビルゲンワースや医療協会は苦労していないわけです。赤子を欲するなら、特別な母親(苗床)を用意する必要があったはず。というわけで赤子の上位者オセロット、その母親に注目してみます。
彼女は先王オスロエスの妻であり豊穣と恵みの女神にすら例えられたが 末子オセロットを産んだ後、姿を消したという
女神の祝福 - 『DARK SOULS 3』
同じ記事を再掲しますが、オスロエスの妻について掘り下げています。豊穣と恵みの女神にすら例えられたという彼女の正体は、深みの聖堂に座する「生まれ変わりの母、ロザリア」であり、グウィネヴィアの子孫だと考えています。
太陽の光の王女グウィネヴィアに仕える 聖女たちに伝えられる特別な奇跡
太陽の光の恵み - 『DARK SOULS』
母であり妻であったグウィネヴィアの奇跡は その恩恵をひろく戦士たちに分け与えた
太陽の光の恵み - 『DARK SOULS 3』
「太陽の光の恵み(『3』)」のテキストにある一文「母であり妻であった」とは、ことロザリアに関して言えば多分文字通りの意味だと思います。つまりロスリック唯一の王女として建国以来、歴代の王との間で子供を作り続けてきたんでしょう。子々孫々に至るまで近親相姦を繰り返してきた。これがオスロエスを発狂させた「血の営み」であり、そうして神の、グウィンの血を濃縮していった先、ロスリック国は王のソウルを顕現させようとしたんです。
その試みはロスリック王子という形で一応の結実を果たす訳ですが、それは一先ず置いておき、末子オセロットが月の魔物であったという仮説の上、ロザリアもまた「fair maiden」であったことになります。疑問なのは王妃に月の力があるなら、親から子に受け継がれる形で、歴代の王にも少しずつそれは宿っていたのでしょうか。はたまたシースの啓蒙に触れた後のオスロエスに影響される形で、王妃もまた啓蒙を得、「fair maiden」に至ったのでしょうか。詳しいルールにまで手を出すと再現が無いので止めておきますが、少なくとも彼女には、産み落とし、或いは生まれ変わらせた対象に月の力を付与する能力があったのだと思います。それは実子たちもさることながら、蛆人たちにすら宿っていました。

蛆と羽

蛆人の魔法からも「羽」が散っているんですね。もっとも「羽」と「月」の関係についての仮説に基づく訳ですが、一人の女性が関与した子供と蛆人たちの魔法に「羽」という特徴が共通していたというのは覚えておいて損がないはず。
で、さきほど「後述する」と言っておいた「青ざめた舌(pale tongue)」についてですが、まあ、そこまでの意味は込められていないかなと思っています。強いて言えば「示唆」ではあるかなと。「血が抜けた」故に「青ざめた(pale)」わけで、それは前述したような「人間性の変異、澱み」を示す言葉として採用されている可能性はあります。深みという領域が人間性を変えてしまうように、ロザリアという「fair maiden」は、まさしく人間性に手を加えることで、肉体たる器すらも変質させてしまう。「青ざめた舌」とは、彼女が持つその変質能力の「示唆」なんでしょう。
重要なのは、月の魔物を産んだ以上、彼女は「特別な母体」であったということ。彼女が深みの聖堂に身を寄せていたのは、彼女自身の意志ではなく、深みの信徒たちがロザリアという苗床の向こうに深海の可能性を見出したからなのかもしれません。
補足 : うじんちゅ
ロザリアの寝室に通った女たちの成れの果て。魔術を使う。
蛆人 - 『DARK SOULS TRPG』
『DARK SOULS TRPG』の記述なんですけど、結構重要なことをさらっと言ってます。グループ SNE がフロム・ソフトウェアからどの程度の資料を開示されているか分からないので鵜呑みには出来ないのですが、あの蛆人たちは公爵の書庫のスキュラたちと重ねられている部分もあると思っていて、かつ当サイト解釈によるところの「羽(月)」を扱うこともあり、「へー」という感じ。
それはともかく、気になるのはロスリック王城とイルシールにいる蛆人たちです。



蛆人調査隊

蛆人たちが「深み」の勢力というより、ロザリアの崇拝者としてあの場にいたのなら、彼女たち(?)がそれぞれどのような理由で派遣されていたのか考えてみるのも面白いでしょう。ロスリックの方は「ロザリアの娘」の様子を見に来た、と単純に考えていいかもしれません。娘さん、お元気でしたよーって。しかしそれだといまいち分からんのがイルシールの蛆人。遺体になっていた理由は、たぶん過去記事で話したと思うので掘り下げませんが、たぶんあの国の水が合わなかったのかなと思ってます。じゃあなの為に来たのかというと……なんでだろ。ロザリアの血のルーツはアノール・ロンドにあるので、聖地巡礼の途中だったのかもしれません。
もしそうでないのなら話はちょっと変わってきます。ゲルトルードはロザリアの子ですが、「天使の娘」でもあります。そしてイルシールは月の虫が蔓延る地です。ロザリアの思惑こそ測りかねますが、蛆人たちはそういった「深海の時代」の予兆のようなものを探りにきていたのかもしれません。獣に潜むものがそうであるように、「蛆」が成虫に至れない未成熟の証と見るなら、蛆人たちはそれぞれの場所に夢を見に来たのでしょうか。
月の魔物が火の炉なら
オセロットは月の魔物でした。父親に自覚できぬ月が宿り、それが特別な母親と交わることで生まれた結果なのだと思います。そして「月」はゲルトルードにも受け継がれ天使信仰を生み、そして王子ロスリックもまた「羽」を宿しました。こう考えると、「男性でありながら『月』を宿す」という意味でロスリック王子は「月の魔物」的ではあります。
実際のところ、そう間違った見方ではないのかなと思うわけです。過去記事においてロスリック王子の正体を考えてみましたが、前述した通り、血の営みによって神の血を濃くし、やがて最古の王グウィンを再現するという試みの果てにロスリック王子が生まれました。それは成功ではあったのですが、異なる側面もあります。ロスリック王子はその能力、セリフにおいて暗月の神グウィンドリンと似通い、また声優も同じ。つまりグウィンを作ろうとしたらグウィンドリンができちゃったのがロスリック王子なんです。
以前の記事ではここで止まっていましたが、これは逆に考えることも出来ます。
緑衣の巡礼がプリシラの再現だと仮定すると、緑衣の巡礼がそうであるようにプリシラとは「造られた火防女」だったのではないかと推測できました。ではロスリック王子がそうであるように、グウィンドリンもまた「造られた薪の王」だったと考えてみていいのではないでしょうか。そうすると、ここにそのまま「月の魔物は『生きた火の炉』である」という仮説が接続できるわけです。
陰の太陽はなぜ生まれたのか。火の陰りに備えた「薪」として用意されたのかもしれませんし、そうではないのかもしれない。それが正しいとしても、では、なぜ使わなかったのか。こういったことから神々の思惑を想像してみるのも楽しいでしょう。
月蝕(1)
思えばむやみに長くなってしまったこの記事シリーズですが、振り返って、自分の中で「繋がった」と思えたのは、『DARK SOULS 3』で「人の澱み」というキーワードが登場した瞬間です。「人の澱み」は深みにおいて虫となり、「人の淀みの根源」とは虫である。そして上位者ゴースの中には、果たして虫が巣食っていました。
やがて火は消え、暗闇だけが残る。
OP より - 『DARK SOULS』
火の無き深海の時代とは、唯一残った闇のソウル(人間性)から神秘を取り出す世界です。様々なものに形を変える闇を深みから掬い上げ力に変える。例え神秘が虫の形に変わり果てたとしても、それを成し遂げたものこそ、次代において神に近しく、「上位者」と崇められる権利を獲得します。
深みの聖者エルドリッチ。彼は人喰いを繰り返すことで際限なく肥大した肉塊でした。人間性とはダークソウルの欠片だと言います。ならば逆を言えば、人間性をより集めればそれは限りなく「ダークソウル(暗い魂)」に近しいものになるのでしょうか。「闇」もまた王のソウル。故に、エルドリッチは体内で捏ね上げた闇のソウルを以て薪の王に上り詰めた訳です。ならば同時にそれは、かつてカアスが予見した「闇の王」と言うべき存在でしょう。薪の王にして闇の王。しかしエルドリッチは、その先を見通していました。
深みは本来、静謐にして神聖であり 故におぞましいものたちの寝床となる
それを祀る者たちもまた同様であり 深い海の物語は、彼らに加護を与えるのだ
深みの加護 - 『DARK SOULS 3』
深みに潜む蟲たちは、小さな顎に牙を持ち 瞬く間に皮膚を裂き、肉に潜り込む
蝕み - 『DARK SOULS 3』
エルドリッチの汚泥の如き体には、おぞましい虫が溢れかえっていました。これらは恐らく人間性の成れの果て。深みにはおぞましいものたちが潜むといい、それら「おぞみ」の正体が、人間性の澱みであることを考えると、エルドリッチの肉体は、それ自体が深みであることが分かります。ダークソウルの欠片たる人間性が澱み、濃く溜まった場所は「深み」となる。故にエルドリッチは「深みの聖者」と謳われるのでしょう。
長く続いたこの記事シリーズ。その中で紹介してきた様々な仮説の、彼は集大成でした。上位者エルドリッチ、しかしそう呼び表す為には、幾つかの工夫が必要となります。



宿主たち

月蝕(2)
エルドリッチの残したものから鑑みるに、その影響力は「上位者的」です。
深みの聖者エルドリッチの残した歪んだ指輪。
致命攻撃時に FP を回復する。
おぞましい人喰いで知られるエルドリッチはきっと伝えたいのだろう。
悲鳴に浴し、生命の震えをこそ喰らうやり方を。
エルドリッチの青石 - 『DARK SOULS 3』
深みの聖者エルドリッチの残した歪んだ指輪。
致命攻撃時に HP を回復する。
(以下同文)
エルドリッチの赤石 - 『DARK SOULS 3』
お気づきでしょうか。「エルドリッチの青石」と「エルドリッチの赤石」は、それぞれカレル文字「オドンの蠢き」と「血の歓び」に対応しているんです。
人ならぬ声の表音となるカレル文字の 1 つ
「蠢き」とは、血の温もりに密かな滲みを見出す様であり 狩人の昏い一面、内臓攻撃により、水銀弾を回復する
オドンの蠢き - 『Bloodborne』
人ならぬ声の表音となるカレル文字の 1 つ
「血の歓び」とは、血の温もりに生の喜びを見出す様であり 狩人の昏い一面、内蔵攻撃により HP を回復する
カレル「血の歓び」 - 『Bloodborne』
エルドリッチが後のオドンである……という意味ではないです。それも面白いと思いますが、ここで言いたいのは、後の「人ならぬ声」と類似の効果を宿すものをエルドリッチが残していたという点。もちろんカレル文字が上位者に由来するものとは明言されておりませんが、興味深い描写ではあるんじゃないでしょうか。神話の時代に神々や英雄が振るった力を、我々は「指輪」という形で借り受けました。カレル文字、人ならぬ声の表音とは、その系譜なんでしょう。
そしてもう一つ、エルドリッチが残したものがあります。「腐肉」です。

腐肉落ちてますよ。

ぬめぬめと歩を進めるエルドリッチから零れた、肉体の欠片でしょうか。名前はそのまま「エルドリッチの腐肉」ですが、考えようによってはこれ、「上位者の先触れ」に似ます。
地下遺跡の各所に巣食う、奇妙な小生物たち
特にナメクジは、見捨てられた上位者の痕跡である
真珠ナメクジ - 『Bloodborne』
上位者の先触れとして知られる軟体動物の抜け殻
軟体生物は多種存在し、医療教会は総じてこれを精霊と呼ぶ
精霊の抜け殻 - 『Bloodborne』
精霊が具体的にどうやって上位者から生まれるのかは不明ですが、案外エルドリッチの腐肉のように体から剥がれ落ちるようにして出現するのかもしれません。軟体生物は、虫の二次感染を目的とした「自律行動する種付け装置」。腐肉もまた同じ目的かどうかは分かりませんが、とにかく「痕跡を残す」という意味で、やはりエルドリッチの在り方は上位者的に描かれているように思います。
ちなみに劇中、腐肉と称されるエネミーは三種出現するはずですが、「深淵」属性を帯びているのはエルドリッチのそれだけです。肉体自体が深淵、そして剥がれ落ちた欠片もまた、深淵。迷惑。
月蝕(3)
が、やはりおかしい。月の力とは女性にしか宿らず、故に上位者とは女性にのみ到達できる地平である。自分で言いだしたとは言え、このルールは強固であり、そう易々と破られたら堪ったものではありません。何よりも、獣血の主がそうであったように「上位者になれなかったもの」の象徴として蛆虫は存在します。そしてエルドリッチに宿る虫もまた、どうにも蛆でした。



エルドリッチの寄生虫

ならば単純、薪の王にして闇の王エルドリッチは、しかし「上位者のなりそこない」と言うべきなのでしょうか。
こんな記事を書きました。
人の澱みについて、そしてエルドリッチの神喰らいについての私見が主な内容となっております。長いので読まなくていいです。
エルドリッチの足跡として、まず薪の王として火を継いだ後、火の陰りに呼応して蘇ります。その後彼はイルシールへと旅立つわけですが、その前に深みの聖堂へと立ち寄っています。何のためか。ロザリアと交わるためだと思います。



子作りに来ました。

無理やりこじ開けた鉄格子、侵入者から「母」を守ろうとしたのか、しかし壁に縫い付けられる蛆人たち。これを見る限り、ロザリア勢力とエルドリッチ勢力は友好的ではなかったんでしょう。そして寝室において何が行われたかは分かりませんので、これは勿論推測ですが、ロザリアが抱く一際大きな蛆虫、或いは肉の塊。これはエルドリッチとロザリアの子供だと思います。

肉塊くん。

別の解釈もありです。この巨大な肉塊は関係なく、エルドリッチはロザリアに「生まれ変わり」を頼んだと捉えてもありでしょうか。もしかして性別を変えてもらおうとした? しかし個人的にはやはり子を為そうとしたのだと思います。なぜなら全ての上位者は赤子を求めるからです。
上位者のなりそこないだと言ったり、上位者だと言ったり、どっちなんでしょうか。しかしエルドリッチの在り方が「上位者的」である以上、やはり「上位者のように」、上位者が欲するものを求めるんでしょう。しかし目的は果たされませんでした。だからこそ、エルドリッチはアノール・ロンドへと向かうんです。
しかし何のためにエルドリッチは、上位者は赤子を求めるのか。それは赤子それ自体ではなく、赤子が持つ力により、その先にある「火」を求めているからです。
使用により啓蒙を得るが、同時に、内に瞳を得るともいう
だが、実際にそれが何をもたらすものか、皆忘れてしまった
3 本目のへその緒 - 『Bloodborne』
人喰らいにより王の資格を得たエルドリッチは しかしその玉座に絶望し、神を喰らいはじめた
王の薪(エルドリッチ) - 『DARK SOULS 3』
彼は陰った火の先に、深海の時代を見た。
故に、それが遥か長い苦行と知ってなお 神を喰らいはじめたのだ。
エルドリッチのソウル - 『DARK SOULS 3』
幾つかの記事で、エルドリッチの目的について推論を述べてきました。しかしそのどれも不完全であり、『DARK SOULS』『Bloodborne』双方の要素を合わせなければ答えが出ないものだと考えています。エルドリッチが絶望したのはなぜか。継いだ火が、いずれ消えると知ったからではないでしょうか。ならば求めるべきは、消えた後、闇から火を熾す方法です。そしてそれは、「月」の力を以てのみ、或いは可能になる所業でした。全ての上位者がそうであるように、深海の時代に火を追い、故に赤子を、月の力を求めることがその道。やがて皆が忘れてしまったものを、この時のエルドリッチだけは理解していたんじゃないかと思います。
だからエルドリッチは、月の魔物グウィンドリンを喰らったんです。



月の蝕み

月蝕(4)
エルドリッチは火の時代の名残として、現存する神々を喰らい始めたと解釈してもいいかもしれませんが、個人的にはミスリードではないかと思っています。この「神喰らい」とは、即ちグウィンドリンのみを指すのではないかと。
特別な器と赤子。それらは精霊と寄生虫のように、共にあることで神秘を生みだします。乳母がメルゴーを抱くことで力を得たように、母体を傍らに置いた遺子が太陽の光を操ったように、女王ヤーナムが狩人を拘束したように、そして或いは上位者シースが内なる月の力より「魔術」を拓いたように、妖王オスロエスが我が子を喰らうことで白竜の似姿を手に入れたように、やはりエルドリッチもまた、月を喰らうことでその力を身に宿します。

月光への呼びかけ

その手法こそオスロエスと同じかもしれませんが、妖王とは異なりこちらは明確に月の宿主として適応しようとしているように思えます。それは「人喰い」として培ったエルドリッチの経験によるものなのか、器としての出来の違いなのか。
エルドリッチが上位者なのか、なりそこないに過ぎなかったのかと言ってきましたが、やはり彼は上位者と言っていい存在だったんじゃないかと思えてきました。なぜなら赤子とは火を熾す為の「生きた炉」であり、手段に過ぎない。ならばエルドリッチは既に宿している訳です。王のソウルという「火」を。

火の宿主

だから言ってしまえば、エルドリッチはかなり例外的な上位者だったのだと思います。月の力に頼らずとも火を宿す、あらゆる上位者たちが求めて止まないものを備えた存在でした。しかし「はじまりの火」そのものがそうであるように、王の薪もまた火を失うのでしょう。だからこそ彼は、火の後に残る暗闇から再び火を熾す為に、月を喰らい始めたんです。
エルドリッチの人格については全く分かりません。赤石等のテキストを読む限り人喰い大好きマンだった可能性もありますが、それでも火を継ぎ、更にその先の深海においてさえ火を灯そうとしたのは、純粋に世のため人のためだったのでしょうか。もっともその大いなる目的は頓挫し、しかし彼の遺志は後の世、数多の軟体生物たちが引き継ぐことになります。
深みの聖者エルドリッチ。薪の王、そして闇の王にして、火の時代の上位者でした。
さいごに
終わった! いや相変わらず間を開けてしまって申し訳ございません。いつにもましてグチャグチャですが、とりあえずこれで『DARK SOULS』と『Bloodborne』の繋がりについては大部分を書き終えました。全部じゃないです。だからまだこのシリーズはあと一回だけ続きます。次回「火と楔と血の話」、最終回。ようやく「楔」の話です。
あと火の時代に生まれた上位者についてはもう一体存在すると思っています。それに関しても、別の機会に。ではまたお会いしましょう。