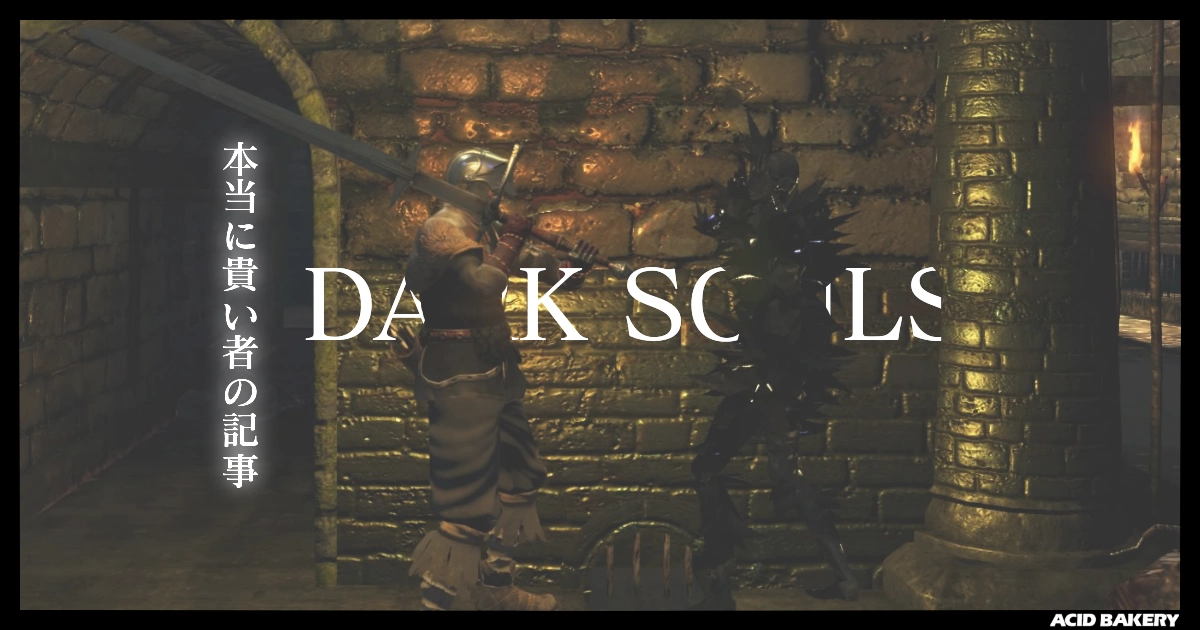怨嗟・鬼討ち・深淵狩り
2019.12.22
『DARK SOULS』シリーズと『SEKIRO』についての記事です。因縁は続くのだと、唯それだけのシリーズ。
記事同士の接点は特に無いのでお読み頂かなくても問題ありませんが、興味とお時間がありましたら是非どうぞ。

隻腕の狼、深淵を討つ。

怨嗟の炎
『隻狼』とは、復讐の物語でした。
「恐怖は絶対。一時の敗北はよい。だが手段を選ばず、必ず復讐せよ」
梟 - 『隻狼』
忍びが主を奪われ、ついでに腕も切り落とされる衝撃から幕は上がります。『隻狼』は復讐の物語。それは主の奪還、或いは自らを害した義父との決着も意味するでしょうか。しかし復讐、その言葉が含むものは大きく、劇中では「怨嗟」なるキーワードが登場します。
戦場にいたのは、怨嗟の炎に飲まれた、隻腕の鬼であった
戦いの記憶・怨嗟の鬼 - 『隻狼』
ある男が、修羅になりそこない、怨嗟の炎の積り先となった
因果ゆえ、なかなか死にきれぬ
だが鬼となり、ようやく逝けた
戦いの残滓・怨嗟の鬼 - 『隻狼』
この奥義を最後に、仏師は忍義手を捨てた。
極め、殺しすぎた。怨嗟の炎が漏れ出すほどに。
奥義・纏い斬り - 『隻狼』
- 仏師
「傷がうずくのよ」
- 狼
「その左腕か」
(略)
- 仏師
「…斬って…くださったのじゃ…プハァー! 飲まれかけた、儂のためにな…
- 狼
「何に、飲まれかけたのだ?」
- 仏師
「…修羅」
仏師にどぶろくを振る舞った際の台詞 - 『隻狼』
こんな記事を書きました。
内容を要約すると、「人の形をしたもの」に宿る霊魂や業についての話です。
形代は心残りの幻である
ゆえに業深いものは、形代が多く憑く
多く殺した忍びは、その身に業を背負い、生きることになる
忍びの業・身業 - 『隻狼』



人の形をした器

謎の巨大注連縄人形、その股間に貼られたお札は、識者によれば「死者の霊魂」を扱うものであったご様子。対し形代とは「心残りの幻」だと言います。転じて形代に宿る不可思議な力とは霊魂の類であり、即ち注連縄人形とは「巨大な形代」であったという仮説を立てさせて頂きました。
両者が共に人の形を取るのは、その力の源がかつて正しく人に宿っていた「魂」だからでしょうか。人に宿っていた力は、人の形をしたものに宿すが相応しい、そういう事なのかもしれません。
さて、人の形をしたものに「力」が宿りやすいのであれば、人そのものはどうでしょう。その答えが「御霊降ろし」であり、「怨嗟の鬼」でした。



人という器

飴を噛みしめ、「阿攻」に構えることで人ならぬ御霊の加護を自らに降ろす
御霊降ろしは,人の身に余る御業
ゆえに飴を噛みしめ、こらえるのだ
阿攻の飴 - 『隻狼』
この炎の怪異が大見得を切るのは、「鬼」という存在が強大な「御霊降ろし」の末に生まれた示唆だと思われます。ではどんな「御霊」を降ろしたか。それこそが「怨嗟」でした。
人の、人による怨みの念。これが怨嗟の正体。そして「怨嗟」の器となった仏師、彼が籠った荒れ寺には大量のお札が。

インフル怨嗟

個人的には魔除けと解釈していましたが、検索してみると逆の意味になっているという説が見つかったりします。或いは彼は、「怨嗟」を自ら引き受けていたのかもしれませんね。
「炎は… まだ、消えませんか?」
エマ - 『隻狼』
「何度聞いても、変わりゃあしない。いくら仏を彫ろうとも、怨嗟の炎は消せぬ。押し留めるが、せいぜいじゃ」
仏師 - 『隻狼』
自分自身を「怨嗟の器(積り先)」とし、その上で押し留めようとしていたのでしょうか。
ちなみに上記の記事で書き漏らしたのですが、人の形をしたものに霊魂や業が宿るなら、「忍び義手」もまた同じもの。
忍義手には、業がこもっている
刻み込まれた大小の傷は、重ねた死闘の証だろう
使いこなすほどに、その業を背負うことになる
仏師の業・刻み傷 - 『隻狼』
仏師はあえて怨嗟や業を引き受けた、と前述しましたが、それは彼が忍び義手を捨てた事と矛盾するでしょうか。想像の余地は多分にありますが、仏師がどのようなつもりだったにせよ、やはりというべきか、彼に積もった莫大な怨嗟(業)は終には発火し、生じた炎は宿主を「鬼」へと変えたのです。



ちなみに怨嗟の鬼と見えた戦場は鬼庭刑部雅孝とのバトルエリアでもありました。鬼の名を持つ男との闘いは、先に待つ本物の鬼との闘い、その暗示だったという小話

形代と注連縄人形、人の形をしたものに遺志と力が宿るなら、必然それは人そのものにすら宿り、そして宿主を、人を超えたものへとならしめる。それが御霊降ろしであり、その果てに鬼が存在した訳です。
『隻狼』とは復讐の物語でした。戦国それ自体が人の業であるなら、戦場にて荒れ狂う「怨嗟の炎」とは、言わば復讐の火であったのかもしれません。
罪の火
こんな記事を書きました。
『DARK SOULS 3』、火の終わりを描いたあの物語には、しかし消えぬ火と称される「罪の火」が登場します。上の記事は、その正体に迫る為のものです。正直な話、考えてみても分からない点が多く残る困った記事になった印象なのですが、一つだけ自信を持って主張するなら、罪の火とは火ではありません。じゃあ何かと言えば、闇であると。
「…あんた、この種火は…暗すぎる。むしろ深淵に近いものだぜ…」
アンドレイ(罪の種火を渡した際の反応) - 『DARK SOULS 3』
だが、やがて火は消え、暗闇だけが残る
OP より - 『DARK SOULS』
例え火が消えようとも、闇だけは残る。仮にその性質を炎へと変えたなら、それは「消えぬ火」として、やはり残り続ける訳です。
「炎の形をした闇」。それが罪の火の正体だという旨の記事でした。
では如何にして闇が炎属性へ転化したか。そこには「ある禁忌」が関与していたようです。
後に混沌の火を生み出した彼女たちは 魔術師であると同時に祈祷師でもあり 故にこの杖は信仰補正を持っている
イザリスの杖 - 『DARK SOULS 3』
最高位の象徴にすぎなかった大杖は 大主教マクダネルの手で魔術杖となった
それは信仰を魔術の糧とする禁忌である
聖者の燭台 - 『DARK SOULS 3』
混沌の炎の発祥に関しては未だ以て謎が多い。しかし恐らく彼女たち自身を飲み込んだその有様から、その炎の誕生には闇が関わっていると推測します。そして「魔術師であり祈祷師」だったという彼女達の在り方もまた深く関わるのでしょう。
闇の武器は闇攻撃力を持ち信仰による補正も高くなる。
闇の貴石 - 『DARK SOULS 3』
混沌の武器は炎攻撃力を持ち理力、信仰両方の補正を受ける。
混沌の貴石 - 『DARK SOULS 3』
要するに「闇は願いを叶えてくれる」訳です。それが望みのままかはともかく。
また深みの主教たちも炎の魔術と思わしきものを扱う訳ですが、これは人が人間性という生来の闇を持つ為に、イザリスらが終ぞ実現できなかった「炎属性の魔術」が実現されたのではないでしょうか。考えてみれば、彼らは元々深み(闇)を封印する立場でありながら、その手段として自身の人間性(闇)に頼った訳です。故にこそ最後には飲み込まれてしまったのかもしれません。
肝心な事は、イザリスや深みの主教たちに共通する因子、即ち「魔術師であり聖職者」という役割、その傍には「炎」があったということ。そして祈りによって生じた炎の根源に、常に闇が関与すると仮定するなら……。
罪の都、その宮廷魔術師たちのフード
その黒く高い帽子が示唆するように 彼らはまた、神官でもあったという
宮廷魔術師のフード - 『DARK SOULS 3』
罪の都においても「魔術師でありながら聖職者」なる存在がおりました。祈りが闇を炎へ変換し得るなら、罪の都もまた条件を満たしていると言えます。故に、罪の火とは闇であると。闇に祈るものは、最期には闇に飲まれる運命なのでしょうか。深淵を覗くものは云々。ちなみに過去記事では掘り下げませんでしたが、「魔術師である」という点も重要なのでしょうね。ただ祈るというだけでは、闇は炎として応えないのかもしれない。歴史上対立してきたという聖職者と魔術師。その両輪を修める事が禁忌なのか、本当のところは不明なのですが、仮にそれを禁じた理由があるとするなら、そこには暗い炎を呼び起こす事への恐怖が根差していたのかもしれません。
さて、罪の火が闇である、或いは闇と深い関わりを持つ事を暗示する描写は、こんなところにも見られます。



イルシールとウーラシール

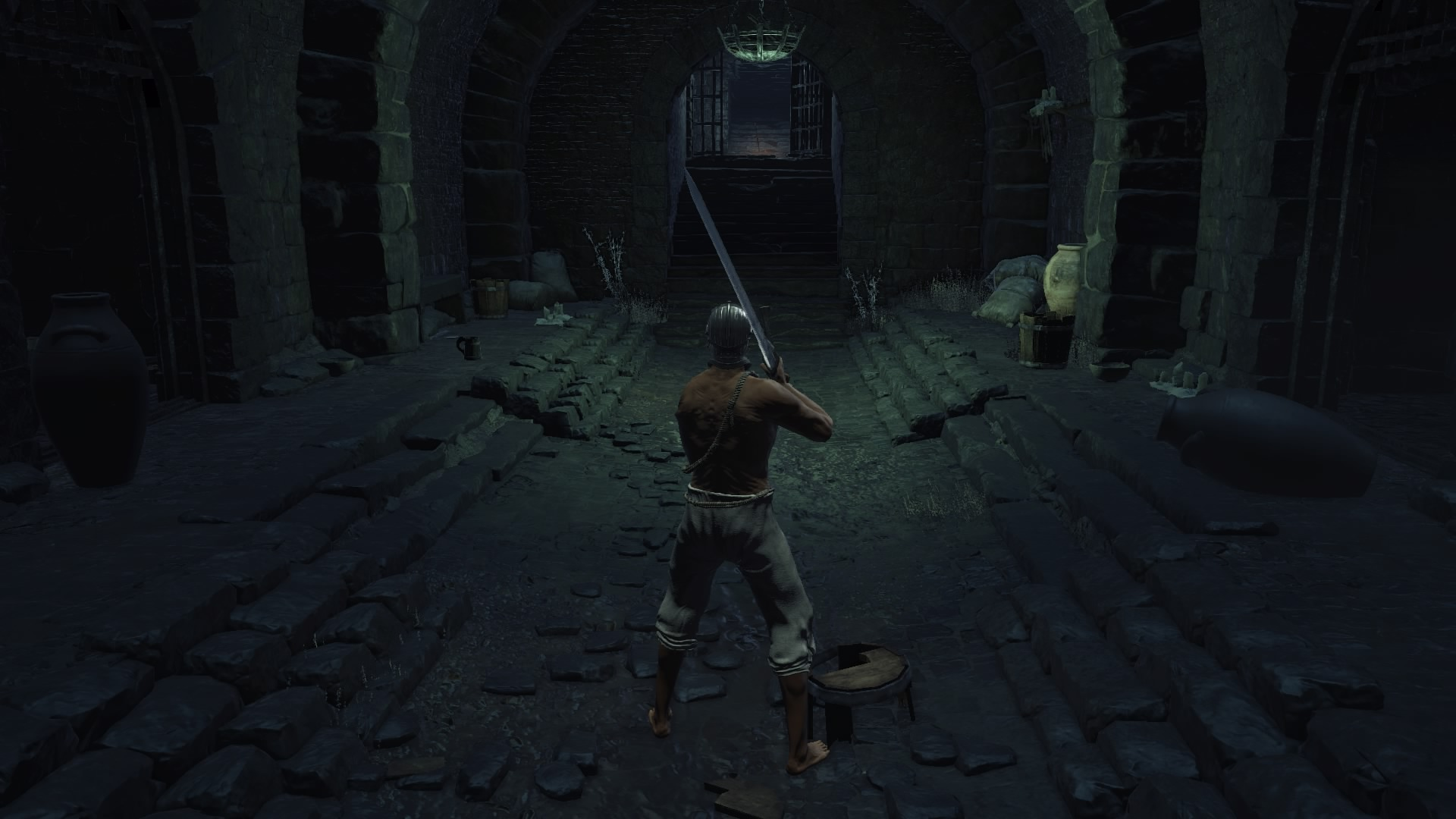
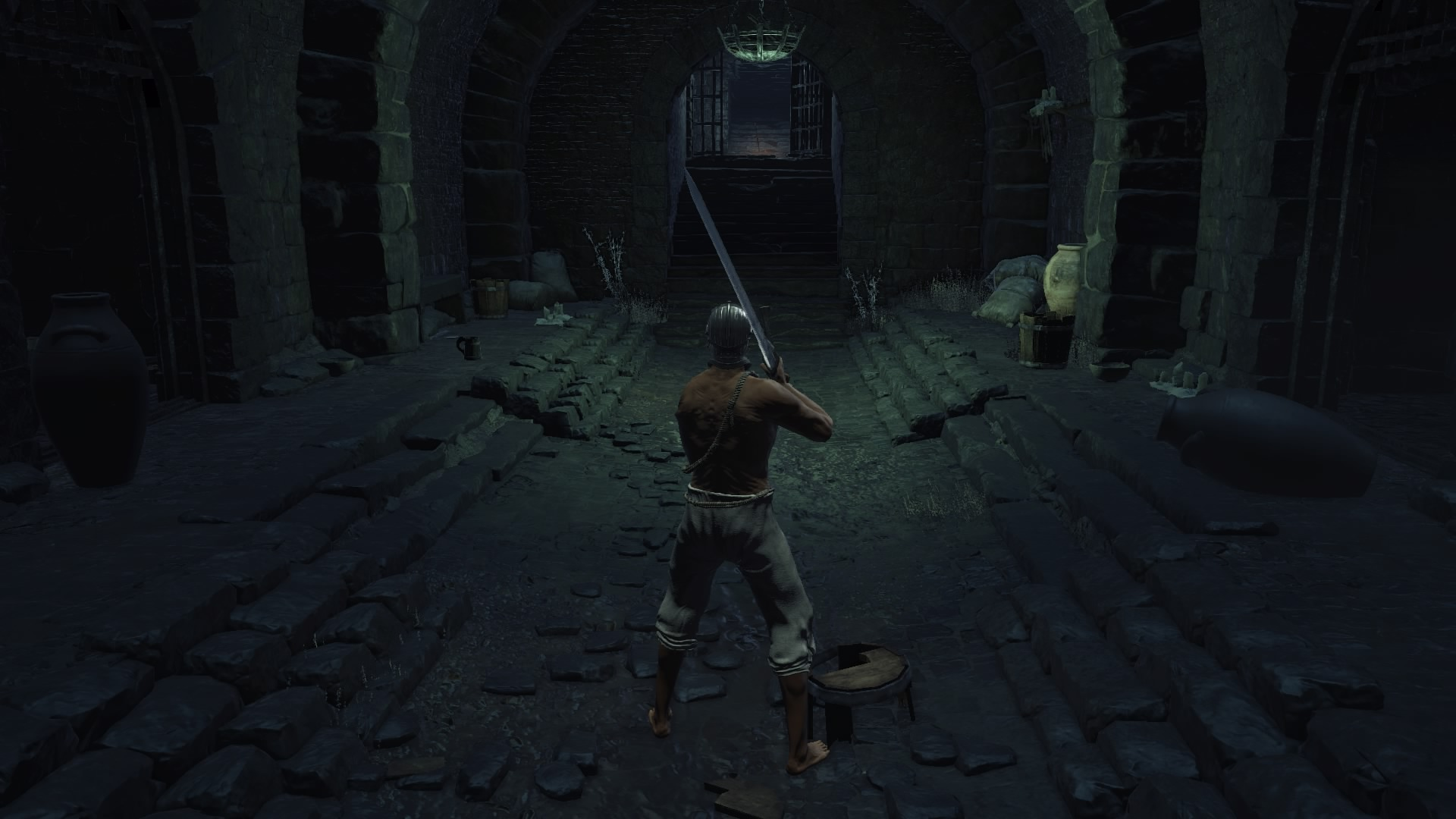

イルシールの地下牢と、ウーラシールの地下牢




罪の都と深淵の穴

イルシールの地下牢 その窓格子の鍵
だが窓の先は、底も見えない暗い穴と 滅びきった罪の都が見えるのみである
窓格子の鍵 - 『DARK SOULS 3』
「ウーラシール市街 / イルシール市街」から始まり、地下牢を経由して「暗い穴」へと辿り着く。両ルートの類似が示すのは、イルシールがウーラシールの跡地であり、罪の都とはそのまま、かつての深淵の穴の跡に興った事実を示すのか、それともその類似性から罪の都と深淵の結びつきを強調する為のものなのか。今思えば立地こそ異なれど、イルシールの地下牢に捕らえられた巨人とは、ウーラシールに捕らえられたゴーを示唆する意味もあったのかもしれません。
まあ真実は不明です。重要な事は一点。「罪の火は闇である」。もしかするなら罪の都の宮廷魔術師、彼らの神官としての祈りに、深淵という巨大な闇が応えた結果生まれたものが、消えぬ「罪の火」だったのではないか。ざっくり言うと、過去記事ではそんな感じの事を主張した訳です。
「…あんた、この種火は…暗すぎる。むしろ深淵に近いものだぜ…」
アンドレイ(罪の種火を渡した際の反応) - 『DARK SOULS 3』
「属性」とは所詮、表面的な振る舞いに過ぎないのでしょう。幾ら炎として揺らめこうとも、その本質は闇。故に罪の火は闇がもたらす異形をそのまま残します。

罪の都と深淵の穴


「腕」の怪物、深淵の主と罪の異形

「マヌス(manus)」とは「腕」の意。深淵の主マヌスとは、言わば「腕の怪物」でした。名の通り怪物は巨大な腕を振るいます。そして罪の都の異形もまた腕を象っている。なぜかと言えば、人間性とは「欲」を象徴するものでもあるからです。
「欲しい」という意志の具現こそが、人の本質たる「運」へと向かい、その暴走こそが「腕」の怪物を生む。闇に由来する以下の怪異たちも同様でしょう。



腕の怪異たち。




吸精

ダークレイスの「吸精」などは特に象徴的で、罪の異形もまた同様の業を用います。小ロンドが深淵に飲まれた地であるなら、同じく「腕」の異形が跋扈する罪の都もまた深淵である示唆と取れるでしょうか。深淵の中枢には、常に「腕」の怪異が現れるのです。
『DARK SOULS』は火と闇の物語でした。火の終わりと入れ替わるように現れた「罪の火」は、しかし消えぬ故に火ではなかった。どれほど炎に似ようとも、その本質は闇。火無き世にあって闇だけが常しえに残り続けるのなら、或いは未だ、この物語は完結していないのかもしれません。
深淵は流転する
海物語 -深み-
だが、やがて火は消え、暗闇だけが残る。歴史の初めから示唆されていた事実は、未来へとどのような影響を及ぼすのでしょうか。
人の内にある最も重いもの。人の澱み
それはどんな深みにも沈み 故にいつか、世界の枷になるという。
人の澱み - 『DARK SOULS 3』
深みは本来、静謐にして神聖であり 故におぞましいものたちの寝床となる
それを祀る者たちもまた同様であり深い海の物語は、彼らに加護を与えるのだ
深みの加護 - 『DARK SOULS 3』
人の内にある重きもの、かねて「人間性」と呼ばれていたそれはいつしか、世界の深みへと澱んでいくようです。そしてその先で、それらは「おぞましいもの」として芽吹き、或いは孵化し、人の世を底から蝕んでいく。先に待ち受けるそんな時代を、さる聖者は「深海」と称したようですが、闇を基とした「罪の火」もまた、その「おぞましいもの」の一種として今後世界を蝕んでいく事が伺える訳です。
こんな記事も書きました。
上述の内容にもう一歩だけ踏み込んだものとなっております。結論から言えば罪の火は怨念の火であるというもの。





深淵に沸く怨念

ウーラシール、小ロンド遺跡には共に亡霊(≒人間性)が湧く。では同じく深淵に飲まれた罪の都には? その答えを「罪の火」へと求めました。
罪の火は闇である。そして人のみに見られる「亡霊」という現象が、それ故に人間性(闇)から成り立つなら、特定の条件下においてそれは「炎属性」へと転じ得る。罪の火は深淵そのものが着火した訳ではなく、人々の怨みを火種とした「ウィル・オ・ウィスプ(火の玉)」だった。そのようなアプローチでした。
人の怨嗟は、燃ゆるのです。
これからの罪の話をしよう
色々述べてきましたが、罪の火の「罪」が何かは分からないまま。しかし「罪」それ自体の行末に関しては思う所があります。
黒髪の魔女ベルカの伝える奇跡
短時間に大ダメージを受けると、自動的に反撃する
罪とは罰せられるべきものであれば 罪を定義し、罰を執行するのが 罪の女神ベルカの役目であろう
因果応報 - 『DARK SOULS』
陰の太陽グウィンドリンに仕える 暗月の剣の騎士たちに与えられる神秘のオーブ
彼らはつまり、神々の復讐の刃なのだ
青い瞳のオーブ - 『DARK SOULS』
人(NPC)や他世界のプレイヤーキャラクターを害したもの、或いは神の領域や何らかの誓約で禁じられた行いに対して罪は背負わされました。テキストに倣うなら、それらを罪と規定していたのは女神ベルカであったようです。また罪に対しては罰ないし復讐が執行され、その刃を司るのは陰の太陽グウィンドリンでした。人は、犯す罪でさえ、対する罰に至るまで神々により管理されていたという話。
では、例えば神の威光が届かない深淵という領域において罪と罰はどうなるのか。復讐はどう果たされるのか。その答えが小ロンドやウーラシールを跋扈する亡霊の類なのではないかと。野放しになった人の怨念、復讐霊のなりそこない、それが「亡霊」たちの正体なんじゃないでしょうか。神の律する罪と罰の上ではなく、ただ怨みのままに仇を討つ。怨念が火に転じるならば、神の手を離れた人々の、自由意志に基づく「復讐」、その一つの形こそが罪の火だったんじゃないかと思う訳です。
火の時代は終わりを迎えます。火を存在の根拠とする神々は、火と共に世界から消え去る運命にある。しかし人々が罪悪や復讐から解放される事はないのでしょう。罪の都とは次代のモデルケースでした。
「罪」とは何だったのでしょうか。
ヨーム関連のテキストを読む限り、どうも罪の都は戦争をしていたようです。もしも都の罪と怨念が戦と関わりあるものであるなら、罪の火の火種はそこにこそありそうです。戦争とは人の常。争いが死を量産し、死者の怨念が火を招くのなら、争いが大きければ大きいほどに、招かれる火(闇)もまた……。
深淵の再来
そして火継ぎの歴史は終わりを迎えました。ソウルの力も消えて無くなり、唯一残った「闇」だけが人々へ神秘をもたらします。しかし古い神話などとうに忘れた人々は、その力が果たして「闇」だと認識しているのでしょうか。はじまりの火の現出が初めて世界を多様に切り分けたのとは逆に、闇だけしか残らない世界において、それはもう闇とは呼ばれないのかもしれません。
ある者は述べました。
「竜咳になった者は…人が、人として、生きるための、当たり前の力を、奪われています。ゆえに、血が淀むのでしょう」
エマ - 『隻狼』
それは火が絶えた後も、依然として人だけが備える力。「人が人として生きるための当たり前の力」、即ち「人間性」です。
竜胤を巡る「淀み」は勿論、形代に宿る輝きも、巨大な注連縄人形を動かす力の何もかもが、元は人だけが持つ「人が人として生きるための当たり前の力(人間性)」によって成り立っているのでしょう。そして人だけの特性と言えた「亡霊」もまた、この時代においては健在でした。
罪と罰が人に課せられた業であるならば、神無き後の世においてもやはり人は罪を犯し、罰を受けることになります。復讐霊というシステムは消えても、復讐の遺志は無くならない。野放しになった亡霊は、その怨みのままに、仇討ちの刃を振り下ろすんです。

仇討ちの霊 に侵入されました!

夕刻は、逢魔が時
夜の闇が日を飲み込もうとする一時
強い怨念が仇討ちの霊となり、現れることがある
逢魔が時 - 『隻狼』
かつて復讐霊として厳に管理されたそれらは、今や神の手を離れ「仇討ちの霊」として彷徨います。
そして、やがて亡霊(闇)は火を招く。
忍義手には、業がこもっている
刻み込まれた大小の傷は、重ねた死闘の証だろう
使いこなすほどに、その業を背負うことになる
仏師の業・刻み傷 - 『隻狼』
この奥義を最後に、仏師は忍義手を捨てた。
極め、殺しすぎた。怨嗟の炎が漏れ出すほどに。
奥義・纏い斬り - 『隻狼』
過去に述べました。「慈悲」こそが怨嗟の積り先となる条件だと。人斬りは戦国の嗜み。しかしそんな中にあって、それを罪と受け入れてしまう「慈悲」こそが「業(罪)の器」たる条件なのではないかと。
忍びは人を殺すが定めなれど、一握の慈悲だけは、捨ててはならぬ…
楔丸 - 『隻狼』
ある男が、修羅になりそこない、怨嗟の炎の積り先となった
戦いの残滓・怨嗟の鬼 - 『隻狼』
「…あんた、覚えておきな。怨嗟はもう、積もる先を失った。戦が続けば、世はもっと酷いことになるだろう。…だからって、あんたが替わりになることはないんだよ」
おばあちゃん - 『隻狼』
人斬りを罪と捉える慈悲はその者の「楔」となり、しかしむしろそれが外れた反動こそが人を修羅に落としてしまうのかもしれません。或いは闘いを捨てればまだ引き返せる。ですが、あろうことか後付けされた忍義手が、その持ち主を業の、罪の、怨嗟の集積体として完成させてしまった。
怨みが、人の遺志(ソウル)が「闇」と不可分であるなら、そして一所に積もった多くの怨嗟(闇)が「深淵」と称すべきものへと変わるとするならば。
「…あんた、この種火は…暗すぎる。むしろ深淵に近いものだぜ…」
アンドレイ - 『DARK SOULS 3』
怨嗟の炎は火に非ず。

怨嗟の鬼は、


深淵の主は、

故に、深淵の中枢には、「腕」の怪異が現れる。

人を苗床にして


深みより出でる。

怨嗟の炎。それはとてもとても古い時代に、罪の火と呼ばれた怨みの火。
「ウィル・オ・ウィスプ」は人魂であり火の玉。しかしこうも訳されます。「鬼火」と。
深淵は流転する。世界の底へと沈んだそれは、炎の如く振る舞いながら、未だ健在でした。
怨嗟の主
怨嗟の鬼第二形態時の追尾火球を動画に入れ忘れてますが、個人的には「追う者達」がベースかなあと思ってます。穢れのエレナが放ってきた一発ずつのアレが近い。ちなみに怨嗟のあの火球、人影が確認できるので巨大な形代かなあと思ってたんですが、どうも鬼仏のシルエットらしいですね。
怨嗟の主
ところでマヌスとは何だったのでしょうか。
それは尋常のソウルではなく どろりとして生あたたかい、優しい人間性の塊である
マヌスは、古くとも明らかに人であった
人間性を暴走させ、深淵の主となった後も ずっと寄る辺、あの割れたペンダントを求めていた
深淵の主マヌスのソウル - 『DARK SOULS 3』
「深淵など、まさにウーラシールの自業自得。出っ歯の大蛇に謀られ、墓を掘り、古人の躯を辱めるなど」
素晴らしいチェスター - 『DARK SOULS』
「友アルトリウスを蝕んだ深淵の闇は いまやこの国、ウーラシールを飲み込もうとしている。…おそらく、滅びは避けられまい。だが、たとえ、闇の蛇に唆されたとして。彼らは自ら望み、あれを起こし、狂わせたのだ」
鷹の目ゴー - 『DARK SOULS』
どうも古人の眠る墓を掘り起こした事が深淵の主を生んだ切欠になったようです。しかし「マヌスという人物を呼び覚ました」のか、「呼び覚ました何かがマヌスという人物を深淵の主に変えてしまった」のかは解釈が分かれると思います。個人的には後者を推したい。
以前書いた事ですが、恐らくその墓とは闇よりダークソウルを見出した人の始祖、「誰も知らぬ小人」その人のものであったと考えています。それがウーラシールの「マヌス」という人物に憑依し、その「大いなる御霊降ろし」が結果として「深淵の主」をもたらした。深淵の主とは個体名ではなく、呼び起こされた深淵の「宿主」となった怪物の総称だった訳です。怨嗟の炎がある種の深淵であるなら、怨嗟の鬼もまた深淵の(宿)主だったと言えます。
振り返ってみて、『DARK SOULS 2』において最初期に倒す「名を禁じられた者たち」4者が「古き死者のソウル」「古き白竜のソウル」などをドロップする事から、あれらは恐らくかつてはじまりの火から「王のソウル」を見出した者達の成れの果てです。つまり『1』のマヌスを巡る騒動、「最初の王の遺志が人に憑依する」という構図は、そのまま『2』への前振りになっていたのではないか。そういう逆算からマヌスの正体へと思いを馳せる事が可能でした。
そして遠い未来、日ノ本。戦国時代末期の北国「葦名」において、悲劇は繰り返されました。
誰も知らぬ小人のソウルが未だ残っていたとか、そんな話ではありません。しかし「人間性」がダークソウルの欠片であり、それが例え気が遠くなるほどの時間を経て、忘れられ、砕かれ希釈されたとしても、闇は常しえに残り続ける。ならば手を変え品を変え、深淵は幾度だって現出を試みるのでしょう。ウーラシールの悲劇は、これから先も再演され続ける訳です。怨嗟の鬼が深淵の主の似姿であったのは、それを強く示唆する為のものでした。
戦場にいたのは、怨嗟の炎に飲まれた、隻腕の鬼であった
戦いの記憶・怨嗟の鬼 - 『隻狼』
「隻腕の鬼」と言いつつ、その怪物には忍義手を再現するような形で巨大な炎の腕が存在していました。「マヌス(manus)」とは「腕」の意。忍義手という仕掛けがそも、人の本質的な「闇」を刺激するものであったのかもしれません。となると面白い描写が思い浮かびます。
仏師「傷がうずくのよ」
狼「その左腕か」
(略)
仏師「…斬って…くださったのじゃ…プハァー! 飲まれかけた、儂のためにな…」
狼「何に、飲まれかけたのだ?」
仏師「…修羅」
狼と仏師の会話より - 『隻狼』
一心「こいつはな、修羅酒とも言う。…昔、儂は…修羅を…いや、修羅の如きものを、斬ったことがある」
狼「それは、一体…」
一心「斬り続けた者は、やがて、修羅となる。何のために斬っていたか…。それすら忘れ、ただ斬る悦びのみに、心を囚われるのじゃ。お主の目にも、修羅の影があるぞ」
狼と仏師の会話より - 『隻狼』
なぜ一心は仏師の、当時「飛び猿」として名を馳せていた忍びの「腕」を切断したのか。思うに肥大化を始めていたんじゃないでしょうか。闇は「欲」の根源。それこそが人の本質。故に人間性から端を発した怪異は欲を象徴する「腕」を特徴とした外形となりやすい、というのは上述しました。その果てがマヌス(腕)です。一心は飛び猿の外見的変化から、奥底に疼く深淵の兆候を見抜いたか、或いは心根の変容から、その業の中核が「腕」だと見抜いたのかもしれません。「深淵」の脅威など知る由もないでしょうに。さすがは剣聖と言ったところでしょうか。
そしてもう一つ。炎の魔術、罪の火。闇から生み出された炎の傍らには「魔術師であり聖職者」という二道を修めた在り方が確認できるという話をしました。未来において「魔術師」という者がどのように形を変えているかは不明ですが、形代に宿る業を操り、忍び技を放つ様は「魔術師的」と言えるでしょうか。戦国末期において日ノ本の人々がどれほど信仰に対し熱心だったかは分かりかねますが、「元忍びの仏師」という在り方は、「魔術師であり聖職者でもある」と解釈できなくもない。「仏師」が罪の火、怨嗟の炎の器として選ばれた背景には、もしかするとそういった事情もあったのかもしれません。逆に仏師がそうであった(かもしれない)ように、マヌスもまた魔術師であり聖職者だったなんてことが推し量れるかもしれませんね。
今ふと思いましたが、ウーラシールとイルシールが「牢獄」を経て「深淵(暗い穴)」に至ったという構図。そのまま葦名における「捨て牢」から身投げ場の「暗い穴」に適用できるんですが……ただのフロムの手癖なのか、こちらが想像する通りの意図があるのか。
そんな訳で深淵は人の業に根差すが故に常しえであり、世界のどこからでも噴出する迷惑極まりない不滅の「災禍」と言えます。しかし忘れてはならない事がまだあります。深淵が不滅であるなら、それを監視する者もまた、不滅であるのだと。
深淵と狼
深淵の最中、或いは火の陰りにおいて神の力が弱まり、それ故に人の亡霊が消えぬ火に転じるのなら、その現象は何も罪の都に限ったものではなかったのかもしれません。或いはただ、ロードランやロスリックの外側において、神の管理とはそも行き届いていなかったのか。どちらにせよ罪の火、怨嗟の炎が人のソウルに由来するものであるなら、火継ぎを巡る領域、その外界であっても、ウーラシールの悲劇は繰り返されていた可能性があります。
東の地に伝わる独特の大弓
彼らの神話によれば、角を持つ巨人 鬼を討つために使われたという
鬼討ちの大弓 - 『DARK SOULS 3』
『DARK SOULS』が『隻狼』の遠い前日譚であり、罪の都が葦名という舞台の前振りだったとするなら、罪の都に「鬼討ちの大弓」が配置されていたのは、つまりそういう理由だったんじゃないでしょうか。
罪の都において「鬼討ち」装備を抱いて朽ちていたその誰かは、当時の「東の地」より、怨嗟(深淵)の気配を察して馳せ参じたのかもしれません。その在り方は、さながら深淵の監視者に似ます。深淵が世界のどこからでも湧き出るならば、その災禍を討たんとする者もまた世界中に存在するんです。希望は潰えていなかった!
ファランの狼血の主 深淵の闇に汚れた騎士の大剣
狼の騎士は、最初の深淵の監視者であり その剣もまた闇の眷属に大きな威力を発揮する
狼騎士の大剣 - 『DARK SOULS 3』
かつて騎士は終に倒れ、使命と狼血を残した
それはファランの不死隊のはじまりであり 監視者たちはその甲冑に、自らの最期を見る
狼騎士の鎧 - 『DARK SOULS 3』
血を分け誓った深淵の監視者たちの王の資格は、その狼血にこそあった。
王の薪(深淵の監視者) - 『DARK SOULS 3』
狼血を分けた監視者たちのソウルは また狼血の主のソウルでもある。
狼血のソウル - 『DARK SOULS 3』
「狼騎士」アルトリウスは、かつてマヌスの深淵に飲まれて倒れました。大いなる深淵狩りの伝説は、しかし実際にはどこぞから現れた不死人が果たした訳ですが、その後アルトリウスの遺志は「血」に宿り、ある者達へと継承されていたようです。それがファラン不死隊。監視者とも称される彼らは、深淵に対する狩人でした。
「…ファランの不死隊は、不死人の旅団。狼の血に誓い、深淵を監視し、その兆しがあれば一国ですら葬り去る」
ホークウッド - 『DARK SOULS 3』
……「こいつらも大概迷惑だな」とか言ってはいけません。しょうがないでしょ、深淵よりはマシなんです。しかしながら、血という形でアルトリウスの使命を最も色濃く継いだのは確かにファラン不死隊であったかもしれませんが、東国より来た鬼討ちもまた「深淵を狩る者」だとして、何ものも介さず、その使命は広く伝わっていたのかもしれません。
「…あんた、覚えておきな。怨嗟はもう、積もる先を失った。戦が続けば、世はもっと酷いことになるだろう。…だからって、あんたが替わりになることはないんだよ」
おばあちゃん - 『隻狼』
大手門エリアのおばあちゃんは訳知り顔でこんな事を言いますが、彼女は遠い遠い昔にあった「東の地の神話」を継承する者だったのかもしれませんね。或いは深淵それ自体が人の業であるなら、深淵に対する警戒心もまた、人に備わる防衛本能と解釈すべきでしょうか。
深淵を監視する時、深淵もまたこちらを監視している。故に深淵とその監視者は不可分なのです。例えその大元たる狼血が途絶えたとしても変わらない。きっとそれは「運命」なのでしょう。そして運命は、深淵に対する狩人を再びあつらえました。



運命は再演される。

ファンの間において、こんな逸話があります。曰く「アルトリウスは利き腕を潰されていた」。なるほど、確かに劇中それを振るう様はどこかぎこちない……と見えなくもない。
由来の知れぬ古い大剣
数多の所有者を経て フォローザの放浪騎士ゴルディンに渡ったが 彼の死を境に途絶えた
使い手は皆、名を馳せた剣士となったが 彼らは左利きの剣士であったという
栄華の大剣 - 『DARK SOULS 2』
「栄華の大剣」はアルトリウスの大剣と同じ形状であり、また左手に装備する事でそのモーションが狼騎士そのものとなります。この事から上述した「アルトリウスの利き腕は左手だった」という読み解きが出来るのですが、或いはその逸話を汲んだ結果生まれたファンサービスに過ぎなかったという見方も可能でしょう。実際のところは不明です。ここで重要な事は、アルトリウスの片腕が不自由であったという一点。あの時あの場所において、彼は「隻腕の狼」でした。
深淵は流転し、運命は再演される。大忍び梟が戦場で拾った飢えた狼が、何か特別な血を受け継いでいたというような事は無いのでしょう。誰かから使命を吹き込まれたとか、前述した人の防衛本能だとかも、きっと関係ない。本当に、それは唯の偶然として、「狼」の名を与えられた隻腕の忍びは、再来した深淵へと相対する事となったんです。御子の忍びは図らずも、戦国末期に現れた「深淵を狩る者」として、その役割を果たしたのでした。
深淵を狩ったというアルトリウスの伝説は しかし道半ばで終わっていた
あるいは堕ちた彼を討ち、誇りを救った物が 実際の伝説の主、深淵を狩る者となるのだろうか
アルトリウスのソウル - 『DARK SOULS』
気が遠くなるほどの過去。誰もが忘れてしまった昔、道半ばで終わっていたはずの深淵狩りは、しかしそれを継ぐ者を遺しました。例え使命を知らずとも、敗れる事があろうとも、形を変え、逆襲はきっと果たされる。
『隻狼』とは、復讐の物語でした。
残り火
しかし、深淵とは強大です。時に、それに抗する者をも飲み込んでしまう。
最古の監視者であるアルトリウスをはじめ、ファラン不死隊も最期には深淵へと沈んだように思います。また深みの主教たちは、元々は「深みの封印者」であり、彼らもまた相対した故に深淵の一部に成り果てました。新たな深淵の宿主、怨嗟の鬼を討ち果たし得た狼も、一つボタンを掛け違えれば、やはりその末路は……。

堕ちた狼

この画像、面白いのは狼の隻腕から漏れ出す怨嗟の炎(罪の火)と、周囲に燃え盛る炎の色が異なる点です。怨嗟の炎は火に非ず。よって尋常の炎色ではありえないのでしょう。しかし、だとして、周囲の炎の火元はどこでしょうか。
怨嗟の炎の予兆のようなものと捉えてもいいですし、暗躍する梟が放ったものと考えてもいいかもしれません。しかしこの炎は一心の登場と共に燻り始めます。ならば順当なところで、これは一心がもたらした炎と考えていいんじゃないでしょうか。

一心の火

一心もまた剣技を極めた者。しかし修羅ではない。それは慈悲ある故に堕ちた狼と、戦国武将らしい精神を持つ一心との対比なのでしょう。尚且つ炎の色が違う。闇を基とする怨嗟の炎と異なるならば、葦名一心のそれは、如何なる理から成り立つ炎なのか。
然り、その炎は、闇に非ず。
「はじまりの火が、消えていきます。すぐに暗闇が訪れるでしょう。...そして、いつかきっと暗闇に、小さな火たちが現れます。王たちの継いだ残り火が」
火防女 - 『DARK SOULS 3』
火継ぎの時代が最期を迎え、暗闇の時代へ。しかしそんな中にあって、最初のそれとは比べるべくもないほど小さくなろうと、それでも誰かの中に「火」は受け継がれていく。紡がれてきた物語は、例え形を変えても終わる事は無いのだと、火防女はそう呟きました。
「火」です。葦名一心のそれは、いや、これこそが火。怨嗟でも、混沌でもない、かつて世界を切り分けた、真なる「はじまりの火」の残滓であったのだと、最期にそれだけ述べておきたい。
『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE Official Artworks』には非常に興味深いイラストが掲載されています。詳しくはお手元のアートワークスを開いて頂くか、こちらから確認して頂きたいのですが、薬師エマの初期案として、彼女は目を包帯で覆った姿として描かれています。
これを受けてネット上の評判では「いつものフロム」「和製かぼたん」などとネタにされていましたが、案外、本当にそうだったんじゃないでしょうか。
最初の火防女の瞳であるといわれる
後に全ての火防女が失う光そのもの
それは瞳無き火防女に 見るべきでないものを見せるという
火防女の瞳 - 『DARK SOULS 3』
フロムの定める盲目は火防女の象徴と言って良いでしょう。開発初期において、火の無き時代に、それでも残る火を求め、「火防女エマ」は剣聖の元へと訪れていたのかもしれません。もっとも今となっては分かりませんが。
黄泉帰りは、その者の全盛の形を取る
即ち、死闘を重ね、貪欲に強さを求め、あらゆる技を飲み込もうとした一心だ
一心は最期まで死闘を求め、それは叶った
戦いの残滓・剣聖 葦名一心 - 『隻狼』
老境の一心は、研ぎ澄まされた刃である
技を研ぎ澄まし、束ね、葦名流をなすうち、無駄は見事に削ぎ落とされた
剣の心技を極めた者。まさしく剣聖であった
戦いの残滓・葦名一心 - 『隻狼』
若かりし全盛の一心と、老境の一心。設定上どちらが強いかは議論が分かれるでしょう。テキストを読む限り、「全盛」という言葉は一心の貪欲さに対して掛かっているのであり、しかしそんな状態にあって尚、一心は「火」を操る事は無かった。では老境の一心が勝るかと言えば、それは結局わかりません。火の有無など、単純に「強さ」の指針にはならないかもしれない。しかしながら、やはり老いさらばえた先に一心が至った境地は、とても偉大なものであったように思えてならないのです。
英雄たちの内にある残り火
火の無き灰たちが終に得られず 故に惹かれるもの
残り火 - 『DARK SOULS 3』
火の時代は終わり、誰もが遠い神話など忘れた、人類時代の戦国末期。不死ですら無い一人の老武士が、いつか「火」の境地へと至りました。それは古き英雄の境地であり、彼はただ剣の極みを以て、神話の領域へと並んだのです。

英雄 葦名一心

剣聖 葦名一心、火の無き時代の「英雄」でした。
まとめ
さいごに
『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』、「The Game Awards 2019 - Game of the Year」受賞おめでとうございます。どちらにせよ年内にアップしようと思っていた記事でしたが、それでも筆に熱が籠り申した。まだまだ書きたい事は控えていますが、取り合えず今年はこんなものでしょうか。では皆さま、また来年。良いお年を。